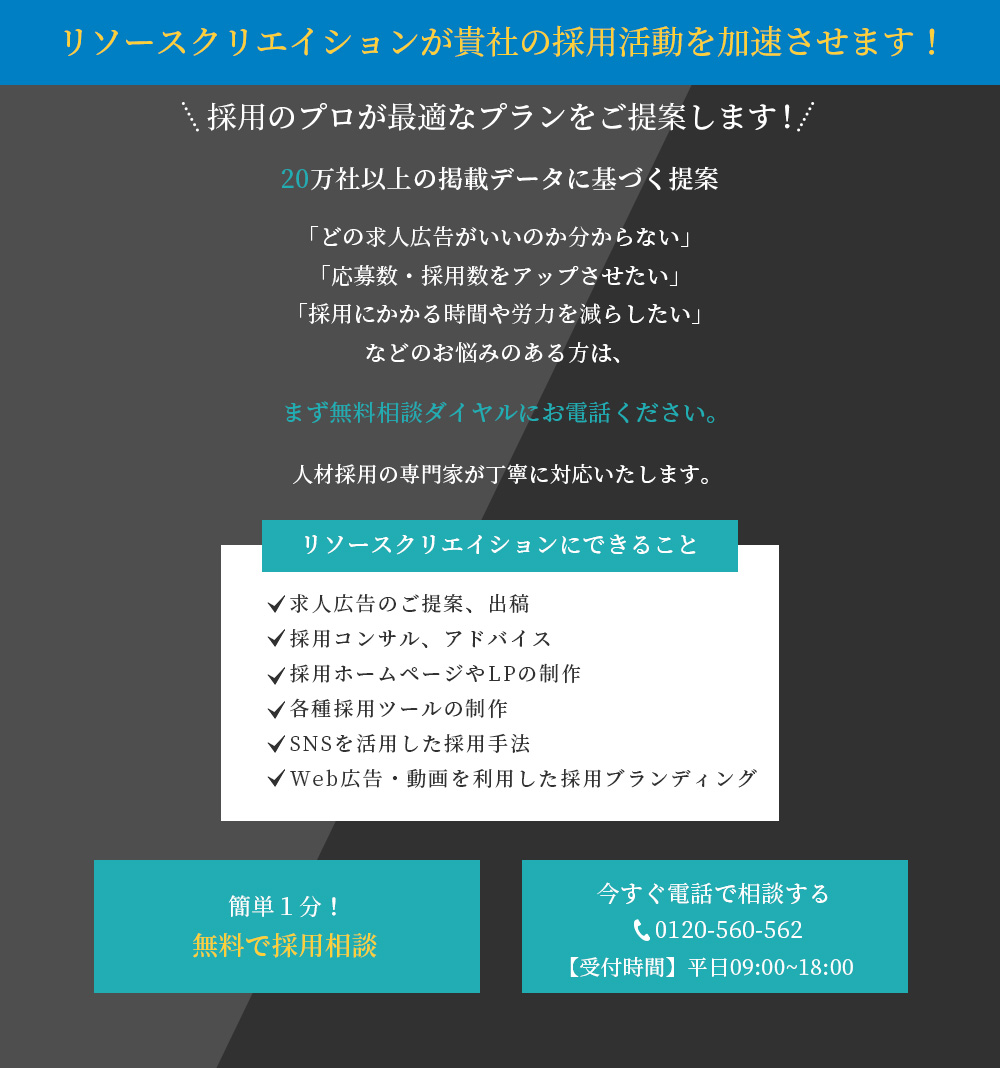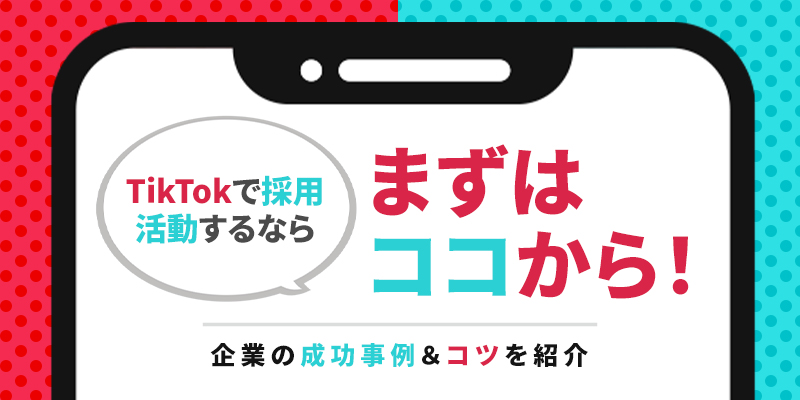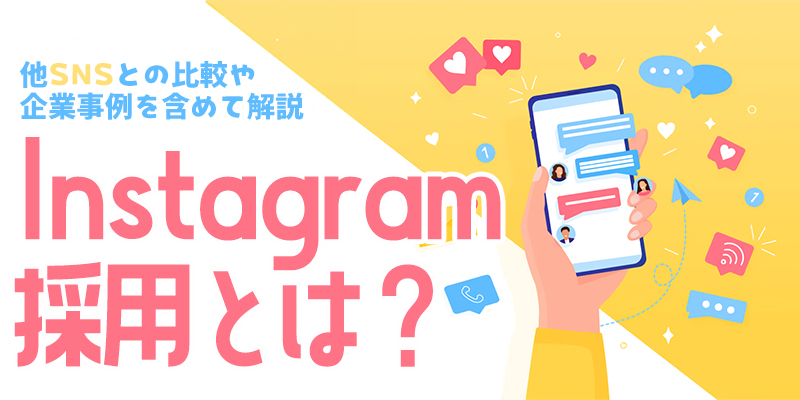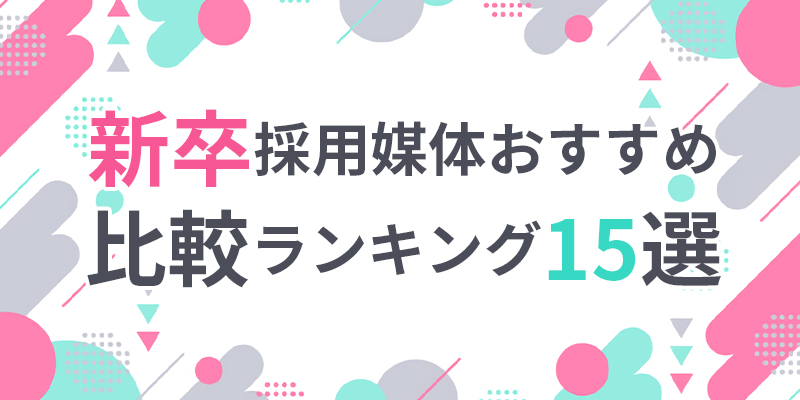SNS戦略
【2025年版】SNS採用完全ガイド|Z世代に響く始め方から成功事例、主要5媒体の運用術まで
更新日:2025.11.11

Z世代の採用競争が激化する中、従来の手法だけでは"優秀な人材の確保"が難しくなっています。
そこで注目されているのが、SNSを活用した採用活動です。
例:Tiktok → ユイカとヒロシ
Instagram → 株式会社リソースクリエイション
Youtube → RCの部屋
この手法は、企業のリアルな魅力を伝え、候補者と直接的な関係を築く上で非常に有効とされます。
この記事では、SNS採用の基本的なやり方から最新トレンド、具体的な始め方、そして各媒体の成功事例までを網羅的に解説し、採用戦略をアップデートするための実践的な情報を提供します。
まずは基本から!SNS採用(ソーシャルリクルーティング)とは
SNS採用とは、ソーシャルリクルーティングとも呼ばれ、
X(旧Twitter)やInstagram、Facebookなどのソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を活用して行う採用活動全般を指します。
具体的には、企業が公式アカウントを通じて自社の魅力や社風、働く社員の様子などを発信し、
求職者とコミュニケーションを図りながら採用につなげる手法です。
従来の求人広告とは異なり、候補者と直接的かつ双方向のやり取りが可能な点が大きな特徴です。
▼もっと詳しく知りたい方▼
こちらをクリック
X(旧Twitter)やInstagram、Facebookなどのソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を活用して行う採用活動全般を指します。
具体的には、企業が公式アカウントを通じて自社の魅力や社風、働く社員の様子などを発信し、
求職者とコミュニケーションを図りながら採用につなげる手法です。
従来の求人広告とは異なり、候補者と直接的かつ双方向のやり取りが可能な点が大きな特徴です。
▼もっと詳しく知りたい方▼
こちらをクリック
Z世代の採用にSNSが不可欠とされる2つの背景
現代の就職活動において、特にZ世代を対象とした新卒採用でSNSの活用が不可欠とされています。その背景には、Z世代が情報収集の主要ツールとしてSNSを日常的に利用している実態があります。
26年卒の学生が就活準備でSNSを使っている割合は、68.2%の学生が就職活動でSNSを活用しています。彼らは企業ウェブサイトの公式情報だけでなく、SNS上のリアルな口コミや社員の生の声を重視するため、従来の求人媒体だけでは効果的なアプローチが難しくなっているのです。
参照データ:https://career-research.mynavi.jp/column/20250115_91304/(マイナビキャリアリサーチLab)
26年卒の学生が就活準備でSNSを使っている割合は、68.2%の学生が就職活動でSNSを活用しています。彼らは企業ウェブサイトの公式情報だけでなく、SNS上のリアルな口コミや社員の生の声を重視するため、従来の求人媒体だけでは効果的なアプローチが難しくなっているのです。
参照データ:https://career-research.mynavi.jp/column/20250115_91304/(マイナビキャリアリサーチLab)

企業にもたらすSNS採用の4つのメリット
SNS採用を導入することは、企業にとって多くのメリットをもたらします。 転職市場には現れていない優秀な人材へアプローチできるほか、採用にかかるコストを削減する効果も期待できます。
また、企業のリアルな情報を発信することで、候補者とのミスマッチを防ぎ、入社後の定着率向上にも寄与します。 ここでは、SNS採用が企業にもたらす具体的な4つのメリットについて、それぞれ詳しく見ていきます。
しかしSNS採用では、今すぐの転職は考えていないものの、良い企業があれば検討したいという「潜在層」にもアプローチが可能です。
日常的な情報発信を通じて自社の魅力を伝え続けることで、こうした潜在層に自社を認知してもらい、将来的なキャリアの選択肢として認識させることができます。 特に優秀な人材ほど知人からの紹介などで転職を決める傾向があり、中途採用においてSNSを通じた関係構築は有効な手段となります。
オフィス環境、社員同士の交流、社内イベントの様子などを写真や動画で共有することで、候補者は社風や働く人々の雰囲気を直感的に理解できます。 このような継続的な情報発信は、単に応募者を集めるだけでなく、企業の価値観に共感する「ファン」を育てる採用広報活動となります。
実際に、株式会社リソースクリエイションでも、SNSを活用して「働く人の雰囲気」や「社内イベントのリアル」を継続的に発信した結果、
新卒エントリー数が 約300名 から、
2026年卒では 4,000名 を超えるまでに増加しました。
単に母集団を増やすだけでなく、「この会社で働きたい」と思ってくれるファン層が厚くなったことで、自社にマッチした人材からの応募が自然と集まる状態に近づいています。
結果として、自社にマッチした人材からの応募が増え、
エンゲージメントの高い採用を実現できる可能性が高まります。
▼もっと詳しく知りたい方▼
https://rc-group.co.jp/contact/
また、企業のリアルな情報を発信することで、候補者とのミスマッチを防ぎ、入社後の定着率向上にも寄与します。 ここでは、SNS採用が企業にもたらす具体的な4つのメリットについて、それぞれ詳しく見ていきます。
転職市場に出てこない潜在層にもアプローチできる
従来の求人サイトや転職エージェントでは、主に積極的に転職活動を行っている「顕在層」へのアプローチが中心でした。しかしSNS採用では、今すぐの転職は考えていないものの、良い企業があれば検討したいという「潜在層」にもアプローチが可能です。
日常的な情報発信を通じて自社の魅力を伝え続けることで、こうした潜在層に自社を認知してもらい、将来的なキャリアの選択肢として認識させることができます。 特に優秀な人材ほど知人からの紹介などで転職を決める傾向があり、中途採用においてSNSを通じた関係構築は有効な手段となります。
企業のリアルな魅力を発信しファンを増やせる
SNSは、求人票の限られた情報だけでは伝えきれない、企業のリアルな姿を発信するのに最適なツールです。オフィス環境、社員同士の交流、社内イベントの様子などを写真や動画で共有することで、候補者は社風や働く人々の雰囲気を直感的に理解できます。 このような継続的な情報発信は、単に応募者を集めるだけでなく、企業の価値観に共感する「ファン」を育てる採用広報活動となります。
実際に、株式会社リソースクリエイションでも、SNSを活用して「働く人の雰囲気」や「社内イベントのリアル」を継続的に発信した結果、
新卒エントリー数が 約300名 から、
2026年卒では 4,000名 を超えるまでに増加しました。
単に母集団を増やすだけでなく、「この会社で働きたい」と思ってくれるファン層が厚くなったことで、自社にマッチした人材からの応募が自然と集まる状態に近づいています。
結果として、自社にマッチした人材からの応募が増え、
エンゲージメントの高い採用を実現できる可能性が高まります。
▼もっと詳しく知りたい方▼
https://rc-group.co.jp/contact/
採用コストを大幅に削減できる可能性がある
多くのSNSは無料でアカウントを開設・運用できるため、求人広告媒体への掲載費用や人材紹介会社へ支払う成功報酬といった、従来の採用手法にかかるコストを大幅に削減できる可能性があります。 特に、採用にかけられる費用が限られている中小企業にとって、低コストで始められる点は大きな魅力です。 もちろん、SNS広告の出稿や分析ツールの導入、運用代行を依頼する場合は別途費用が発生しますが、自社で運用ノウハウを蓄積すれば、長期的にはコストパフォーマンスの高い採用チャネルを確立できます。
多くのSNSは無料でアカウントを開設・運用できるため、求人広告媒体への掲載費用や人材紹介会社へ支払う成功報酬といった、従来の採用手法にかかるコストを大幅に削減できる可能性があります。 特に、採用にかけられる費用が限られている中小企業にとって、低コストで始められる点は大きな魅力です。 もちろん、SNS広告の出稿や分析ツールの導入、運用代行を依頼する場合は別途費用が発生しますが、自社で運用ノウハウを蓄積すれば、長期的にはコストパフォーマンスの高い採用チャネルを確立できます。
候補者との相互理解が深まりミスマッチを防げる
SNS採用では、コメントやダイレクトメッセージを通じて、選考前から候補者と直接的なコミュニケーションを取ることが可能です。 企業は飾らない日常を発信し、候補者はそれに対して気軽に質問できるため、双方向のやり取りの中から相互理解が深まります。 候補者は企業のリアルな情報を得ることで入社後のイメージを具体化でき、企業側も候補者の投稿から人柄や価値観を垣間見ることができます。 こうしたプロセスを経ることで、採用活動における「思っていた社風と違った」というミスマッチを減らし、入社後の定着率向上に貢献します。始める前に知っておきたいSNS採用の3つの注意点
SNS採用は多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。 計画なく始めてしまうと、期待した効果が得られないばかりか、かえって企業のイメージを損なうリスクも伴います。 ここでは、SNS採用を始める前に必ず理解しておくべき3つの注意点として、運用工数、炎上リスク、そして求められる専門知識について解説します。
成果が出るまでには継続的な運用が必要になる
SNS採用は、アカウントを開設してすぐに結果が出るものではありません。 フォロワーを増やし、候補者との信頼関係を構築するには、中長期的な視点での地道で継続的な運用が不可欠です。 コンテンツの企画作成、定期的な投稿、コメントやメッセージへの返信といった日々のタスクを続けることで、徐々に効果が現れます。 そのため、短期的な成果を求めるのではなく、企業の資産としてアカウントを育てていくという認識を持つことが重要です。 担当者のリソースを確保し、計画的に運用を続ける体制を整える必要があります。投稿内容によっては炎上し企業イメージを損なう恐れがある
SNSは情報が瞬時に広範囲に拡散される特性を持つため、不適切な投稿は「炎上」を引き起こし、企業の評判やブランドイメージを著しく損なう危険性があります。 差別的な表現、政治や宗教に関する偏った意見、社会通念上問題のある内容などはもちろん、軽い冗談のつもりが意図せず誰かを傷つけてしまうケースも少なくありません。 炎上を未然に防ぐためには、投稿前に複数人で内容をチェックする体制を整えたり、時事的なニュースを確認して社会の空気を読んだりするなど、慎重な運用が求められます。アカウントの企画・運用に専門的な知識と工数がかかる
効果的なSNS採用を行うには、各媒体の特性を理解した上でのコンテンツ企画、ターゲットに響く情報発信、そして効果測定と分析・改善といった専門的な知識やスキルが要求されます。 また、コンテンツの作成から投稿、コメント対応、分析レポート作成まで、日々の運用には想像以上の工数がかかります。 社内にSNS運用のノウハウや十分なリソースがない場合、担当者の負担が過大になったり、投稿の質が低下したりする恐れがあります。 このような場合、外部のコンサルティングや運用代行サービスを利用することも有効な選択肢となります。【目的別】主要5SNSの特徴と採用での活かし方
SNS採用を成功させる鍵は、自社の採用目的やターゲット層に合わせて、最適なプラットフォームを選択し活用することです。 各SNSにはそれぞれ異なる特徴やユーザー層が存在するため、その特性を理解せずに運用を始めても効果は限定的です。 ここでは、主要な5つのSNSアカウントを取り上げ、それぞれの特徴と、採用活動においてどのように活かしていけばよいかを目的別に解説します。
X(旧Twitter):リアルタイムの情報発信と拡散力で認知を拡大
Xは、リアルタイム性の高さとリポストによる情報の拡散力が最大の特徴です。 140文字(日本語)という手軽さから、企業の最新ニュース、イベントの告知、説明会の案内などをスピーディーに発信するのに適しています。 ハッシュタグを活用すれば、特定の業界や職種に興味を持つユーザーに効率良くアプローチできます。 また、カジュアルなコミュニケーションが生まれやすく、候補者とフランクな関係を築きやすい点も魅力です。 ターゲティング精度の高いSNS広告も比較的低予算から始められるため、企業の認知度拡大に効果的です。Instagram:写真や動画で社風や働く人の魅力を伝える
Instagram(インスタ)は、写真や動画といったビジュアルコンテンツが中心のプラットフォームです。 洗練されたオフィス、楽しそうな社内イベント、活き活きと働く社員の姿などを投稿することで、企業のブランドイメージや社風を直感的に伝えることができます。 特に、ショート動画機能の「リール」は若年層への訴求力が高く、企業の魅力をテンポ良く紹介するのに最適です。 また、24時間で消える「ストーリーズ」機能を使えば、Q&Aコーナーやアンケートなどを通じて、候補者と気軽に双方向のコミュニケーションを図ることが可能です。Facebook:実名登録制で信頼性の高い情報発信が可能
Facebookは実名での登録が基本であり、ユーザー層の年齢も比較的高めであるため、ビジネス関連の信頼性の高い情報発信に適しています。 企業の公式なプレスリリース、社員インタビュー記事、業界に関する専門的な考察などを投稿することで、企業の信頼性や専門性をアピールできます。 また、ユーザーのプロフィールに経歴やスキルが記載されていることも多く、特定の経験を持つ人材を探す「ダイレクトリクルーティング」にも活用可能です。 特にBtoB企業や、ミドル層・ハイクラス層の採用を目指す大手企業にとって有効な媒体といえます。TikTok:ショート動画でZ世代に企業の魅力を直感的に訴求
TikTokは、10代〜20代のZ世代に絶大な人気を誇るショート動画プラットフォームです。 企業の魅力を短時間で、かつエンターテインメント性を交えて伝えるのに非常に効果的です。 トレンドの音楽やエフェクトを活用したユニークな動画は、他のSNSでは見られないほどの爆発的な拡散を生む可能性があります。 オフィス紹介や社員の1日、仕事内容の解説などを面白く、分かりやすく見せることで、企業の認知度向上や親近感の醸成に繋がります。 TikTokでは、作り込まれた広告よりも、社員の素顔が見えるようなリアルなコンテンツが好まれる傾向にあります。YouTube:長尺動画で企業文化や社員インタビューを深く伝える
YouTubeは、より時間をかけた長尺の動画を通じて、企業の情報を深く、多角的に伝えられるプラットフォームです。 事業内容の詳細な解説、複数の社員による座談会、プロジェクトの裏側を紹介するドキュメンタリーなど、テキストや写真だけでは伝わらない情報を網羅的に提供できます。 特に、社員インタビュー動画は、仕事のやりがいやキャリアパス、企業の文化などを候補者に具体的にイメージさせるのに有効です。 他のSNSで企業に興味を持った候補者をYouTubeチャンネルへ誘導し、さらなる理解促進と志望度向上を図るという使い方が効果的です。7つのステップで進める!SNS採用の始め方
SNS採用を成功に導くためには、思いつきで始めるのではなく、戦略的なアプローチが欠かせません。 目的の明確化から始まり、ターゲット設定、媒体選定、コンテンツ企画、そして効果測定と改善まで、体系立てて進めることが重要です。 ここでは、これからSNS採用に取り組む企業が迷わないよう、具体的な方法を7つのステップに分解して解説します。 この流れに沿って、自社に最適なSNS採用戦略を構築していきましょう。
▼もっと詳しく知りたい方▼
https://rc-group.co.jp/contact/
STEP1:SNS採用で達成したい目的を明確にする
最初に、「何のためにSNS採用を行うのか」という目的を具体的に設定します。 例えば、「20代の若手エンジニアの母集団を前年比20%増やす」「新卒採用における内定承諾率を5%向上させる」「地方在住者からの募集を増やす」といったように、定量的・定性的なゴールを明確にします。 この目的が、後のステップである媒体選定やコンテンツ企画、KPI設定の軸となります。 目的が曖昧なままでは施策に一貫性がなくなり、効果的な運用は望めません。STEP2:採用したい人物像(ペルソナ)を具体的に描く
次に、自社が採用したい理想の人物像である「ペルソナ」を詳細に設定します。 年齢、性別、居住地、学歴、スキルセットといった基本情報に加え、価値観、ライフスタイル、趣味、情報収集に利用するSNSなど、その人物のライフスタイルが目に浮かぶまで具体的に描き出します。 ペルソナを明確にすることで、どのような情報が彼らに響くのか、どのような言葉遣いで語りかけるべきかがクリアになります。 この作業は、求人情報の発信だけでなく、全てのコンテンツ制作の指針となります。STEP3:目的とペルソナに最適なSNS媒体を選ぶ
設定した目的とペルソナに基づき、最も効果的なSNS媒体を選定します。 例えば、Z世代の新卒採用が目的ならばInstagramやTikTokが、30代の即戦力エンジニアがペルソナならばXやFacebookが候補となるでしょう。 各SNSのユーザー層や文化、得意な表現方法を理解し、自社のターゲットが最もアクティブに利用しているプラットフォームを選ぶことが重要です。 マイナビのような従来の求人媒体と併用する場合は、それぞれのチャネルの役割を明確にし、連携させることで相乗効果を狙います。STEP4:目標達成度を測るためのKPIを設定する
SNS採用の施策が目的達成にどれだけ貢献しているかを客観的に測るため、具体的な数値目標であるKPI(重要業績評価指標)を設定します。 KPIには、アカウントの成長度を示す「フォロワー数」や「インプレッション数」、投稿への関心度を示す「エンゲージメント率(いいね、コメント、保存数)」、採用への貢献度を示す「プロフィールURLのクリック数」「採用サイトへの遷移数」「応募数」などがあります。 マーケティングの観点から複数のKPIを設定し、定期的に進捗を追うことで、施策の有効性を判断し改善に繋げられます。STEP5:アカウントの世界観と発信するコンテンツ内容を決める
ペルソナに「この会社、面白そう」「働いてみたい」と思ってもらうため、アカウント全体のコンセプトやトーン&マナーを決定します。 例えば、「若手社員が中心となって発信する、活気と親しみやすさが魅力のアカウント」や「業界のプロフェッショナルとして、専門的で質の高い情報を発信するアカウント」など、一貫した世界観を構築します。 その上で、社員インタビュー、オフィスツアー、1日の仕事紹介(Vlog)、業界知識の解説といった具体的なコンテンツを企画します。 単なる採用情報だけでなく、候補者の役に立つ情報や共感を呼ぶ内容をバランス良く発信することが重要です。STEP6:無理なく継続できる運用体制と投稿計画を立てる
SNS採用は継続が不可欠なため、担当者一人に過度な負担がかからない、持続可能な運用体制を構築します。 人事部だけでなく、広報や現場社員など、複数のメンバーを巻き込み、役割を分担するのが理想的です。 誰がコンテンツを企画し、誰が作成・投稿し、誰がコメント対応や分析を行うのかを明確にします。 また、行き当たりばったりの運用を避けるため、「毎週月曜は社員紹介、水曜はオフィス風景、金曜は週末の雑談」といったように、大まかな投稿スケジュールを立てておくと、安定した情報発信が可能になり、コンテンツの質も担保しやすくなります。STEP7:定期的に効果を分析し改善を繰り返す
SNS運用は「投稿して終わり」ではありません。 定期的にパフォーマンスを振り返り、改善を重ねていくことが成果を出すための鍵です。 各SNSが提供する分析ツール(インサイト)を活用し、設定したKPIの数値をチェックします。 どの投稿のエンゲージメントが高かったか、フォロワーはどのような層が多いか、どの時間帯の反応が良いかなどを分析し、その結果から得られた仮説を次のコンテンツ企画に活かします。 このPDCAサイクルを回し続けることで、アカウントは着実に成長していきます。 社内での分析が難しい場合は、関連セミナーへの参加も有効です。▼もっと詳しく知りたい方▼
https://rc-group.co.jp/contact/
SNS採用の成果を最大化させる3つの成功のポイント
SNS採用の基本的なステップを理解した上で、さらにその成果を最大化するためには、いくつかの重要な心構えと工夫が必要です。 単に情報を発信するだけでなく、企業全体を巻き込み、候補者との関係性を深めていく視点が求められます。 ここでは、SNS採用を成功へと導くために、特に意識すべき3つのポイントを解説します。
会社全体で協力し一貫性のある情報を発信する
SNS採用は、採用担当者だけのミッションではありません。 会社全体を巻き込み、様々な部署の社員に協力してもらうことで、発信される情報に深みとリアリティが生まれます。 例えば、現場のエンジニアに技術的な内容を発信してもらったり、営業担当に顧客とのエピソードを語ってもらったりすることで、多角的な視点から会社の魅力を伝えられます。 経営層から現場社員までがSNS採用の重要性を理解し、一貫性のあるメッセージを発信することで、企業のブランドイメージはより強固になり、候補者からの信頼も得やすくなります。採用期間だけでなく日常的にアカウントを運用する
SNS採用のよくある失敗例として、採用活動を行う期間だけ投稿を活発にし、それ以外の時期は放置してしまうケースが挙げられます。 候補者は、企業の「今」を知りたいと考えています。 そのため、募集の有無にかかわらず、日常的にアカウントを運用し、会社の普段の様子を発信し続けることが重要です。 継続的なSNS運用は、フォロワーとのエンゲージメントを維持し、転職を今すぐ考えていない潜在層に対しても自社の魅力を刷り込む効果があります。 こうした日々の積み重ねが、いざ採用が必要となった時に大きな力となります。候補者との積極的なコミュニケーションを心がける
SNSの最大の特性は、双方向性にあります。 企業からの一方的な情報発信に終始するのではなく、候補者とのコミュニケーションを積極的に楽しむ姿勢が重要です。 投稿に寄せられたコメントや質問には、可能な限り丁寧に、そして迅速に返信しましょう。 時には、企業側から候補者の投稿に「いいね」をしたり、コメントをしたりすることも有効です。 このような対話を通じて、候補者は企業に親近感を抱き、心理的な距離が縮まります。 一人ひとりの候補者と真摯に向き合う姿勢が、最終的に応募や入社の決断を後押しします。【SNS媒体別】参考にしたい企業のSNS採用成功事例
SNS採用を成功させるためには、具体的な企業の成功事例から学ぶことが非常に効果的です。 各SNSプラットフォームの特性を巧みに活かし、独自の工夫で採用ブランディングを確立している企業は数多く存在します。
導入事例 :https://sns-agency.rc-group.co.jp/case/
導入事例 :https://sns-agency.rc-group.co.jp/case/
ご不明点はお気軽にお問い合わせください
この度はリソースクリエイションにご興味を持ってくださいまして、誠にありがとうございます。
ご不明点・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。
殿堂入り記事
オススメ記事
オススメ記事
殿堂入り記事