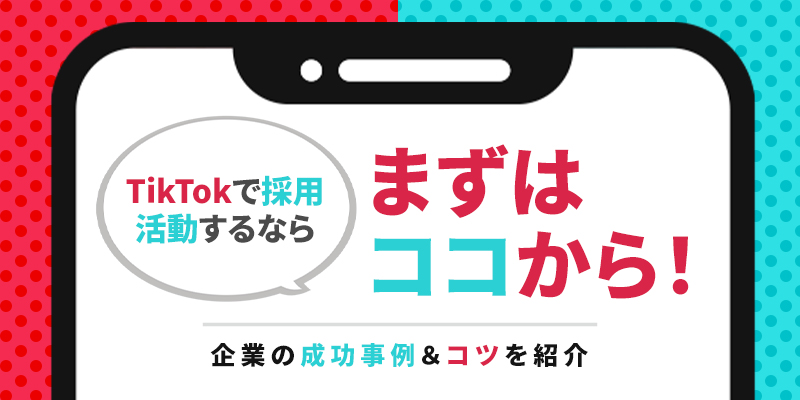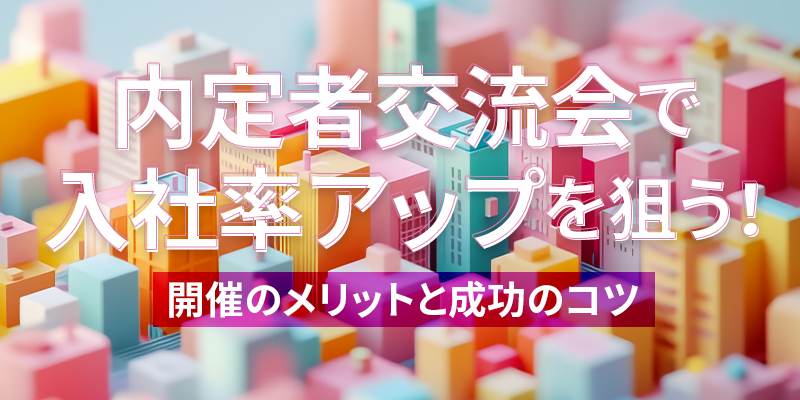採用支援
若手の8割が辞令をきっかけに退職!?転勤・異動の伝え方と退職防止策
更新日:2025.09.10
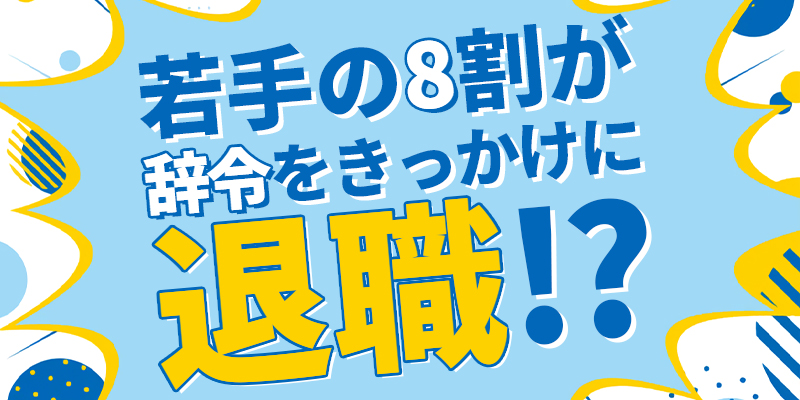
近年、転勤を命じられた若手社員の約8割が、それを退職のきっかけとして捉えているという調査結果があります。特に20代・30代の若年層は、転勤の辞令によって退職を考える傾向が強く、実際に3割が転勤を理由に退職した経験を持つことも明らかになっています。そのため、企業は転勤の伝え方を工夫し、適切な退職防止策を講じることが、優秀な若手人材の流出を防ぐ上で非常に重要です。
本記事では、若手が転勤によって退職を考える背景にある意識と、企業が取るべき具体的な対策について解説します。
転勤が若手社員の退職トリガーに
企業の人材配置戦略として行われる転勤が、若手社員を中心に離職を促す大きな要因となっています。転勤による退職は、単なる欠員の発生に留まらず、企業の成長を担う優秀な人材の流出につながり、組織にとって深刻な損失です。
現代の若手社員は、仕事だけでなくプライベートの充実も重視する傾向が強く、転勤は彼らのライフプランやキャリアプランに大きな影響を与えるため、企業は転勤のあり方を見直す必要があります。ここでは、データに基づき、多くの社員が転勤を理由に退職を検討する実態を明らかにします。
現代の若手社員は、仕事だけでなくプライベートの充実も重視する傾向が強く、転勤は彼らのライフプランやキャリアプランに大きな影響を与えるため、企業は転勤のあり方を見直す必要があります。ここでは、データに基づき、多くの社員が転勤を理由に退職を検討する実態を明らかにします。
約7割が転勤の辞令を「退職のきっかけ」と認識
ミイダス株式会社の調査によると、転勤経験者のうち約7割が「転勤が退職のきっかけになった」と回答しており、これは企業にとって無視できない数字です。企業が成長を期待して発令する転勤命令が、社員の意向とは裏腹に、離職の直接的な引き金となっている現実が浮き彫りになっています。企業としては育成のつもりでも、当事者にとってはキャリアや生活を中断されるネガティブなイベントと捉えられ、結果的に退職に至るケースが少なくありません。特に20代・30代の若手社員で離職の意向が強い傾向
転勤による退職意向は、特に20代・30代の若手社員において顕著です。また、入社後の年数で見ると、入社後2年未満の社員が退職を検討する割合が非常に高いという結果も出ています。キャリア形成の初期段階にある若手にとって、早期の転勤は自身のキャリアプランやライフプランを大きく揺るがす出来事と受け止められやすく、離職という選択につながりやすい傾向が見られます。
なぜ従業員は転勤で辞めてしまうのか?3つの主な理由
従業員が転勤を理由に退職を選ぶ背景には、複合的な理由が存在します。それは単に新しい環境への適応が億劫だというだけでなく、生活やキャリアに深刻な影響を及ぼすストレスが伴うためです。
ここでは、従業員が転勤を拒む主な理由を「家庭環境」「生活基盤」「キャリアプラン」の3つの観点から具体的に解説します。
また、子育て中の家庭では、苦労して入園させた保育園を辞め、転居先で新たに見つけなければならないという大きな課題に直面します。さらに、親の介護といった問題も無視できません。こうした家族の事情は社員一人の努力では解決が難しく、転勤を断念する大きな理由となります。
このように、仕事以外の部分で生活の質が低下するリスクは転勤を受け入れがたくする大きな要因です。
例えば、特定の分野でスキルを深めたいと考えている社員にとって、会社のジェネラリスト育成方針に基づく異動は、望まないキャリアパスと映るかもしれません。会社側が描く成長の道筋と、本人が思い描くキャリアプランとの間に大きな違いがあると、社員は会社に自分の将来を託せないと感じます。特に、事前の相談なく異動が決定されると、会社への不信感が募り、退職という選択肢が現実味を帯びてきます。
ここでは、従業員が転勤を拒む主な理由を「家庭環境」「生活基盤」「キャリアプラン」の3つの観点から具体的に解説します。
理由1:共働きや育児など、家庭環境の変化に対応できない
共働き世帯が一般化した現代において、転勤は個人の問題ではなく家族全体の問題となります。パートナーである妻(あるいは夫)がキャリアを中断せざるを得なくなったり、転職を余儀なくされたりするケースは少なくありません。また、子育て中の家庭では、苦労して入園させた保育園を辞め、転居先で新たに見つけなければならないという大きな課題に直面します。さらに、親の介護といった問題も無視できません。こうした家族の事情は社員一人の努力では解決が難しく、転勤を断念する大きな理由となります。
理由2:現在の生活基盤を失うことへの強い抵抗感
持ち家や子どもの学校、友人関係や地域のコミュニティなど、長年かけて築いてきた生活基盤を失うことに対して、多くの人が強い抵抗感を抱きます。特に、慣れ親しんだ土地を離れる転居を伴う転勤は、プライベートの安定を大きく損なう可能性があります。また、都市部から地方への異動では生活の利便性が、逆に地方から都市部への異動では住居費や通勤時間の増加が懸念されます。このように、仕事以外の部分で生活の質が低下するリスクは転勤を受け入れがたくする大きな要因です。
理由3:自身の思い描くキャリアプランとのミスマッチ
社員が自身の専門性や将来像について明確なキャリアプランを持っている場合、会社の意図する異動と本人の希望にミスマッチが生じることがあります。例えば、特定の分野でスキルを深めたいと考えている社員にとって、会社のジェネラリスト育成方針に基づく異動は、望まないキャリアパスと映るかもしれません。会社側が描く成長の道筋と、本人が思い描くキャリアプランとの間に大きな違いがあると、社員は会社に自分の将来を託せないと感じます。特に、事前の相談なく異動が決定されると、会社への不信感が募り、退職という選択肢が現実味を帯びてきます。
納得感を引き出す!退職を防ぐ転勤の伝え方4ステップ
転勤による退職を防ぐ鍵は、一方的な転勤命令ではなく、社員の納得感を引き出すコミュニケーションにあります。会社側の論理だけを押し付ける伝え方では、社員の不満や反発を招き、最悪の場合クレームに発展しかねません。
ここでは、社員が前向きに転勤を受け入れ、エンゲージメントを維持するための伝え方を4つのステップで具体的に解説します。
これにより、社員は自分が一人の人間として尊重されていると感じ、抱えている懸念や事情を正直に話しやすくなります。準備期間の短い一方的な通告は、社員に「自分は会社の駒でしかない」という不信感を抱かせます。
単に「欠員が出たから」「育成の一環として」といった曖昧な理由では、社員の心には響きません。
「君の持つ〇〇のスキルが、△△支店の新しいプロジェクトで不可欠なんだ」「リーダーシップを発揮して、現地の若手をまとめてほしい」といったように、その社員の強みや実績に触れ、異動先で期待する具体的な役割と異動の目的を明確に語ることが重要です。
会社が自分を正当に評価し、期待を寄せていることが伝われば、社員は異動をキャリアアップの機会として前向きに捉えることができます。
「以前、将来はマネジメントに挑戦したいと話してくれたが、今回の異動先ではそのために必要なチーム運営の経験が積める」といったように、転勤が本人の目標達成にどう貢献するのかを具体的に説明します。会社の都合だけでなく、社員自身の成長という視点を加えることで、転勤は「やらされるもの」から「自身の未来への投資」へと意味合いが変わります。
キャリアへの不安、経済的な負担、家族の同意など、社員が抱えるであろう様々な問題に真摯に耳を傾け、解決策を一緒に模索する姿勢を見せることで、社員は会社から大切にされていると感じ、前向きな検討をしやすくなります。
ここでは、社員が前向きに転勤を受け入れ、エンゲージメントを維持するための伝え方を4つのステップで具体的に解説します。
ステップ1:内示は1ヶ月以上前に、個別面談で打診する
転勤を伝える際は、タイミングと形式が極めて重要です。法的な期限はさておき、社員が引越しや家族への説明、業務の引き継ぎなどを落ち着いて行うためには、少なくとも1ヶ月以上、可能であれば2〜3ヶ月前には内示を行うのが望ましいでしょう。また、その伝え方も、一斉メールなどで事務的に行うのではなく、必ず直属の上司が個別面談の時間を設定し、直接対話する形で打診することが不可欠です。これにより、社員は自分が一人の人間として尊重されていると感じ、抱えている懸念や事情を正直に話しやすくなります。準備期間の短い一方的な通告は、社員に「自分は会社の駒でしかない」という不信感を抱かせます。
ステップ2:会社が本人に期待する役割と異動の目的を具体的に語る
転勤の打診において、「なぜあなたなのか」を具体的に伝えることは、社員の納得感を得る上で欠かせません。単に「欠員が出たから」「育成の一環として」といった曖昧な理由では、社員の心には響きません。
「君の持つ〇〇のスキルが、△△支店の新しいプロジェクトで不可欠なんだ」「リーダーシップを発揮して、現地の若手をまとめてほしい」といったように、その社員の強みや実績に触れ、異動先で期待する具体的な役割と異動の目的を明確に語ることが重要です。
会社が自分を正当に評価し、期待を寄せていることが伝われば、社員は異動をキャリアアップの機会として前向きに捉えることができます。
ステップ3:本人のキャリアプランと転勤の関連性を示す
会社からの期待を伝えるだけでなく、今回の転勤が社員本人のキャリアプランにとってどのような意味を持つのかを示すことが、納得感を醸成する上で非常に効果的です。そのためには、日頃から1on1などを通じて本人のキャリア志向を把握しておく必要があります。「以前、将来はマネジメントに挑戦したいと話してくれたが、今回の異動先ではそのために必要なチーム運営の経験が積める」といったように、転勤が本人の目標達成にどう貢献するのかを具体的に説明します。会社の都合だけでなく、社員自身の成長という視点を加えることで、転勤は「やらされるもの」から「自身の未来への投資」へと意味合いが変わります。
ステップ4:一方的な命令ではなく、本人の意向や懸念をヒアリングする
会社側の期待や目的を伝えた後は、必ず本人の意向や懸念を丁寧にヒアリングする時間を十分に確保します。これは、決定事項を伝える場ではなく、あくまで「打診」と「相談」の場であるという姿勢を示すことが重要です。「この話を聞いてどう思うか」「何か心配なことや、家庭の事情で難しいことはないか」と問いかけ、社員が本音を話しやすい雰囲気を作りましょう。キャリアへの不安、経済的な負担、家族の同意など、社員が抱えるであろう様々な問題に真摯に耳を傾け、解決策を一緒に模索する姿勢を見せることで、社員は会社から大切にされていると感じ、前向きな検討をしやすくなります。

社員の不安を解消する!転勤による退職を防止する4つの制度
転勤に伴う退職を防ぐには、丁寧なコミュニケーションだけでなく、社員の不安を根本から解消するための制度的なサポートが不可欠です。場当たり的な対応ではなく、全ての社員に公平に適用される明確なルールを整備することで、安心して転勤を受け入れられる環境が整います。
ここでは、社員の負担を軽減し、転勤へのハードルを下げるための具体的な4つの制度について解説します。
具体的には、引越し費用や新居の契約にかかる初期費用を会社が全額負担することや、転勤先の家賃を補助する制度(借り上げ社宅など)が有効です。特に、家族と離れて生活する単身赴任者には、二重生活の負担を軽減するための単身赴任手当や、定期的に帰省するための交通費補助が不可欠です。これらの金銭的なサポートは、社員が経済的な心配をせずに新しい仕事に集中するためのセーフティネットとして機能します。
また、一定期間勤務した後には元の部署に戻れる「帰任権」を保証する制度や、自らキャリアを選択できる社内公募制度などを設けることで、転勤がキャリアの袋小路にならないという安心感を与えることができます。
この制度は、社員が自らの意思で転勤のない働き方を選択できるようにするもので、転勤を理由とした離職を防ぐ効果が期待できます。もちろん、全国転勤可能な社員との処遇のバランスを考慮した制度設計は必要ですが、多様な働き方を許容する企業文化を醸成することは、優秀な人材の確保と定着に大きく貢献します。
また、赴任先の医療機関や商業施設、地域のコミュニティに関する情報を提供するなど、家族が新しい生活にスムーズに馴染めるようなサポートも有効です。家族の不安が解消されることは、社員本人の心理的な安定に直結します。
ここでは、社員の負担を軽減し、転勤へのハードルを下げるための具体的な4つの制度について解説します。
制度1:家賃補助や単身赴任手当で経済的負担を軽減する
転勤によって発生する経済的な負担は、社員にとって大きな懸念事項です。この不安を解消するため、手厚い支援制度の整備が求められます。具体的には、引越し費用や新居の契約にかかる初期費用を会社が全額負担することや、転勤先の家賃を補助する制度(借り上げ社宅など)が有効です。特に、家族と離れて生活する単身赴任者には、二重生活の負担を軽減するための単身赴任手当や、定期的に帰省するための交通費補助が不可欠です。これらの金銭的なサポートは、社員が経済的な心配をせずに新しい仕事に集中するためのセーフティネットとして機能します。
制度2:転勤後のキャリアパスや選択肢を明確に提示する
転勤に対するキャリア上の不安を払拭するためには、異動後のキャリアパスを具体的に示すことが重要です。「いつまで転勤先にいるのか分からない」という状態は、社員のモチベーションを著しく低下させます。そのため、「原則として3年間」といったように転勤期間の目安を明示したり、「このミッションを達成すれば、本社の中核部署へ異動する道が開ける」といったように、次のステップを具体的に提示したりすることが有効です。また、一定期間勤務した後には元の部署に戻れる「帰任権」を保証する制度や、自らキャリアを選択できる社内公募制度などを設けることで、転勤がキャリアの袋小路にならないという安心感を与えることができます。
制度3:「勤務地限定制度」を導入し、多様な働き方を認める
全ての社員が転勤可能な状況にあるわけではありません。育児や介護といった家庭の事情、あるいは個人のライフプランにより、特定の地域から離れられない社員もいます。こうした多様な働き方のニーズに応えるため、「勤務地限定制度」の導入は有効な選択肢となります。この制度は、社員が自らの意思で転勤のない働き方を選択できるようにするもので、転勤を理由とした離職を防ぐ効果が期待できます。もちろん、全国転勤可能な社員との処遇のバランスを考慮した制度設計は必要ですが、多様な働き方を許容する企業文化を醸成することは、優秀な人材の確保と定着に大きく貢献します。
制度4:転勤者の家族もサポートする福利厚生を整える
転勤は社員本人だけでなく、その家族にとっても大きな生活の変化を伴います。そのため、家族を含めたサポート体制を構築することが、社員のエンゲージメントを維持する上で重要です。例えば、転勤に伴って配偶者が退職せざるを得ない場合に、再就職を支援するサービスを提供したり、転園・転校が必要な子どものために地域の学校情報を提供したりといった支援が考えられます。また、赴任先の医療機関や商業施設、地域のコミュニティに関する情報を提供するなど、家族が新しい生活にスムーズに馴染めるようなサポートも有効です。家族の不安が解消されることは、社員本人の心理的な安定に直結します。
もし従業員に転勤を拒否されたら?企業がとるべき対応手順
丁寧な打診や制度的な支援を用意しても、やむを得ない事情で従業員が転勤を断るケースは起こり得ます。このような状況で、企業は感情的になったり問題を放置したりせず、冷静かつ適切な手順で対応することが求められます。転勤命令が無効となるケースも存在するため、法的な観点も踏まえながら、従業員との対話を基本とした対応が必要です。
一方的に業務命令違反だと断じるのではなく、まずは相手の立場や状況を理解しようと努める姿勢が重要です。このプロセスを丁寧に行うことで、従業員との信頼関係を損なうことなく、問題解決に向けた建設的な対話の土台を築くことができます。
具体的には、転勤の業務上の必要性が乏しい場合、人選に合理的な理由がない場合、転勤によって従業員が通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を被る場合などは、権利濫用と判断され命令が無効になる可能性があります。正当性を欠いたまま懲戒処分や退職勧奨に踏み切ると、法的な紛争に発展するリスクが高まります。
あらゆる可能性を検討してもなお合意に至らず、退職が避けられない場合は、懲戒解雇ではなく合意退職を目指すべきです。その際、会社都合として処理し、従業員が失業保険の受給などで不利益を被らないよう配慮することが、無用なトラブルを避ける上で賢明な対応となります。
まずは拒否理由を丁寧にヒアリングし、背景を理解する
従業員から転勤を拒否された場合、まず行うべきは、その理由を決めつけることなく丁寧にヒアリングすることです。「なぜ転勤できないのか」を、具体的な背景事情とともに詳しく聞きましょう。拒否の裏には、育児や親の介護、本人の健康問題など、軽視できない深刻な理由が隠されている場合があります。一方的に業務命令違反だと断じるのではなく、まずは相手の立場や状況を理解しようと努める姿勢が重要です。このプロセスを丁寧に行うことで、従業員との信頼関係を損なうことなく、問題解決に向けた建設的な対話の土台を築くことができます。
就業規則を確認し、転勤命令の正当性をチェックする
従業員からヒアリングを行うと同時に、自社の就業規則に転勤を命じることができる旨の規定が明記されているかを確認します。その上で、今回の転勤命令が法的に正当なものか、つまり「権利濫用」に当たらないかを慎重に検討する必要があります。具体的には、転勤の業務上の必要性が乏しい場合、人選に合理的な理由がない場合、転勤によって従業員が通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を被る場合などは、権利濫用と判断され命令が無効になる可能性があります。正当性を欠いたまま懲戒処分や退職勧奨に踏み切ると、法的な紛争に発展するリスクが高まります。
代替案の提示や勤務地限定社員への区分変更を検討する
ヒアリングと法的検討の結果、転勤の強行が困難あるいは不適切だと判断した場合は、代替案を模索します。例えば、転居を伴わない近隣の事業所への異動を再提案したり、現在の部署で別の役割を担ってもらったりといった選択肢が考えられます。もし勤務地限定制度があるならば、社員区分の変更を打診することも有効な手段です。あらゆる可能性を検討してもなお合意に至らず、退職が避けられない場合は、懲戒解雇ではなく合意退職を目指すべきです。その際、会社都合として処理し、従業員が失業保険の受給などで不利益を被らないよう配慮することが、無用なトラブルを避ける上で賢明な対応となります。
まとめ
転勤をきっかけとした若手社員の退職は、企業の伝え方や制度設計に起因するケースが少なくありません。働き手や家族の価値観が多様化する現代において、過去の慣習に則った一方的な転勤命令は、優秀な人材の流出リスクを増大させます。この問題に対処するためには、社員一人ひとりのキャリアプランや家庭の事情を考慮した丁寧なコミュニケーションが不可欠です。
また、転勤に伴う経済的負担やキャリアの不透明性を解消するための制度を整備し、働き方の選択肢を増やすことも有効です。万が一、転勤を拒否された場合でも、まずは理由を傾聴し、法的な正当性を確認した上で、代替案を含めた柔軟な対応を検討することが求められます。
また、転勤に伴う経済的負担やキャリアの不透明性を解消するための制度を整備し、働き方の選択肢を増やすことも有効です。万が一、転勤を拒否された場合でも、まずは理由を傾聴し、法的な正当性を確認した上で、代替案を含めた柔軟な対応を検討することが求められます。
ご不明点はお気軽にお問い合わせください
この度はリソースクリエイションにご興味を持ってくださいまして、誠にありがとうございます。
ご不明点・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。
殿堂入り記事
オススメ記事
オススメ記事
殿堂入り記事