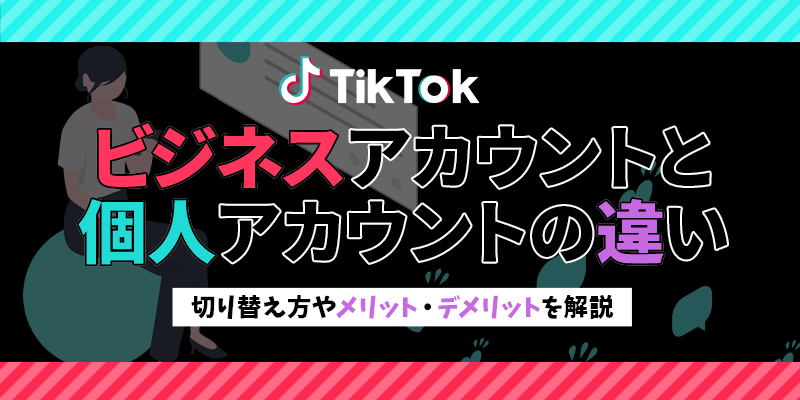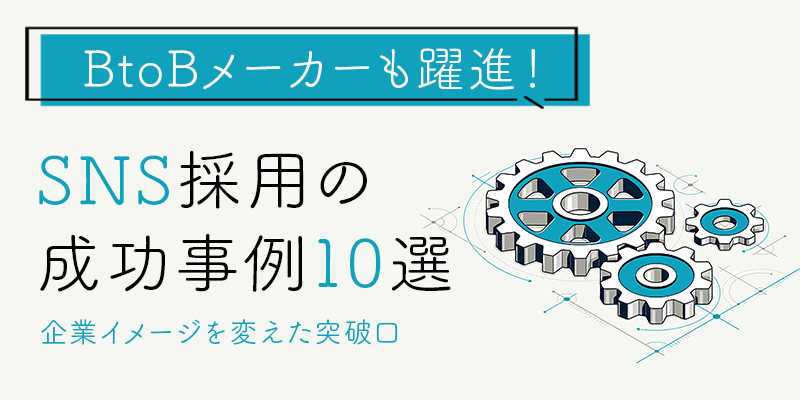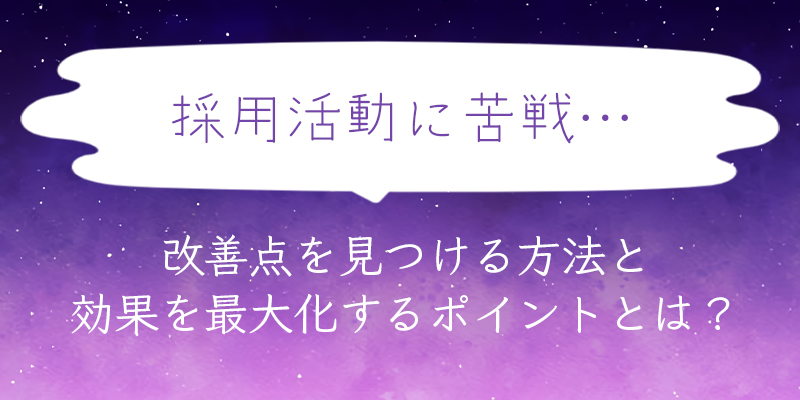採用支援
求人倍率が高い/低いとどうなる?職種別の有効求人倍率を解説
更新日:2025.08.27

転職を考えている方や雇用市場の動向に関心がある方にとって、有効求人倍率は非常に重要な指標です。この数値は、求職者1人あたりに何件の求人があるかを示し、職業選択や転職活動の戦略を立てる上で役立ちます。
本記事では、有効求人倍率の意味や計算方法、その高低が転職活動に与える影響、具体的な職種別の求人倍率、そしてデータを見る上での注意点について詳しく解説します。
そもそも有効求人倍率とは?求職者1人あたりの求人件数
有効求人倍率は、求職者1人に対して何件の求人があるかを示す指標です。厚生労働省が全国のハローワークに登録された求人数と求職者数をもとに毎月公表しており、雇用市場の需給バランスを示す重要な経済指標とされています。この数値は景気動向とほぼ一致して動く「一致指数」としても用いられており、有効求人倍率が1を上回れば求人数が求職者数を上回り、1を下回れば求職者数が求人数を上回る状況を示しています。
この倍率を見ることで、現在の求職状況が企業優位の「買い手市場」なのか、求職者優位の「売り手市場」なのかを判断することができます。例えば、求人倍率が2倍であれば、1人の求職者に対して2件の有効な求人があることを意味し、転職希望者にとっては選択肢が多く、希望に合った職場を見つけやすい状況と言えるでしょう。
例えば、ある月に有効求人数が200件、有効求職者数が100人だった場合、有効求人倍率は200件 ÷ 100人 = 2.0倍となります。これは、1人の求職者に対して2件の求人があることを示しており、求職者にとって選択肢が多い「売り手市場」であると判断できます。このように、有効求人倍率は、単に数字としてだけでなく、それが意味する雇用市場の需給バランスを理解することで、転職活動や採用戦略をより的確に立てるための重要な手がかりとなります。
企業側は優秀な人材を確保するために、給与や福利厚生などの待遇を改善したり、柔軟な働き方を提示したりするなど、採用活動を活発化させる傾向があります。これにより、転職希望者はより良い条件での転職が期待でき、自身のキャリアアップやワークライフバランスの向上につながる可能性が高まります。例えば、2024年7月時点の建設躯体工事従事者の有効求人倍率が8.50倍と非常に高かったように、特定の職種では人材が圧倒的に不足しているため、未経験者であっても採用されやすい傾向が見られます。このように、求人倍率が高い市場では、転職希望者が主導権を握りやすい状況となるのです。
企業側から見ると、多くの応募者が集まるため、採用活動の難易度が下がり、自社が求める人材を厳選して採用できるメリットがあります。求職者は競争が激しくなるため、より高いスキルや経験が求められたり、希望する条件を妥協したりする必要が生じるかもしれません。これは特に、人気の職種や特定の地域で顕著に見られる傾向です。例えば、一般事務職は常に求職者が多く、企業側が応募者を選びやすい状況が続く傾向にあります。このような市場では、求職者は自身の強みを明確にし、差別化を図ることが重要になります。
この倍率を見ることで、現在の求職状況が企業優位の「買い手市場」なのか、求職者優位の「売り手市場」なのかを判断することができます。例えば、求人倍率が2倍であれば、1人の求職者に対して2件の有効な求人があることを意味し、転職希望者にとっては選択肢が多く、希望に合った職場を見つけやすい状況と言えるでしょう。
有効求人倍率の計算式と使われる用語の意味
有効求人倍率は、雇用市場の状況を測る上で重要な指標であり、有効求人数を有効求職者数で割ることで算出されます。この計算式に含まれる「有効」という言葉は、ハローワークに登録されている求人や求職が、それぞれ有効期間内である状態を指します。具体的に、有効求人数とは、ハローワークで当月に新たに登録された求人と、前月から引き続き有効な求人を合わせた数のことです。同様に、有効求職者数とは、当月にハローワークに新規で求職の申し込みを行った人と、前月から求職活動を継続している人の合計を指します。例えば、ある月に有効求人数が200件、有効求職者数が100人だった場合、有効求人倍率は200件 ÷ 100人 = 2.0倍となります。これは、1人の求職者に対して2件の求人があることを示しており、求職者にとって選択肢が多い「売り手市場」であると判断できます。このように、有効求人倍率は、単に数字としてだけでなく、それが意味する雇用市場の需給バランスを理解することで、転職活動や採用戦略をより的確に立てるための重要な手がかりとなります。
有効求人倍率が高いと転職希望者にとって有利な「売り手市場」
有効求人倍率が高い状態は、転職希望者にとって非常に有利な「売り手市場」であることを意味します。具体的には、求職者1人に対して複数の求人が存在する状況を指し、例えば有効求人倍率が2倍であれば、1人の求職者が2件の求人の中から選択できることになります。このような市場では、求職者は自身のスキルや経験、希望する条件に合致する企業や職種をより多く見つけることが可能です。企業側は優秀な人材を確保するために、給与や福利厚生などの待遇を改善したり、柔軟な働き方を提示したりするなど、採用活動を活発化させる傾向があります。これにより、転職希望者はより良い条件での転職が期待でき、自身のキャリアアップやワークライフバランスの向上につながる可能性が高まります。例えば、2024年7月時点の建設躯体工事従事者の有効求人倍率が8.50倍と非常に高かったように、特定の職種では人材が圧倒的に不足しているため、未経験者であっても採用されやすい傾向が見られます。このように、求人倍率が高い市場では、転職希望者が主導権を握りやすい状況となるのです。
有効求人倍率が低いと企業側にとって有利な「買い手市場」
有効求人倍率が低い状況は、企業側にとって有利な「買い手市場」であることを意味します。具体的には、求人数に対して求職者数が多い状態を示し、有効求人倍率が1を下回る場合にこの傾向が顕著になります。例えば、有効求人倍率が0.5倍であれば、2人の求職者に対して1件の求人しかないことになり、転職希望者にとっては仕事探しがより困難になります。企業側から見ると、多くの応募者が集まるため、採用活動の難易度が下がり、自社が求める人材を厳選して採用できるメリットがあります。求職者は競争が激しくなるため、より高いスキルや経験が求められたり、希望する条件を妥協したりする必要が生じるかもしれません。これは特に、人気の職種や特定の地域で顕著に見られる傾向です。例えば、一般事務職は常に求職者が多く、企業側が応募者を選びやすい状況が続く傾向にあります。このような市場では、求職者は自身の強みを明確にし、差別化を図ることが重要になります。
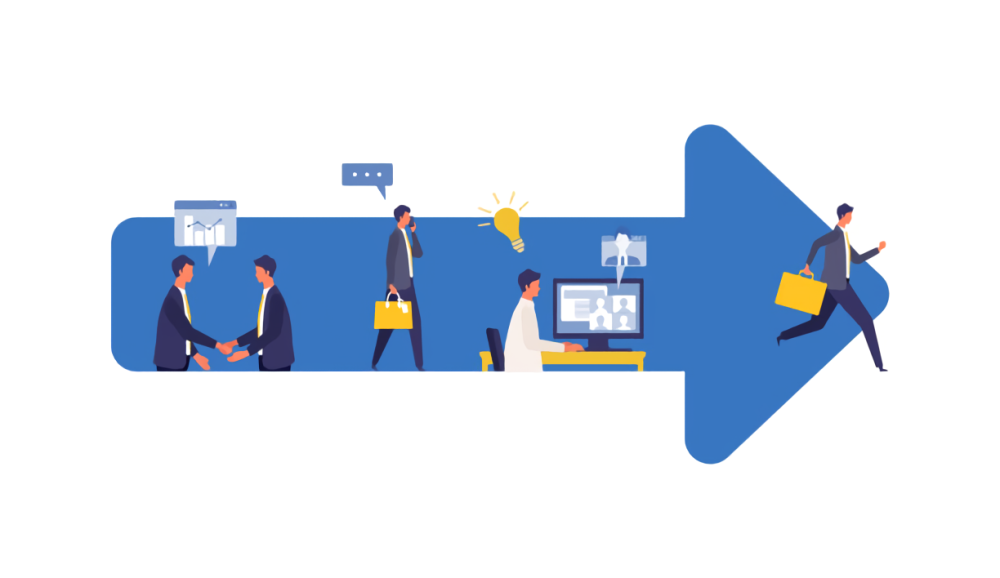
【職種別】有効求人倍率ランキング
有効求人倍率は、全体の平均値だけでなく、職種や地域によって大きく異なります。厚生労働省が公表するデータによると、特に人手不足が顕著な職種では倍率が高くなる傾向が見られます。有効求人倍率は職種や地域によって大きく異なるため、自身の希望する職種や勤務地における具体的な数値を把握することが、転職活動において非常に重要です。
次に、介護サービスの職業も非常に求人倍率が高い職種の一つです。2024年2月のデータでは、都道府県によっては介護職の有効求人倍率が5倍を超える地域が約半数を占めており、特に訪問介護を担うホームヘルパーの有効求人倍率は、直近の昨年度で14.14倍と極めて高い水準で推移していることが報告されています。これは、介護ニーズの増加に対し、労働人口の減少や労働環境の厳しさなどから人材確保が困難になっている状況を反映しています。
これらの職種は、社会的な需要が高く、景気変動の影響を受けにくい特性も持ち合わせていますが、同時に若年層のなり手不足や過重労働といった課題も抱えています。そのため、企業は人材確保に向けて、待遇改善や働き方改革を進めるなど、様々な工夫を凝らしている状況です。
特に一般事務職は、ワークライフバランスが取りやすいことや、特別な資格や経験が不要なケースが多いといった理由から人気が高く、求職者が多い傾向にあります。そのため、求人倍率が低い状況が続いており、転職の難易度が比較的高い職種と言えるでしょう。2020年のデータでは、事務職全体の有効求人倍率が0.33倍、一般事務職に限ると0.26倍と、求職者1人に対して1件未満の求人しかない狭き門でした。dodaの2024年5月の調査では、事務・アシスタント職の求人倍率は0.44倍と、全体平均の2.57倍と比較して非常に低い水準です。
クリエイター職に関しても、美術家やデザイナー、写真家、映像撮影者などの有効求人倍率は0.2倍と、低い水準です。ただし、ITエンジニア・クリエイター全体で見ると、求人倍率が10倍を超えるなど高い水準で推移している場合もあり、クリエイター職の中でも細分化すると状況が異なる場合もあります。例えば、Webデザイナーの求人倍率が7.5倍、UIデザイナーが26.8倍といったデータもあります。クリエイター職は人気の高い職業であり、スキルや経験のある人材同士での競争が起こりやすい傾向にあります。
これらの職種は、比較的低い有効求人倍率であるため、転職を希望する場合は、自身のスキルや経験を明確にし、企業にアピールすることが重要になります。
求人倍率が特に高い職種の例
求人倍率が特に高い職種には、人手不足が慢性化している分野が多く見られます。具体例として、建設・土木系の職種が挙げられます。2024年版の転職レポートによると、「建設・土木・測量技術者」の有効求人倍率は6.59倍と最も高い水準でした。また、警備員などの保安職業従事者や土木作業従事者も高い倍率を示す傾向にあります。次に、介護サービスの職業も非常に求人倍率が高い職種の一つです。2024年2月のデータでは、都道府県によっては介護職の有効求人倍率が5倍を超える地域が約半数を占めており、特に訪問介護を担うホームヘルパーの有効求人倍率は、直近の昨年度で14.14倍と極めて高い水準で推移していることが報告されています。これは、介護ニーズの増加に対し、労働人口の減少や労働環境の厳しさなどから人材確保が困難になっている状況を反映しています。
これらの職種は、社会的な需要が高く、景気変動の影響を受けにくい特性も持ち合わせていますが、同時に若年層のなり手不足や過重労働といった課題も抱えています。そのため、企業は人材確保に向けて、待遇改善や働き方改革を進めるなど、様々な工夫を凝らしている状況です。
求人倍率が比較的低い職種の例
有効求人倍率が比較的低い職種として、一般事務職とクリエイター職が挙げられます。これらの職種では、求職者数に対して求人数が少ない、または需要と供給が均衡している状況が見られます。特に一般事務職は、ワークライフバランスが取りやすいことや、特別な資格や経験が不要なケースが多いといった理由から人気が高く、求職者が多い傾向にあります。そのため、求人倍率が低い状況が続いており、転職の難易度が比較的高い職種と言えるでしょう。2020年のデータでは、事務職全体の有効求人倍率が0.33倍、一般事務職に限ると0.26倍と、求職者1人に対して1件未満の求人しかない狭き門でした。dodaの2024年5月の調査では、事務・アシスタント職の求人倍率は0.44倍と、全体平均の2.57倍と比較して非常に低い水準です。
クリエイター職に関しても、美術家やデザイナー、写真家、映像撮影者などの有効求人倍率は0.2倍と、低い水準です。ただし、ITエンジニア・クリエイター全体で見ると、求人倍率が10倍を超えるなど高い水準で推移している場合もあり、クリエイター職の中でも細分化すると状況が異なる場合もあります。例えば、Webデザイナーの求人倍率が7.5倍、UIデザイナーが26.8倍といったデータもあります。クリエイター職は人気の高い職業であり、スキルや経験のある人材同士での競争が起こりやすい傾向にあります。
これらの職種は、比較的低い有効求人倍率であるため、転職を希望する場合は、自身のスキルや経験を明確にし、企業にアピールすることが重要になります。
最新の有効求人倍率の推移からわかる雇用市場の動向
厚生労働省が発表する最新の有効求人倍率の推移を見ると、雇用市場の動向を把握できます。2025年6月の全国の有効求人倍率(季節調整値)は1.22倍で、前月より0.02ポイント低下しました。また、新規求人倍率は2.18倍で、前月より0.04ポイント上昇しています。この数値は、依然として求職者よりも求人数が多い「売り手市場」が継続していることを示しています。都道府県別に見ると、東京都の有効求人倍率は1.09倍、大阪府は1.04倍でした。福井県では1.86倍と高い水準を記録しています。一方、東京都では受理地別で1.76倍、神奈川県では0.89倍となっています。2025年7月速報値では、全国平均が前月比で0.02ポイント、前年同月比で0.05ポイント上昇し、求職者一人当たりの求人が増加傾向にあります。これは、雇用市場が全体的に底堅く推移していることを裏付けています。
産業別の新規求人を見ると、情報通信業や学術研究・専門・技術サービス業、建設業で増加が見られました。特に情報通信業は、2024年平均で就業者数が最も増加した産業の一つであり、コロナ禍においても就業者数が増えていた分野です。一方で、卸売業・小売業や生活関連サービス業・娯楽業では減少しています。宿泊業・飲食サービス業は依然として人手不足が続いている産業の一つですが、コロナ禍前の就業者数には戻っていません。
過去の推移を見ると、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた2020年、2021年には有効求人倍率が低下しましたが、その後は緩やかに回復しています。特に2020年度の有効求人倍率は1.18倍と前年度から0.42ポイント低下し、下げ幅としては1975年以来45年ぶりの大きさでした。しかし、2023年平均では1.31倍と前年より0.03ポイント上昇し、完全失業率は2.6%で前年と同水準でした。これは、求人が底堅く推移する中で、雇用情勢が改善の動きを見せていることを示唆しています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速やGX(グリーン・トランスフォーメーション)の本格化により、デジタル技術や環境・エネルギー関連の専門知識を持つ人材の需要が高まる一方、定型的な事務作業は自動化され、関連職種の求人が減少する可能性があります。このような産業構造の変化に対応できる専門スキルを持つ人材とそうでない人材との間で格差が拡大する「二極化の時代」が予測されます。
産業別の新規求人を見ると、情報通信業や学術研究・専門・技術サービス業、建設業で増加が見られました。特に情報通信業は、2024年平均で就業者数が最も増加した産業の一つであり、コロナ禍においても就業者数が増えていた分野です。一方で、卸売業・小売業や生活関連サービス業・娯楽業では減少しています。宿泊業・飲食サービス業は依然として人手不足が続いている産業の一つですが、コロナ禍前の就業者数には戻っていません。
過去の推移を見ると、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた2020年、2021年には有効求人倍率が低下しましたが、その後は緩やかに回復しています。特に2020年度の有効求人倍率は1.18倍と前年度から0.42ポイント低下し、下げ幅としては1975年以来45年ぶりの大きさでした。しかし、2023年平均では1.31倍と前年より0.03ポイント上昇し、完全失業率は2.6%で前年と同水準でした。これは、求人が底堅く推移する中で、雇用情勢が改善の動きを見せていることを示唆しています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速やGX(グリーン・トランスフォーメーション)の本格化により、デジタル技術や環境・エネルギー関連の専門知識を持つ人材の需要が高まる一方、定型的な事務作業は自動化され、関連職種の求人が減少する可能性があります。このような産業構造の変化に対応できる専門スキルを持つ人材とそうでない人材との間で格差が拡大する「二極化の時代」が予測されます。

有効求人倍率のデータを見る際に知っておきたい注意点
有効求人倍率のデータは、雇用市場の動向を把握する上で非常に有用ですが、その特性を理解した上で読み解くことが重要です。いくつかの注意点が存在するため、これらを踏まえることで、より正確な状況判断が可能になります。
近年ではインターネットを活用した転職活動が主流となり、多くの企業が民間のプラットフォームを利用して求人情報を発信しています。しかし、これらの求人情報は有効求人倍率の数値には反映されないため、公表されている有効求人倍率だけを見て、求人市場全体の状況を判断することは適切ではありません。転職を検討している方は、ハローワーク以外の多様な情報源も活用し、幅広い視点から自身の希望に合った求人を探すことが重要です。
厚生労働省は「正社員有効求人倍率」も別途公表しており、こちらの数値は正社員の求人数と正社員を希望する求職者数から算出されているため、正社員での転職を検討している場合には、この「正社員有効求人倍率」を参照することが、より実態に即した判断に繋がります。正社員有効求人倍率は、全体の有効求人倍率よりも低い傾向にあることが多いため、希望する雇用形態に応じてデータを確認することが重要です。
また、個別の職種や地域によって状況が異なるため、全国平均の数値だけでは判断しきれない側面も存在します。例えば、2020年の有効求人倍率は、新型コロナウイルス感染症の影響で大きく低下しました。しかし、一部の職種ではオンライン化の進展に伴い、IT関連職種の求人が増加するなど、全体とは異なる動きを見せていました。このように、特定の産業や職種、または地域において、平均値とは異なる雇用情勢が進行している場合があります。したがって、有効求人倍率を解釈する際には、個別の状況を考慮し、他の経済指標や業界ごとの動向も合わせて多角的に分析することが重要です。
ハローワーク経由の求人のみが対象であること
有効求人倍率は、ハローワークを通じて公開された求人数と求職者数から算出される指標です。このため、民間の転職サイトや求人情報誌、人材紹介会社、または企業が自社サイトなどで直接募集している求人は、有効求人倍率の計算には含まれていません。近年ではインターネットを活用した転職活動が主流となり、多くの企業が民間のプラットフォームを利用して求人情報を発信しています。しかし、これらの求人情報は有効求人倍率の数値には反映されないため、公表されている有効求人倍率だけを見て、求人市場全体の状況を判断することは適切ではありません。転職を検討している方は、ハローワーク以外の多様な情報源も活用し、幅広い視点から自身の希望に合った求人を探すことが重要です。
正社員以外の求人(パート・アルバイト)も含まれていること
有効求人倍率には、正社員の求人だけでなく、パートやアルバイト、契約社員、そして派遣社員といった非正規雇用の求人も含まれています。そのため、正社員の職を探している転職希望者にとっては、提示されている有効求人倍率が、必ずしも希望する雇用形態の求人状況を正確に表しているわけではありません。例えば、有効求人倍率が高く見えても、その内訳の多くが非正規雇用の求人である可能性も十分に考えられます。厚生労働省は「正社員有効求人倍率」も別途公表しており、こちらの数値は正社員の求人数と正社員を希望する求職者数から算出されているため、正社員での転職を検討している場合には、この「正社員有効求人倍率」を参照することが、より実態に即した判断に繋がります。正社員有効求人倍率は、全体の有効求人倍率よりも低い傾向にあることが多いため、希望する雇用形態に応じてデータを確認することが重要です。
景気の実感とズレが生じる可能性があること
有効求人倍率は景気動向と密接に連動する指標ですが、時に景気の実感とズレが生じる可能性があります。これは、有効求人倍率がハローワークのデータに基づいていることや、非正規雇用を含む全ての雇用形態の求人を対象としていることが影響しています。例えば、一時的な需要で非正規雇用の求人が増えた場合、有効求人倍率が上昇しても、必ずしも景気が好転していると実感できるわけではありません。また、個別の職種や地域によって状況が異なるため、全国平均の数値だけでは判断しきれない側面も存在します。例えば、2020年の有効求人倍率は、新型コロナウイルス感染症の影響で大きく低下しました。しかし、一部の職種ではオンライン化の進展に伴い、IT関連職種の求人が増加するなど、全体とは異なる動きを見せていました。このように、特定の産業や職種、または地域において、平均値とは異なる雇用情勢が進行している場合があります。したがって、有効求人倍率を解釈する際には、個別の状況を考慮し、他の経済指標や業界ごとの動向も合わせて多角的に分析することが重要です。
まとめ
有効求人倍率は、求職者1人あたりの求人件数を示す重要な経済指標です。この数値が高い場合は、転職希望者にとって有利な「売り手市場」であり、多くの企業が人材を求めている状況を示します。具体的には、自身のスキルや経験を活かし、より良い条件で転職できる可能性が高まります。一方、有効求人倍率が低い場合は、企業側にとって有利な「買い手市場」であり、求職者数に対して求人数が少ないため、競争が激しくなります。
職種別の有効求人倍率を見ると、その傾向は顕著に現れます。例えば、建設・土木系や介護サービス系の職種では、恒常的な人手不足から高い倍率が続いています。特に介護職の有効求人倍率は、都道府県によっては5倍を超える地域もあり、ホームヘルパーでは14.14倍と極めて高い水準です。これは、社会的な需要の増加に対して供給が追いついていない状況を反映しています。これらの職種では、未経験者でも積極的に採用されるケースが多く、転職を検討している方にとっては有利な状況と言えるでしょう。
一方で、一般事務職や一部のクリエイター職(美術家、デザイナー、写真家など)は、有効求人倍率が低い傾向にあります。例えば、2024年5月のdodaの調査では、事務・アシスタント職の求人倍率は0.44倍と、全体平均の2.57倍と比較して非常に低い水準です。これは、これらの職種が人気が高く、求職者数が多いことや、AIによる自動化の影響などが背景にあります。これらの職種で転職を成功させるためには、自身の専門スキルを磨き、企業に対して具体的な貢献価値をアピールすることが重要です。
有効求人倍率のデータを見る際には、いくつかの注意点があります。第一に、ハローワーク経由の求人のみが対象であるため、民間の転職サイトや人材紹介会社の求人は含まれていません。そのため、公表されている数値だけで市場全体を判断することは困難です。第二に、正社員以外の求人(パート・アルバイト、派遣社員など)も含まれているため、正社員での転職を希望する場合は、「正社員有効求人倍率」を参照することがより実態に即した判断に繋がります。最後に、景気の実感とズレが生じる可能性があることも理解しておく必要があります。特定職種や地域の動向、他の経済指標と合わせて多角的に分析することで、より正確な雇用情勢を把握し、自身の転職活動や企業の採用戦略に活かすことが可能です。
職種別の有効求人倍率を見ると、その傾向は顕著に現れます。例えば、建設・土木系や介護サービス系の職種では、恒常的な人手不足から高い倍率が続いています。特に介護職の有効求人倍率は、都道府県によっては5倍を超える地域もあり、ホームヘルパーでは14.14倍と極めて高い水準です。これは、社会的な需要の増加に対して供給が追いついていない状況を反映しています。これらの職種では、未経験者でも積極的に採用されるケースが多く、転職を検討している方にとっては有利な状況と言えるでしょう。
一方で、一般事務職や一部のクリエイター職(美術家、デザイナー、写真家など)は、有効求人倍率が低い傾向にあります。例えば、2024年5月のdodaの調査では、事務・アシスタント職の求人倍率は0.44倍と、全体平均の2.57倍と比較して非常に低い水準です。これは、これらの職種が人気が高く、求職者数が多いことや、AIによる自動化の影響などが背景にあります。これらの職種で転職を成功させるためには、自身の専門スキルを磨き、企業に対して具体的な貢献価値をアピールすることが重要です。
有効求人倍率のデータを見る際には、いくつかの注意点があります。第一に、ハローワーク経由の求人のみが対象であるため、民間の転職サイトや人材紹介会社の求人は含まれていません。そのため、公表されている数値だけで市場全体を判断することは困難です。第二に、正社員以外の求人(パート・アルバイト、派遣社員など)も含まれているため、正社員での転職を希望する場合は、「正社員有効求人倍率」を参照することがより実態に即した判断に繋がります。最後に、景気の実感とズレが生じる可能性があることも理解しておく必要があります。特定職種や地域の動向、他の経済指標と合わせて多角的に分析することで、より正確な雇用情勢を把握し、自身の転職活動や企業の採用戦略に活かすことが可能です。
ご不明点はお気軽にお問い合わせください
この度はリソースクリエイションにご興味を持ってくださいまして、誠にありがとうございます。
ご不明点・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。
殿堂入り記事
オススメ記事
オススメ記事
殿堂入り記事