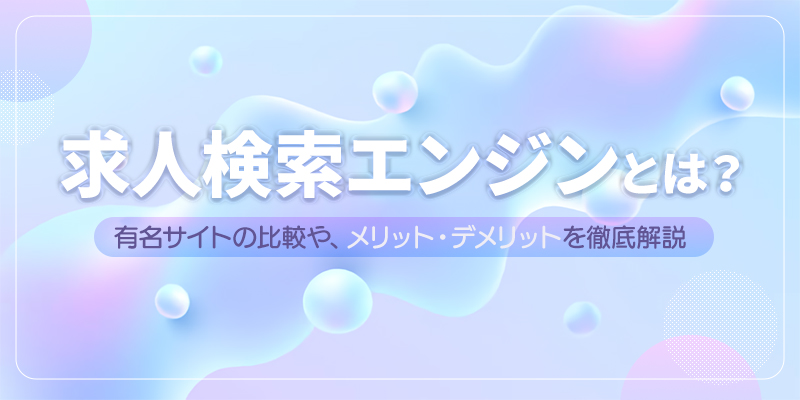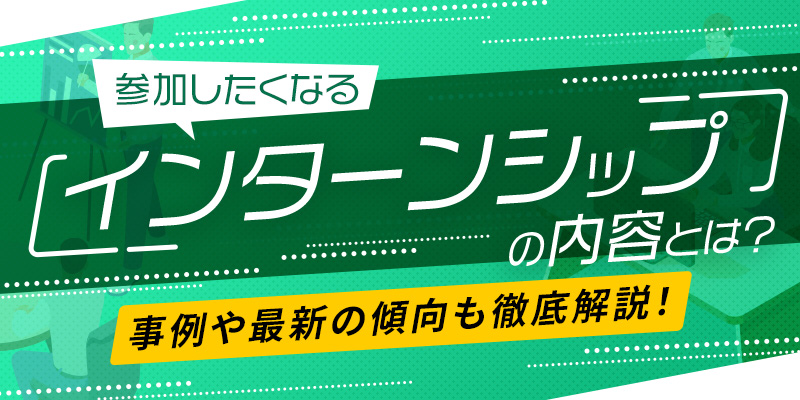採用支援
内定式の意味とは?人事担当者向けに目的や準備の流れを解説
更新日:2025.09.29
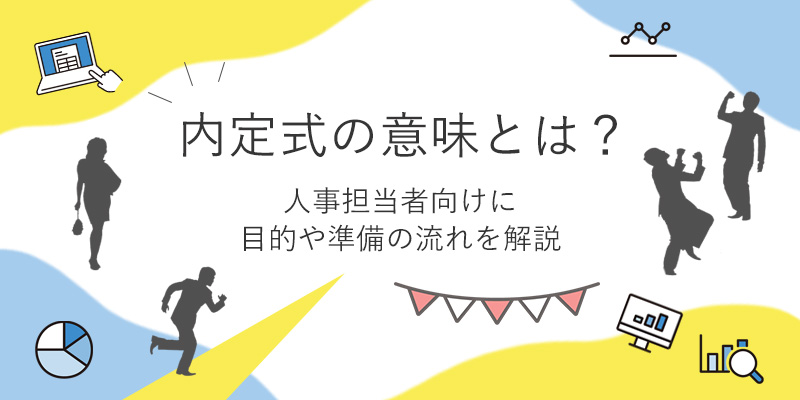
内定式は、企業が内定者に対して正式に入社の意思を確認し、歓迎の意を示す重要な式典です。
単なるセレモニーではなく、内定者の入社意欲を高め、内定辞退を防ぐという人事戦略上の重要な意義を持っています。
人事担当者はその目的を正しく理解し、入念な準備と当日の円滑な運営を行うことが求められます。
この記事では、内定式の基本的な知識から、具体的な準備の進め方、成功させるためのポイントまでを網羅的に解説します。
まずは基本から|内定式とはどんな式典か
内定式とは、企業が採用選考を経て内定を出した学生などに対し、正式に内定を通知するための式典を指します。経団連の指針に基づき10月1日に行われることが多いです。
この式典を通じて、企業は内定者に入社を歓迎する姿勢を示すとともに、内定者は社会人になる自覚を新たにする機会となります。
内定者にとっては、同期入社となる仲間と初めて顔を合わせる場でもあり、企業にとっては入社までの帰属意識を高めるための重要なイベントです。
内定式の対象は「入社予定者」であり、まだ従業員ではありません。この段階では労働契約は成立していますが、入社日までは内定辞退の可能性があります。
そのため、内定式の主な目的は、入社意欲を高めて内定辞退を防ぐことにあります。
一方、入社式の対象は、4月1日をもって労働契約が開始された「新入社員」です。
企業の一員として歓迎し、社会人としての自覚を促し、組織への定着を図ることが目的となります。
開催時期も、内定式が卒業年度の10月に行われるのに対し、入社式は入社当日の4月に行われるのが一般的です。
この式典を通じて、企業は内定者に入社を歓迎する姿勢を示すとともに、内定者は社会人になる自覚を新たにする機会となります。
内定者にとっては、同期入社となる仲間と初めて顔を合わせる場でもあり、企業にとっては入社までの帰属意識を高めるための重要なイベントです。
意外と知らない?内定式と入社式の明確な違い
内定式と入社式は、対象者と目的が異なります。内定式の対象は「入社予定者」であり、まだ従業員ではありません。この段階では労働契約は成立していますが、入社日までは内定辞退の可能性があります。
そのため、内定式の主な目的は、入社意欲を高めて内定辞退を防ぐことにあります。
一方、入社式の対象は、4月1日をもって労働契約が開始された「新入社員」です。
企業の一員として歓迎し、社会人としての自覚を促し、組織への定着を図ることが目的となります。
開催時期も、内定式が卒業年度の10月に行われるのに対し、入社式は入社当日の4月に行われるのが一般的です。
なぜ開催する?人事担当者が押さえるべき内定式の3つの目的
内定式は単なる慣例として行われるものではなく、企業にとって明確な戦略的意図があります。人事担当者は、この式典が持つ複数の目的を理解し、それぞれを達成できるよう企画・運営することが重要です。
主な目的として「内定辞退の防止」「入社後のミスマッチの低減」「同期の連帯感醸成」の3点が挙げられます。
これらの目的を意識することで、内定式のプログラム内容や演出の方向性がより明確になり、投資対効果の高いイベントを実現できます。
複数の企業から内定を得ている学生も少なくないため、自社を選んでもらうための最後のひと押しとして機能します。
経営層から直接ビジョンや期待を語ってもらったり、先輩社員が会社の魅力を伝えたりすることで、企業の熱意を内定者に届けます。
会社からの歓迎の意を明確に示すことで、内定者は「この会社の一員になる」という実感を強く持ち、入社までの長い期間、モチベーションを保ちやすくなります。
事業内容の説明やオフィスツアー、社員との座談会などを通じて、入社後の働き方をより具体的にイメージしてもらいます。
これにより、内定者が抱いていた期待と入社後の現実とのギャップを最小限に抑え、早期離職につながるミスマッチを未然に防ぎます。
将来の配属先の情報やキャリアパスについて言及することも、内定者が自身のキャリアを考える上で有効な情報提供となります。
特に採用人数が多い企業の場合、この機会がなければ入社まで互いの顔を知らないまま過ごすことになります。
グループワークや懇親会といった交流の場を設けることで、内定者同士のコミュニケーションを促し、横のつながりを築くきっかけを作ります。
ここで生まれた連帯感は、入社後の研修や業務において互いに支え合う関係性の土台となり、スムーズな職場適応を助ける重要な要素となります。
主な目的として「内定辞退の防止」「入社後のミスマッチの低減」「同期の連帯感醸成」の3点が挙げられます。
これらの目的を意識することで、内定式のプログラム内容や演出の方向性がより明確になり、投資対効果の高いイベントを実現できます。
内定者の入社意欲を高め、内定辞退を防ぐ
内定式の最も重要な目的の一つは、内定者の入社意欲を維持・向上させ、内定辞退を防ぐことです。複数の企業から内定を得ている学生も少なくないため、自社を選んでもらうための最後のひと押しとして機能します。
経営層から直接ビジョンや期待を語ってもらったり、先輩社員が会社の魅力を伝えたりすることで、企業の熱意を内定者に届けます。
会社からの歓迎の意を明確に示すことで、内定者は「この会社の一員になる」という実感を強く持ち、入社までの長い期間、モチベーションを保ちやすくなります。
会社への理解を深めてもらい、入社後のミスマッチを減らす
内定式は、選考過程では伝えきれなかった企業の文化や事業内容、働き方について、内定者の理解を深める絶好の機会です。事業内容の説明やオフィスツアー、社員との座談会などを通じて、入社後の働き方をより具体的にイメージしてもらいます。
これにより、内定者が抱いていた期待と入社後の現実とのギャップを最小限に抑え、早期離職につながるミスマッチを未然に防ぎます。
将来の配属先の情報やキャリアパスについて言及することも、内定者が自身のキャリアを考える上で有効な情報提供となります。
内定者同士の絆を深め、同期としての連帯感を生み出す
内定式は、これから共に働く同期入社の仲間たちが初めて一堂に会する場です。特に採用人数が多い企業の場合、この機会がなければ入社まで互いの顔を知らないまま過ごすことになります。
グループワークや懇親会といった交流の場を設けることで、内定者同士のコミュニケーションを促し、横のつながりを築くきっかけを作ります。
ここで生まれた連帯感は、入社後の研修や業務において互いに支え合う関係性の土台となり、スムーズな職場適応を助ける重要な要素となります。
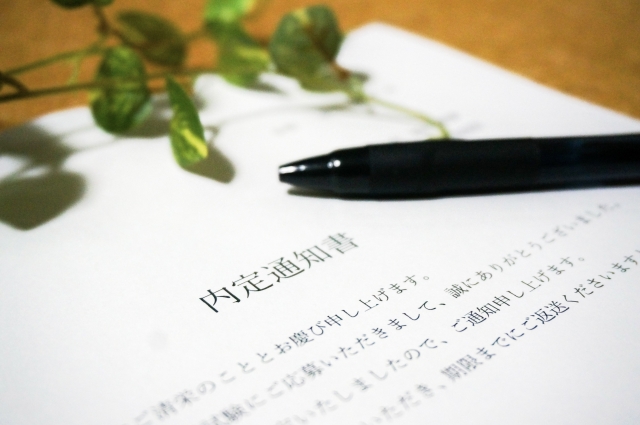
人事担当者が進める内定式の準備|5つのステップ
内定式を成功させるためには、周到で計画的な準備が不可欠です。当日のプログラムが魅力的であっても、事前の段取りに不備があれば円滑な運営は望めません。
人事担当者は、開催時期の決定から備品の手配に至るまで、多岐にわたるタスクを管理する必要があります。
ここでは、内定式の準備を5つの具体的なステップに分けて解説します。
この流れに沿って進めることで、抜け漏れなく効率的に準備を進めることが可能です。
内定者の学業への影響などを考慮し、10月中の別日や土日に設定することも可能です。
開催場所は、参加する内定者の人数やプログラムの内容を考慮して選定します。
自社の会議室やホールを利用するほか、外部の貸会議室やホテルも選択肢となります。会場のアクセスや設備、予算などを総合的に判断し、早めに予約を押さえることが重要です。
遠方からの参加者がいる場合は、交通費や宿泊施設の手配についても検討しておきましょう。
役員挨拶や内定証書授与といった式典的な要素だけでなく、内定者の満足度を高め、交流を促進するコンテンツを盛り込むことが成功の鍵です。
例えば、先輩社員との座談会、オフィスツアー、内定者同士のグループワークなどが考えられます。
それぞれのプログラムに要する時間を算出し、休憩時間も考慮しながら全体のタイムスケジュールを組み立てます。
内定者の緊張を和らげ、「参加して良かった」と感じてもらえるような内容を企画することが大切です。
メールでの送付が一般的ですが、丁寧な印象を与えるために郵送を選ぶ企業もあります。
案内状には、開催概要のほかに、当日の持ち物、服装などを明記します。
服装については「スーツ着用」」や「ビジネスカジュアル」など、内定者が迷わないよう具体的な指示を記載すると親切です。
交通費の精算方法や、出欠確認の返信期限も忘れずに記載し、早めに参加人数を把握することで、その後の準備をスムーズに進められます。
祝辞を述べる役員、内定証書を授与する人事部長、懇親会を盛り上げる先輩社員など、それぞれの役割を明確にし、早めに出席を依頼してスケジュールを確保してもらう必要があります。
当日の円滑な進行のために、タイムスケジュールや各自の役割、進行上のルールなどをまとめた進行表を作成し、事前に共有しておきましょう。
出席する社員全員が「会社の代表」であるという意識を持ち、内定者を温かく迎え入れる姿勢を統一することが重要です。
内定証書は式の象徴となる最も重要な備品であり、内定者の氏名に誤りがないか複数人で入念にチェックすることが不可欠です。
その他、入社承諾書や各種手続き書類、会社案内、ノベルティグッズなどの配布物も用意します。内定期間中の課題としてレポートの提出を求める場合は、そのための資料も忘れずに準備しましょう。
会場で使用するプロジェクターやスクリーン、マイク、受付で使う備品などもリストに含め、事前に動作確認を行っておくと安心です。
人事担当者は、開催時期の決定から備品の手配に至るまで、多岐にわたるタスクを管理する必要があります。
ここでは、内定式の準備を5つの具体的なステップに分けて解説します。
この流れに沿って進めることで、抜け漏れなく効率的に準備を進めることが可能です。
STEP1:開催時期と開催場所を決定する
多くの企業は経団連の指針に倣い、10月1日に内定式を開催しますが、これはあくまで目安であり、法的な強制力はありません。内定者の学業への影響などを考慮し、10月中の別日や土日に設定することも可能です。
開催場所は、参加する内定者の人数やプログラムの内容を考慮して選定します。
自社の会議室やホールを利用するほか、外部の貸会議室やホテルも選択肢となります。会場のアクセスや設備、予算などを総合的に判断し、早めに予約を押さえることが重要です。
遠方からの参加者がいる場合は、交通費や宿泊施設の手配についても検討しておきましょう。
STEP2:当日のプログラム内容を具体的に計画する
内定式の目的を達成するため、当日に何を行うかを具体的に計画します。役員挨拶や内定証書授与といった式典的な要素だけでなく、内定者の満足度を高め、交流を促進するコンテンツを盛り込むことが成功の鍵です。
例えば、先輩社員との座談会、オフィスツアー、内定者同士のグループワークなどが考えられます。
それぞれのプログラムに要する時間を算出し、休憩時間も考慮しながら全体のタイムスケジュールを組み立てます。
内定者の緊張を和らげ、「参加して良かった」と感じてもらえるような内容を企画することが大切です。
STEP3:内定者への案内状を作成・送付する
開催日時や場所、プログラムが決定したら、内定者へ送付する案内状を作成します。メールでの送付が一般的ですが、丁寧な印象を与えるために郵送を選ぶ企業もあります。
案内状には、開催概要のほかに、当日の持ち物、服装などを明記します。
服装については「スーツ着用」」や「ビジネスカジュアル」など、内定者が迷わないよう具体的な指示を記載すると親切です。
交通費の精算方法や、出欠確認の返信期限も忘れずに記載し、早めに参加人数を把握することで、その後の準備をスムーズに進められます。
STEP4:社内関係者への出席依頼と役割分担を行う
内定式には、経営層や役員、現場の管理職や若手社員など、多くの社員が関わります。祝辞を述べる役員、内定証書を授与する人事部長、懇親会を盛り上げる先輩社員など、それぞれの役割を明確にし、早めに出席を依頼してスケジュールを確保してもらう必要があります。
当日の円滑な進行のために、タイムスケジュールや各自の役割、進行上のルールなどをまとめた進行表を作成し、事前に共有しておきましょう。
出席する社員全員が「会社の代表」であるという意識を持ち、内定者を温かく迎え入れる姿勢を統一することが重要です。
STEP5:内定証書や配布資料など必要な備品を用意する
当日に必要となる備品をリストアップし、漏れなく準備を進めます。内定証書は式の象徴となる最も重要な備品であり、内定者の氏名に誤りがないか複数人で入念にチェックすることが不可欠です。
その他、入社承諾書や各種手続き書類、会社案内、ノベルティグッズなどの配布物も用意します。内定期間中の課題としてレポートの提出を求める場合は、そのための資料も忘れずに準備しましょう。
会場で使用するプロジェクターやスクリーン、マイク、受付で使う備品などもリストに含め、事前に動作確認を行っておくと安心です。
当日の流れがわかる!内定式の一般的なプログラム例
内定式の企画を初めて担当する方にとって、当日の具体的な流れをイメージするのは難しいかもしれません。
ここでは、多くの企業で採用されている一般的な内定式のプログラム構成を紹介します。
式典としての格式を保ちつつ、内定者のエンゲージメントを高める要素をバランス良く取り入れることがポイントです。
この例をベースに、自社の社風や内定者の特性に合わせて内容をアレンジし、オリジナリティのある内定式を目指しましょう。
企業のトップが自らの言葉で会社のビジョンや内定者への期待を語ることで、式典全体が引き締まり、内定者は会社からの歓迎の意を強く感じ取ることができます。
内容は、会社の歴史や事業の将来性、社会における役割など、内定者が自社で働くことに誇りを持てるような、前向きで心に響くメッセージが望ましいです。
この挨拶が、内定者の入社意欲を大きく左右する重要な要素となります。
司会者が内定者の名前を1人ずつ読み上げ、代表者(社長や人事部長など)が内定証書を手渡します。
この授与の瞬間を通じて、内定者は自分が正式に会社の一員として認められたことを実感します。
人数が多い場合でも流れ作業にならないよう、授与者が内定者と目を合わせ、一言「おめでとう」「期待しています」といった言葉をかけるだけでも、非常に丁寧な印象を与えることができます。
自己紹介では、氏名や大学名だけでなく、趣味や学生時代に打ち込んだことなどを話してもらうと、人柄が伝わりやすくなります。
また、社会人になるにあたっての決意表明を語ってもらうことで、入社への意欲を再確認する機会にもなります。
他社事例ではグループごとに発表を行うなど、緊張を和らげる工夫も見られます。
人事担当者は、和やかな雰囲気を作り、内定者が話しやすいようサポートすることが大切です。
雇用契約書や入社承諾書の取り交わし、その他提出が必要な書類の配布と説明、回収などを行います。書類の記入に時間がかかる場合は、事前に送付し、当日は質疑応答の時間とすることも可能です。
また、内定期間中の研修や懇親会の有無、連絡手段、入社式までの具体的なスケジュールなどを明確に伝えます。
これにより、内定者は入社までの見通しを立てることができ、不安を解消できます。
食事や飲み物を用意し、立食形式にすると、内定者も社員も自由に移動しやすくなります。
内定者同士の親睦を深めると同時に、年齢の近い先輩社員や管理職と直接話す機会を提供することで、社風への理解を促進し、入社後の人間関係に対する不安を和らげます。
社員が積極的に内定者に話しかけ、質問に答えることで、内定者の帰属意識を高める効果が期待できす。
ここでは、多くの企業で採用されている一般的な内定式のプログラム構成を紹介します。
式典としての格式を保ちつつ、内定者のエンゲージメントを高める要素をバランス良く取り入れることがポイントです。
この例をベースに、自社の社風や内定者の特性に合わせて内容をアレンジし、オリジナリティのある内定式を目指しましょう。
経営層からの祝辞・挨拶
内定式の冒頭で、社長や役員といった経営トップから祝辞や歓迎の挨拶を行います。企業のトップが自らの言葉で会社のビジョンや内定者への期待を語ることで、式典全体が引き締まり、内定者は会社からの歓迎の意を強く感じ取ることができます。
内容は、会社の歴史や事業の将来性、社会における役割など、内定者が自社で働くことに誇りを持てるような、前向きで心に響くメッセージが望ましいです。
この挨拶が、内定者の入社意欲を大きく左右する重要な要素となります。
内定者一人ひとりへの内定証書授与
内定証書の授与は、内定式のハイライトとなるプログラムです。司会者が内定者の名前を1人ずつ読み上げ、代表者(社長や人事部長など)が内定証書を手渡します。
この授与の瞬間を通じて、内定者は自分が正式に会社の一員として認められたことを実感します。
人数が多い場合でも流れ作業にならないよう、授与者が内定者と目を合わせ、一言「おめでとう」「期待しています」といった言葉をかけるだけでも、非常に丁寧な印象を与えることができます。
内定者による自己紹介や決意表明
内定者自身が発言する機会を設けることで、受け身の参加から主体的な参加へと意識を転換させます。自己紹介では、氏名や大学名だけでなく、趣味や学生時代に打ち込んだことなどを話してもらうと、人柄が伝わりやすくなります。
また、社会人になるにあたっての決意表明を語ってもらうことで、入社への意欲を再確認する機会にもなります。
他社事例ではグループごとに発表を行うなど、緊張を和らげる工夫も見られます。
人事担当者は、和やかな雰囲気を作り、内定者が話しやすいようサポートすることが大切です。
入社に向けた事務手続きと今後のスケジュール説明
内定式は、入社に必要な事務手続きを行うための機会でもあります。雇用契約書や入社承諾書の取り交わし、その他提出が必要な書類の配布と説明、回収などを行います。書類の記入に時間がかかる場合は、事前に送付し、当日は質疑応答の時間とすることも可能です。
また、内定期間中の研修や懇親会の有無、連絡手段、入社式までの具体的なスケジュールなどを明確に伝えます。
これにより、内定者は入社までの見通しを立てることができ、不安を解消できます。
先輩社員も交えた懇親会で交流を深める
式典の終了後には、懇親会を開催し、リラックスした雰囲気で交流を深める時間を設けることが一般的です。食事や飲み物を用意し、立食形式にすると、内定者も社員も自由に移動しやすくなります。
内定者同士の親睦を深めると同時に、年齢の近い先輩社員や管理職と直接話す機会を提供することで、社風への理解を促進し、入社後の人間関係に対する不安を和らげます。
社員が積極的に内定者に話しかけ、質問に答えることで、内定者の帰属意識を高める効果が期待できす。
失敗しないために!内定式を成功させる3つのポイント
内定式は、周到な準備と計画のもとに実施されるべき重要なイベントです。しかし、成功を収めるためには、当日の運営における細やかな配慮が欠かせません。
内定式の本来の目的を達成し、内定者にとって忘れられない一日とするために、人事担当者が押さえておくべきポイントがいくつか存在します。
ここでは、内定式を成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。
これらを意識することで、イベントの質を格段に向上させることができます。
受付での明るい声かけや、式典が始まる前のアイスブレイク、親しみやすいBGMの選曲などが有効です。
さらに、懇親会では社員が積極的に内定者の輪に加わり、会話をリードすることで、内定者の孤立を防ぎます。
このような細やかな配慮の準備が、内定者の満足度を大きく左右します。
事前に詳細なタイムスケジュールを作成し、司会者や登壇者、運営スタッフ全員で共有することが不可欠です。
特に祝辞や挨拶は長くなりがちなので、登壇者には事前に持ち時間を伝えるというルールを設けるのが賢明です。
また、プログラムの合間に適度な休憩を挟むことで、参加者の集中力を維持できます。
万が一のトラブルに備えて時間に少し余裕を持たせた計画を立てておくと、慌てずに対処でき、円滑な進行が可能です。
内定者の良きロールモデルとなるような、仕事に誇りを持ち、コミュニケーション能力の高い社員が適任です。
また、内定者の出身大学のOB・OGを参加させると、親近感が湧きやすくなります。
参加する社員の人数も重要で、内定者一人ひとりと話せる機会が確保できるよう調整します。
出席社員には事前に内定式の趣旨を共有し、会社の代表としての役割を意識してもらうことが大切です。
内定式の本来の目的を達成し、内定者にとって忘れられない一日とするために、人事担当者が押さえておくべきポイントがいくつか存在します。
ここでは、内定式を成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。
これらを意識することで、イベントの質を格段に向上させることができます。
内定者の緊張をほぐす雰囲気作りを心がける
内定者の多くは社会人経験がなく、企業の役員や大勢の社員を前にして強い緊張を感じています。そのため、人事担当者は彼らを温かく迎え入れ、リラックスさせる雰囲気作りを最優先に考えるべきです。受付での明るい声かけや、式典が始まる前のアイスブレイク、親しみやすいBGMの選曲などが有効です。
さらに、懇親会では社員が積極的に内定者の輪に加わり、会話をリードすることで、内定者の孤立を防ぎます。
このような細やかな配慮の準備が、内定者の満足度を大きく左右します。
タイムスケジュールを徹底し、円滑な進行を目指す
内定式は限られた時間の中で多くのプログラムをこなすため、時間管理が成功の鍵を握ります。事前に詳細なタイムスケジュールを作成し、司会者や登壇者、運営スタッフ全員で共有することが不可欠です。
特に祝辞や挨拶は長くなりがちなので、登壇者には事前に持ち時間を伝えるというルールを設けるのが賢明です。
また、プログラムの合間に適度な休憩を挟むことで、参加者の集中力を維持できます。
万が一のトラブルに備えて時間に少し余裕を持たせた計画を立てておくと、慌てずに対処でき、円滑な進行が可能です。
出席する社員の人選は慎重に行う
内定式に参加する先輩社員は、内定者にとって「会社の顔」であり、入社の決め手にもなり得る存在です。そのため、出席者の人選は慎重に行う必要があります。内定者の良きロールモデルとなるような、仕事に誇りを持ち、コミュニケーション能力の高い社員が適任です。
また、内定者の出身大学のOB・OGを参加させると、親近感が湧きやすくなります。
参加する社員の人数も重要で、内定者一人ひとりと話せる機会が確保できるよう調整します。
出席社員には事前に内定式の趣旨を共有し、会社の代表としての役割を意識してもらうことが大切です。

【最新】オンライン内定式を開催する場合の注意点
近年、働き方の多様化や地理的な制約、感染症対策などを背景に、オンラインで内定式を実施する企業が増加しています。
オンライン開催は、コスト削減や参加しやすさといったメリットがある一方で、対面とは異なる課題も存在します。
オンラインでの開催の有無を検討している人事担当者は、その特性を十分に理解した上で、自社に最適な形式を判断することが求められます。
ここでは、オンライン内定式を成功させるための注意点を解説します。
遠方に住む内定者も移動や宿泊の負担なく参加でき、企業側も会場費や交通費といったコストを大幅に削減できます。
また、役員や多忙な社員もスケジュール調整がしやすく、自席から気軽に参加できるため、より多くの関係者が内定者と接点を持つ機会を創出できます。
録画機能を使えば、当日都合が悪かった内定者も後から視聴可能となり、情報格差が生まれません。
これらのメリットは、参加のハードルを下げ、内定式本来の意義を高める上で有効です。
この課題を克服するためには、双方向性を意識したプログラムの工夫が不可欠です。
ブレイクアウトルーム機能を活用して少人数のグループディスカッションの時間を設けたり、チャットやリアクション機能でリアルタイムの反応を促したりすることが有効です。
企業の熱意を伝えるためにも、一方的な配信に終始せず、Q&Aセッションを設けるなど、内定者との対話を重視した構成が求められます。
音声が途切れたり、映像が止まったりするトラブルは、参加者の集中力を削ぎ、式の雰囲気を損なう原因となります。
これを防ぐため、事前に使用するWeb会議ツールの推奨環境を内定者に案内し、接続テストの機会を設けることが推奨されます。
また、当日のトラブルに備え、緊急時の連絡先や対処法をまとめたマニュアルを共有しておくと安心です。
配信側も、機材やネットワーク環境を入念にチェックし、安定した環境を確保しておくことが必須です。
内定式だけでなく、オンラインで内定者懇親会を行うことも効果的です。オンライン内定者懇親会についてはこちらの記事もご参照ください。
オンライン開催は、コスト削減や参加しやすさといったメリットがある一方で、対面とは異なる課題も存在します。
オンラインでの開催の有無を検討している人事担当者は、その特性を十分に理解した上で、自社に最適な形式を判断することが求められます。
ここでは、オンライン内定式を成功させるための注意点を解説します。
オンライン開催で得られるメリットとは
オンライン内定式の最大のメリットは、場所の制約を受けない点です。遠方に住む内定者も移動や宿泊の負担なく参加でき、企業側も会場費や交通費といったコストを大幅に削減できます。
また、役員や多忙な社員もスケジュール調整がしやすく、自席から気軽に参加できるため、より多くの関係者が内定者と接点を持つ機会を創出できます。
録画機能を使えば、当日都合が悪かった内定者も後から視聴可能となり、情報格差が生まれません。
これらのメリットは、参加のハードルを下げ、内定式本来の意義を高める上で有効です。
一体感を醸成するためのプログラムを工夫する
オンライン開催における最大の課題は、対面と比較して参加者の一体感が生まれにくい点です。この課題を克服するためには、双方向性を意識したプログラムの工夫が不可欠です。
ブレイクアウトルーム機能を活用して少人数のグループディスカッションの時間を設けたり、チャットやリアクション機能でリアルタイムの反応を促したりすることが有効です。
企業の熱意を伝えるためにも、一方的な配信に終始せず、Q&Aセッションを設けるなど、内定者との対話を重視した構成が求められます。
事前に参加者の通信環境を確認しておく
オンラインイベントの成否は、通信環境の安定性に大きく左右されます。音声が途切れたり、映像が止まったりするトラブルは、参加者の集中力を削ぎ、式の雰囲気を損なう原因となります。
これを防ぐため、事前に使用するWeb会議ツールの推奨環境を内定者に案内し、接続テストの機会を設けることが推奨されます。
また、当日のトラブルに備え、緊急時の連絡先や対処法をまとめたマニュアルを共有しておくと安心です。
配信側も、機材やネットワーク環境を入念にチェックし、安定した環境を確保しておくことが必須です。
内定式だけでなく、オンラインで内定者懇親会を行うことも効果的です。オンライン内定者懇親会についてはこちらの記事もご参照ください。
まとめ
内定式は、内定者と企業が初めて公式に顔を合わせる重要な機会であり、内定辞退の防止や入社後の定着率向上に大きく貢献するイベントです。
人事担当者は、その意義と目的を深く理解し、計画的な準備と細やかな配慮に基づいた運営を行う必要があります。
本記事で紹介した準備のステップ、プログラム例、成功のポイントなどを参考に、自社の理念や文化が伝わるような内定式を企画しましょう。
実施後には、アンケートやレポートなどを通じて内定者からのフィードバックを収集し、次年度の開催に向けた改善点として活かしていく視点も重要です。
また、内定式後も、内定者への継続的なフォローが必要不可欠です。内定者から喜ばれるフォローテクニックについてはこちらの記事も参考になります。
人事担当者は、その意義と目的を深く理解し、計画的な準備と細やかな配慮に基づいた運営を行う必要があります。
本記事で紹介した準備のステップ、プログラム例、成功のポイントなどを参考に、自社の理念や文化が伝わるような内定式を企画しましょう。
実施後には、アンケートやレポートなどを通じて内定者からのフィードバックを収集し、次年度の開催に向けた改善点として活かしていく視点も重要です。
また、内定式後も、内定者への継続的なフォローが必要不可欠です。内定者から喜ばれるフォローテクニックについてはこちらの記事も参考になります。
ご不明点はお気軽にお問い合わせください
この度はリソースクリエイションにご興味を持ってくださいまして、誠にありがとうございます。
ご不明点・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。
殿堂入り記事
オススメ記事
オススメ記事
殿堂入り記事