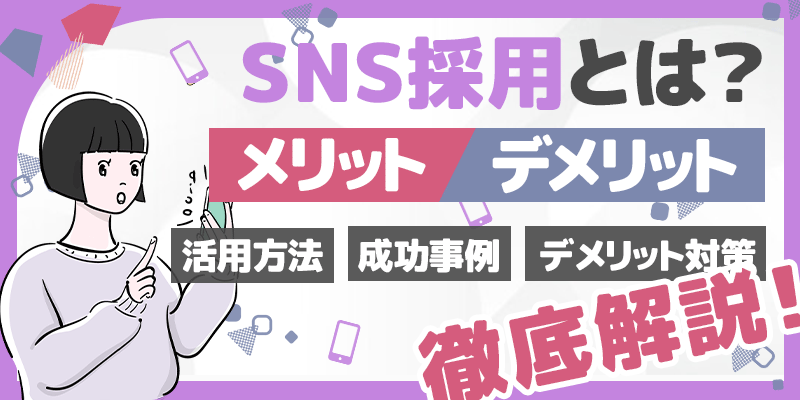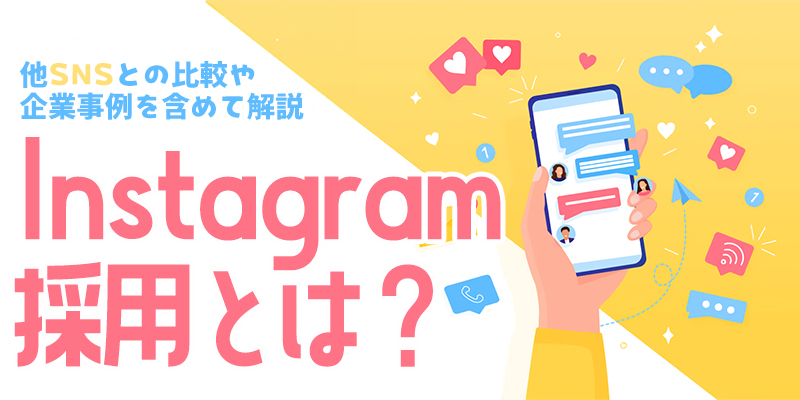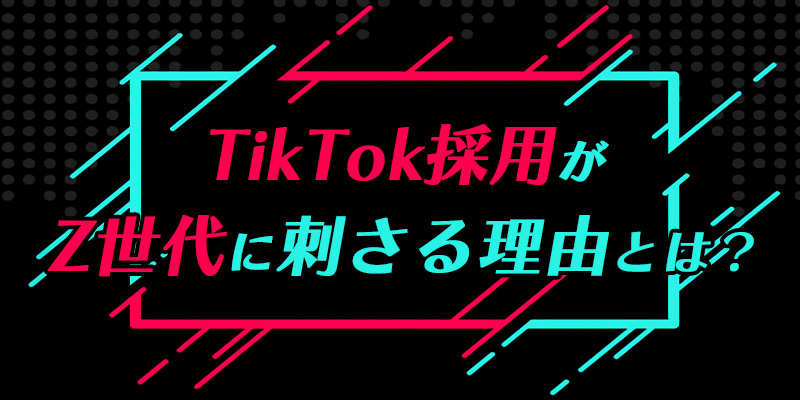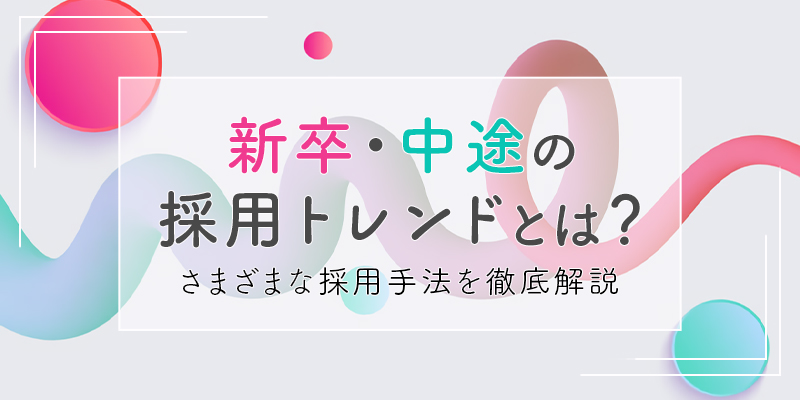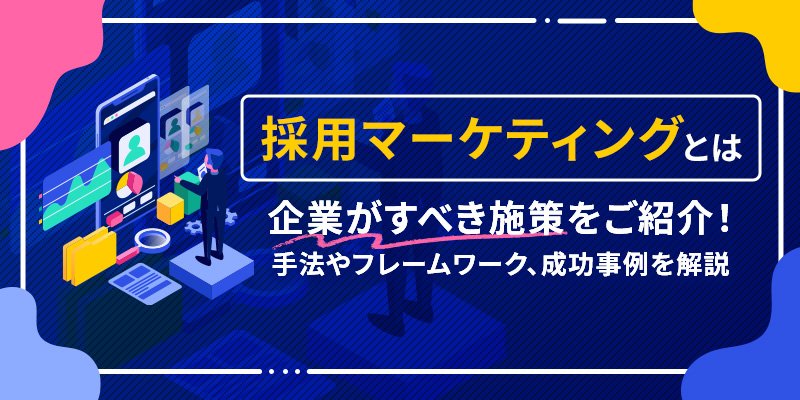採用支援
採用面接に来ないのはなぜ?考えられる理由と今すぐできる対策
更新日:2025.08.21
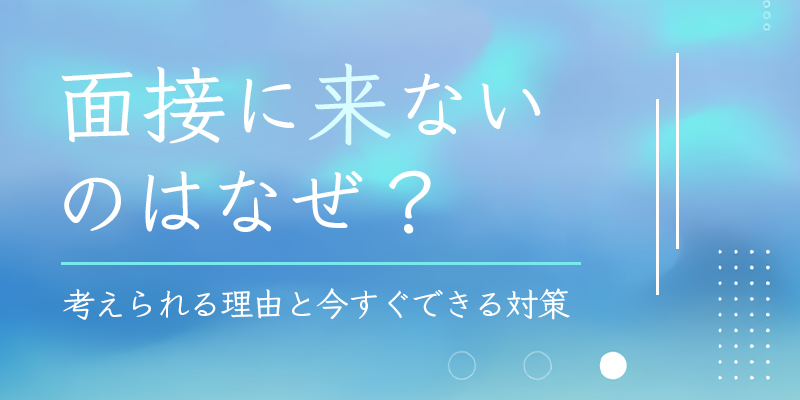
採用活動において、応募者が採用面接に来ないという事態は、多くの採用担当者や人事担当者が直面する課題です。面接の無断欠席やドタキャンは、時間やコストの損失だけでなく、採用計画にも大きな影響を与えます。このような事態を防ぐためには、応募者が面接に来ない理由を理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。
本記事では、応募者が面接に来ない主な理由と、明日から実践できる具体的な対策、そして万が一面接に来なかった場合の対処法について詳しく解説します。
応募者が面接に来ないのはなぜ?考えられる5つの理由
応募者が採用面接に来ない理由は一つではなく、複数の要因が絡み合っているケースが多いです。
本項目では、そのような応募者が面接に来ない場合に考えられる主な5つの理由について、詳細を解説いたします。
応募直後が最も入社意欲が高いタイミングであるため、この時期に迅速な連絡がないと、応募者は企業に対する熱意を失い、結果として面接を辞退してしまう可能性があります。求職者の約3割が当日中の連絡を希望しており、翌日中までに連絡を希望されている方が約4割というデータもあります。連絡が遅いと感じると、応募者の4割以上が他社の求人に応募したり、連絡を無視したりする可能性があるのです。
特に中途採用の場合、在職中の応募者は迅速な連絡を求めており、連絡が遅れることで「この企業は対応が遅い」という不信感につながることも考えられます。応募後の面接日程調整は即日~3日以内に行うことが目安とされています。採用担当者が他の業務を兼務している場合や、応募者が多数いる場合、事務処理に時間がかかり連絡が遅れることもあります。しかし、連絡の遅さは応募者にマイナスの印象しか与えないため、早期の連絡が採用成功の鍵となります。
特に顔が見えないコミュニケーションでは、より丁寧な対応が求められます。企業の対応が不親切だと感じた応募者は、「この会社で安心して働けるのか」という不安を抱き、面接を辞退する可能性が高まります。企業全体で応募者とのコミュニケーションマナーを徹底することが重要です。
実際に、面接辞退を経験した人の約半数(48.7%)が、「志望度が低いと感じた」ことを理由に挙げています。特に、新卒の一括採用や、Webサイトやアプリで気軽にボタン一つで応募できる求人の場合、このようなケースが多く見られます。
入社意欲が最初から低い、あるいは選考途中で下がってしまった応募者に対しては、面接への動機付けを強化する対策が不可欠です。例えば、企業独自の魅力を具体的に伝える情報提供や、カジュアルな面談形式の導入などが考えられます。
これは採用活動において避けられない側面であり、他社からの内定によって選考を辞退するケースは多々見受けられます。中には、内定辞退の連絡をせずに面接に来ないといったケースも考えられるでしょう。
応募者は面接に向けて準備をしていますが、詳細な連絡がないことで「きちんと面接にたどり着けるだろうか」「どんな人が面接官なのだろう」といった不安が増し、面接へのモチベーションが低下する可能性があります。
本項目では、そのような応募者が面接に来ない場合に考えられる主な5つの理由について、詳細を解説いたします。
応募後の連絡が遅く、選考への熱意が低いと思われている
応募者は複数の企業に同時に応募していることが多く、企業からの連絡が遅いと、他社の選考が先に進んでしまったり、応募者の入社意欲が低下したりする原因となります。応募直後が最も入社意欲が高いタイミングであるため、この時期に迅速な連絡がないと、応募者は企業に対する熱意を失い、結果として面接を辞退してしまう可能性があります。求職者の約3割が当日中の連絡を希望しており、翌日中までに連絡を希望されている方が約4割というデータもあります。連絡が遅いと感じると、応募者の4割以上が他社の求人に応募したり、連絡を無視したりする可能性があるのです。
特に中途採用の場合、在職中の応募者は迅速な連絡を求めており、連絡が遅れることで「この企業は対応が遅い」という不信感につながることも考えられます。応募後の面接日程調整は即日~3日以内に行うことが目安とされています。採用担当者が他の業務を兼務している場合や、応募者が多数いる場合、事務処理に時間がかかり連絡が遅れることもあります。しかし、連絡の遅さは応募者にマイナスの印象しか与えないため、早期の連絡が採用成功の鍵となります。
電話やメールの応対内容から企業に不信感を抱いた
応募者との最初の接点となる電話やメールでの応対は、企業の印象を大きく左右します。もし電話での言葉遣いが横柄であったり、メールの内容が機械的で冷たい印象を与えたりすると、応募者は企業に不信感を抱き、面接への意欲を失うことがあります。特に顔が見えないコミュニケーションでは、より丁寧な対応が求められます。企業の対応が不親切だと感じた応募者は、「この会社で安心して働けるのか」という不安を抱き、面接を辞退する可能性が高まります。企業全体で応募者とのコミュニケーションマナーを徹底することが重要です。
「とりあえず応募した」だけで志望度が高くない
複数の企業に同時応募している求職者の中には、書類選考を通過したものの、「とりあえず応募した」という意識が強く、面接に行く段階で「面倒になった」と感じたり、「志望度が低いから辞退しよう」と考える方が少なくありません。実際に、面接辞退を経験した人の約半数(48.7%)が、「志望度が低いと感じた」ことを理由に挙げています。特に、新卒の一括採用や、Webサイトやアプリで気軽にボタン一つで応募できる求人の場合、このようなケースが多く見られます。
入社意欲が最初から低い、あるいは選考途中で下がってしまった応募者に対しては、面接への動機付けを強化する対策が不可欠です。例えば、企業独自の魅力を具体的に伝える情報提供や、カジュアルな面談形式の導入などが考えられます。
他社から先に内定が出て選考を辞退した
応募者は複数の企業で選考を進めていることが一般的であり、その中で他の企業から先に内定が出た場合、その企業への入社を決めて自社の選考を辞退することがあります。特に応募者が第一志望としている企業から内定が出た場合や、同程度の志望度を持つ企業から、より魅力的な条件を連絡された場合、応募者は他の選考をキャンセルする傾向にあります。これは採用活動において避けられない側面であり、他社からの内定によって選考を辞退するケースは多々見受けられます。中には、内定辞退の連絡をせずに面接に来ないといったケースも考えられるでしょう。
面接当日の詳細がわからず不安を感じている
面接当日の具体的な流れや、面接官の情報、企業までのアクセス方法などが不明瞭だと、応募者は不安を感じてしまいます。特に初めての場所やオンライン面接の場合、当日のイメージが掴めないと、体調不良や道に迷うなどの不測の事態に備えられず、結果として面接をキャンセルしてしまうことがあります。応募者は面接に向けて準備をしていますが、詳細な連絡がないことで「きちんと面接にたどり着けるだろうか」「どんな人が面接官なのだろう」といった不安が増し、面接へのモチベーションが低下する可能性があります。
面接のドタキャンを防ぐ!明日からできる具体的な対策8選
面接のドタキャンや無断欠席は、企業にとって大きな損失です。
ここでは、面接辞退を未然に防ぎ、応募者の来社率を高めるための具体的な対策を8つご紹介します。
また、面接候補日を複数提示することで、応募者が自身のスケジュールに合わせて選択しやすくなり、日程調整の手間を減らすことができます。一方的に日時を提示すると、応募者に高圧的な印象を与えかねず、提示された日程が合わなければ面接辞退につながるリスクもあります。柔軟な対応が面接実施の対策として重要であり、応募者の都合を考慮した日程調整は、面接への参加意欲を高めることに繋がります。
例えば、応募から1営業日以内のメールでの返信を徹底し、面接候補日を複数提示することで、応募者のスケジュール調整の負担を軽減できます。また、電話対応の際の話し方や、受付の対応を定期的に確認し、改善点があれば見直すことも大切です。
こうしたきめ細やかな対策は、応募者の企業に対する信頼感を高め、結果として面接辞退を防ぐ効果が期待できます。さらに、緊急連絡先を事前にメールで共有しておくことで、万が一の事態にも応募者が安心して連絡できるようになります。
ただし、過度な連絡は応募者に煩わしさを感じさせる可能性もあるため、面接日の前日や3日前など、適切な間隔で送付することが重要です。この連絡は、企業が応募者を大切にしているというメッセージにもなり、応募者の企業に対する安心感を高める対策にもなります。
例えば、応募者が志望する部署の責任者が面接官を務める場合、応募者はその部署に関連する質問をより深く準備できるでしょう。また、面接官の情報が事前に提供されることで、応募者は面接当日の緊張を和らげ、本来の力を発揮しやすくなります。見知らぬ人物と話すよりも、事前に情報があることで心理的なハードルが下がり、安心して面接に臨めるためです。
これは、応募者目線に立った細やかな配慮であり、企業への信頼感を高めることにも貢献します。面接官の氏名だけでなく、簡単な役職や担当部署なども併せて伝えることで、応募者は面接の目的や内容をより深く理解し、適切な準備を進めることができるでしょう。
ここでは、面接辞退を未然に防ぎ、応募者の来社率を高めるための具体的な対策を8つご紹介します。
応募から1営業日以内に連絡し、面接候補日を複数提示する
応募者の入社意欲が最も高まるのは、応募直後のタイミングです。この熱意が冷めないうちに面接設定へと繋げるため、応募から1営業日以内に連絡することを心がけましょう。連絡が遅れると、応募者は他社の選考を優先したり、入社意欲を失ってしまったりする可能性があります。迅速な連絡は、応募者に対する企業の誠意を示す重要な対策の一つです。また、面接候補日を複数提示することで、応募者が自身のスケジュールに合わせて選択しやすくなり、日程調整の手間を減らすことができます。一方的に日時を提示すると、応募者に高圧的な印象を与えかねず、提示された日程が合わなければ面接辞退につながるリスクもあります。柔軟な対応が面接実施の対策として重要であり、応募者の都合を考慮した日程調整は、面接への参加意欲を高めることに繋がります。
応募者の立場に立った丁寧なメール・電話対応を徹底する
応募者とのやり取りは、企業の印象を決定づける重要な要素です。特に、顔が見えない電話やメールでの連絡は、より丁寧な対応が求められます。迅速かつ誠実な言葉遣いを心がけ、応募者が安心してやり取りできる環境を整えることが、面接辞退を防ぐための重要な対策となります。例えば、応募から1営業日以内のメールでの返信を徹底し、面接候補日を複数提示することで、応募者のスケジュール調整の負担を軽減できます。また、電話対応の際の話し方や、受付の対応を定期的に確認し、改善点があれば見直すことも大切です。
こうしたきめ細やかな対策は、応募者の企業に対する信頼感を高め、結果として面接辞退を防ぐ効果が期待できます。さらに、緊急連絡先を事前にメールで共有しておくことで、万が一の事態にも応募者が安心して連絡できるようになります。
面接の前日にはリマインドメールやSMSで再度案内を送る
面接の前日にリマインドメールやSMSを送ることは、応募者が面接日を忘れることを防ぐ上で非常に有効な対策です。特に、複数企業に応募している応募者は多忙な場合が多く、面接日が近づくと他の予定に埋もれてしまうこともありますので、リマインドの連絡は重要です。リマインドメールやSMSには、面接日時、場所(オンライン面接の場合はURL)、持ち物、緊急連絡先などを具体的に記載し、応募者に再度確認を促しましょう。これにより、応募者の面接に対する意識を高め、ドタキャンを防ぐことに繋がります。ただし、過度な連絡は応募者に煩わしさを感じさせる可能性もあるため、面接日の前日や3日前など、適切な間隔で送付することが重要です。この連絡は、企業が応募者を大切にしているというメッセージにもなり、応募者の企業に対する安心感を高める対策にもなります。
面接官の氏名や役職を事前に共有して安心感を与える
面接官の氏名や役職を事前に共有することは、応募者の不安を軽減し、面接への安心感を高めるための効果的な対策です。誰が面接官を務めるのかが事前に分かれば、応募者は面接の具体的なイメージを掴みやすくなり、面接官のバックグラウンドや専門分野を考慮した上で、より的を絞った対策を立てることが可能になります。例えば、応募者が志望する部署の責任者が面接官を務める場合、応募者はその部署に関連する質問をより深く準備できるでしょう。また、面接官の情報が事前に提供されることで、応募者は面接当日の緊張を和らげ、本来の力を発揮しやすくなります。見知らぬ人物と話すよりも、事前に情報があることで心理的なハードルが下がり、安心して面接に臨めるためです。
これは、応募者目線に立った細やかな配慮であり、企業への信頼感を高めることにも貢献します。面接官の氏名だけでなく、簡単な役職や担当部署なども併せて伝えることで、応募者は面接の目的や内容をより深く理解し、適切な準備を進めることができるでしょう。

「カジュアル面談」を行い心理的ハードルを下げる
「面接」という言葉は、応募者にとって堅苦しく、緊張を伴うものだと捉えられがちです。この心理的なハードルを下げ、より気軽に企業と接触できる機会を提供するための対策として、「カジュアル面談」を面接の前に実施する方法があります。カジュアル面談は、選考の一環ではなく、企業説明や質疑応答を中心とした情報交換の場として位置づけることで、応募者は「お互いのことを知る場」として捉え、リラックスして参加しやすくなります。このアプローチは、特に「とりあえず応募した」という段階の応募者や、転職活動に不慣れな層に対して有効です。選考書類の提出が不要な場合が多く、服装も「普段着で構いません」と伝えることで、さらに心理的な負担を軽減できます。これにより、応募者は企業の雰囲気や働き方をより深く理解し、その後の選考への動機付けを効果的に行うことが可能です。
結果として、応募者の志望度が向上し、最終的な応募や内定につながる可能性を高めることにも貢献します。この対策は、応募者数を増やすだけでなく、ミスマッチの少ない採用にも繋がる重要な一歩と言えるでしょう。
オンライン面接を導入して応募者の時間的・場所的負担を減らす
オンライン面接の導入は、応募者の時間的・場所的負担を大幅に軽減する有効な対策です。遠方に住む応募者や、現職で忙しい応募者にとって、来社にかかる時間や交通費は大きな負担となる場合があります。オンライン面接であれば、自宅や都合の良い場所から面接を受けることができるため、応募のハードルが下がり、応募者層の拡大や応募者数の増加が期待できます。実際に、Web面接を導入している企業の約6割が、導入後に応募者数が増加したと回答しています。特に、交通費の負担がなくなることで、これまで応募を諦めていた遠方からの優秀な人材にもアプローチできるようになるのです。
また、オンライン面接は急なスケジュール変更にも柔軟に対応できる点もメリットです。例えば、応募者が急な出張や体調不良に見舞われた場合でも、日程調整がしやすくなり、面接をキャンセルせずに済む可能性が高まります。
適切なオンライン会議ツールの選定と、操作方法の事前案内を丁寧に行うことで、スムーズな面接実施が可能です。例えば、事前に接続テストを促したり、トラブル時の連絡先を明記したりするなどの対策が有効です。これにより、応募者の心理的な負担も軽減され、面接への参加意欲を高めることにも繋がります。
面接で聞く質問の一部をあらかじめ伝えておく
面接で聞かれる質問の一部を事前に伝えておくことも、応募者の不安を軽減し、面接への参加率を高める有効な対策です。応募者は、面接で何を話せば良いのか、どのような準備が必要なのかという不安を抱えていることがあります。質問の一部を事前に共有することで、応募者は回答を準備する時間を十分に確保でき、自信を持って面接に臨むことができます。これにより、面接当日の緊張が和らぎ、応募者が本来の力を発揮しやすくなる効果が期待できます。
例えば、「自己紹介」「志望動機」「入社後に貢献したいこと」といった基本的な質問だけでなく、業務内容に関連する質問や、応募者の強みや弱みに関する質問など、いくつか具体的な質問例を提示すると良いでしょう。これにより、応募者は漠然とした不安から解放され、面接に集中できるようになります。また、事前に質問を伝えることで、応募者が企業文化や求める人物像をより深く理解し、それに合わせた回答を準備できるため、ミスマッチの防止にも繋がります。
この対策は、企業側にもメリットがあります。事前に質問を伝えることで、面接官は応募者がどのような準備をしてくるか予測しやすくなり、面接の質を高めることができます。応募者が十分に準備をして臨むことで、面接官も応募者の潜在能力や適性をより正確に評価できるようになるのです。これは、応募者にとっても企業にとっても有益な対策と言えます。
求人票や自社サイトで職場の雰囲気を公開し、働くイメージを持たせる
求人票や自社サイトで職場の雰囲気や働く環境を具体的に公開することは、応募者が入社後のイメージを明確にする上で重要な対策です。文字情報だけでなく、写真や動画を活用して社内の様子、社員の働く姿、休憩スペースなどを紹介することで、応募者はよりリアルなイメージを抱くことができます。これにより、「入社してみたら思っていたのと違った」というミスマッチを防ぎ、入社後の定着率向上にも繋がります。働くイメージが具体的に持てることで、応募者の面接へのモチベーションも高まるでしょう。
例えば、社員インタビューや一日の業務の流れを動画で公開することで、実際に働く社員の生の声や、具体的な仕事内容が伝わりやすくなります。これにより、応募者は自分自身がその職場で働く姿を具体的に想像できるようになり、企業への興味や志望度が深まることが期待できます。
もし応募者が面接に来なかった場合の対処法
応募者が面接に来なかった場合、まずは電話で状況を確認することが重要です。事故や体調不良など、やむを得ない事情で面接に来られなかった可能性も考えられるため、応募者の安否確認も兼ねて、面接に来られなかった理由を簡潔に尋ねましょう。この際、応募者の入社意欲がある場合は、再度日程調整の機会を設けることも検討する必要があります。
この際、応募者の入社意欲がある場合は、再度日程調整の機会を設けることも検討しましょう。例えば、体調不良で電話に出られなかったが、回復次第面接を受けたいという意思がある場合、改めて日程を調整することで、優秀な人材との縁を繋ぐことができます。特に、緊急連絡先として携帯電話番号だけでなく、メールアドレスも事前に確認しておくことで、電話がつながらない場合の代替手段を確保できます。
応募者が電話に出ない場合でも、一方的に選考を終了するのではなく、まずは状況確認の連絡を試みることが重要です。これにより、企業としての誠実な対応を示すことができ、応募者にとっても企業への印象が悪化することを防げます。連絡が取れない場合でも、なぜ来なかったのかを推測するだけでなく、直接確認する姿勢が、今後の採用活動の改善にも繋がるでしょう。
メールを送ることで、応募者が電話に出られなかった理由が何であれ、企業側が状況を気にかけていることを伝えられます。また、連絡が来なかったとしても、企業としての丁寧な対応を示すことができます。複数回の連絡で返信がなければ、その時点で選考を終了と判断しても問題ありません。しかし、一方的に選考を終了するのではなく、まずはメールでの確認を試みることが、企業イメージの維持にも繋がります。
例えば、応募者からの応募日、面接設定の連絡日時、応募者からの返信日時、面接日、そして無断キャンセルに至った日時などを時系列で詳細に記録することが重要です。この記録は、今後の採用活動の改善に役立つだけでなく、万が一トラブルが発生した場合の証拠にもなります。
応募者は将来的に自社の顧客となる可能性もあるため、たとえ無断キャンセルであっても、無下に扱うべきではありません。不採用とする場合でも、丁寧な不採用通知を送るなど、社会人としてのマナーを守った対応を心がけましょう。このような客観的な記録と、冷静で丁寧な対応は、企業のブランドイメージ維持にも繋がります。
まずは電話で状況を確認し、来られない理由を聞く
応募者が面接に来なかった場合、まずは電話で状況を確認しましょう。事故や体調不良など、やむを得ない事情で面接に来られなかった可能性も考えられます。電話がつながったら、応募者の氏名と面接予定日を伝え、面接に来られなかった理由を簡潔に尋ねます。無理に詳しく聞き出す必要はありませんが、状況を把握し、応募者の安否を確認する意味でも連絡は大切です。この際、応募者の入社意欲がある場合は、再度日程調整の機会を設けることも検討しましょう。例えば、体調不良で電話に出られなかったが、回復次第面接を受けたいという意思がある場合、改めて日程を調整することで、優秀な人材との縁を繋ぐことができます。特に、緊急連絡先として携帯電話番号だけでなく、メールアドレスも事前に確認しておくことで、電話がつながらない場合の代替手段を確保できます。
応募者が電話に出ない場合でも、一方的に選考を終了するのではなく、まずは状況確認の連絡を試みることが重要です。これにより、企業としての誠実な対応を示すことができ、応募者にとっても企業への印象が悪化することを防げます。連絡が取れない場合でも、なぜ来なかったのかを推測するだけでなく、直接確認する姿勢が、今後の採用活動の改善にも繋がるでしょう。
電話がつながらなければ、再調整の意思があるかメールで確認する
電話での確認を試みても応募者と連絡が取れない場合は、メールで再調整の意思があるかを確認することが重要です。この際、なぜ面接に来なかったのかを責めるような内容ではなく、体調不良や急用など、何かあったのかを心配する姿勢でメールを送りましょう。そして、もし再調整の意思がある場合は、その旨を返信してほしいと伝えてください。メールを送ることで、応募者が電話に出られなかった理由が何であれ、企業側が状況を気にかけていることを伝えられます。また、連絡が来なかったとしても、企業としての丁寧な対応を示すことができます。複数回の連絡で返信がなければ、その時点で選考を終了と判断しても問題ありません。しかし、一方的に選考を終了するのではなく、まずはメールでの確認を試みることが、企業イメージの維持にも繋がります。
無断キャンセルでも感情的にならず、冷静に事実を記録する
応募者が無断キャンセルした場合でも、採用担当者は感情的にならず、冷静に対応することが求められます。面接に来なかった事実と、それまでの連絡履歴を正確に記録しておきましょう。例えば、応募者からの応募日、面接設定の連絡日時、応募者からの返信日時、面接日、そして無断キャンセルに至った日時などを時系列で詳細に記録することが重要です。この記録は、今後の採用活動の改善に役立つだけでなく、万が一トラブルが発生した場合の証拠にもなります。
応募者は将来的に自社の顧客となる可能性もあるため、たとえ無断キャンセルであっても、無下に扱うべきではありません。不採用とする場合でも、丁寧な不採用通知を送るなど、社会人としてのマナーを守った対応を心がけましょう。このような客観的な記録と、冷静で丁寧な対応は、企業のブランドイメージ維持にも繋がります。
まとめ
採用面接に来なかった応募者がいる場合、その背景にはさまざまな理由が考えられます。企業側が適切な対策を講じることで、面接への参加率を高め、優秀な人材の獲得につなげることが可能です。
面接に来なかった応募者に対しては、まず電話で状況を確認し、つながらなければメールで再調整の意思があるかを確認することが重要です。この際、感情的にならず、冷静に事実を記録しておくことが、今後の採用活動の改善に役立ちます。
しかし、そもそも採用面接に来なかったということは、残念ながら不採用の可能性が高いと考えられます。応募者の選考辞退や無断欠席を防ぐためには、応募後の迅速な連絡や、カジュアル面談の導入、オンライン面接の活用など、応募者目線に立ったきめ細やかな対策が求められます。これらの対策は、応募者の不安を軽減し、面接への参加意欲を高めるだけでなく、企業への信頼感を醸成することにもつながります。
面接に来なかった応募者に対しては、まず電話で状況を確認し、つながらなければメールで再調整の意思があるかを確認することが重要です。この際、感情的にならず、冷静に事実を記録しておくことが、今後の採用活動の改善に役立ちます。
しかし、そもそも採用面接に来なかったということは、残念ながら不採用の可能性が高いと考えられます。応募者の選考辞退や無断欠席を防ぐためには、応募後の迅速な連絡や、カジュアル面談の導入、オンライン面接の活用など、応募者目線に立ったきめ細やかな対策が求められます。これらの対策は、応募者の不安を軽減し、面接への参加意欲を高めるだけでなく、企業への信頼感を醸成することにもつながります。
ご不明点はお気軽にお問い合わせください
この度はリソースクリエイションにご興味を持ってくださいまして、誠にありがとうございます。
ご不明点・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。
殿堂入り記事
オススメ記事
オススメ記事
殿堂入り記事