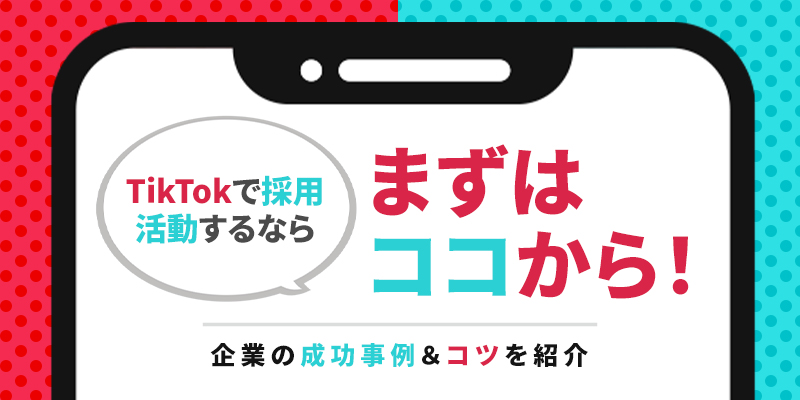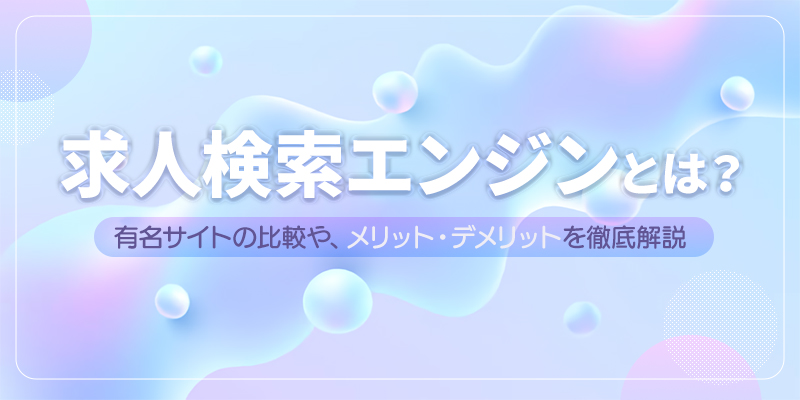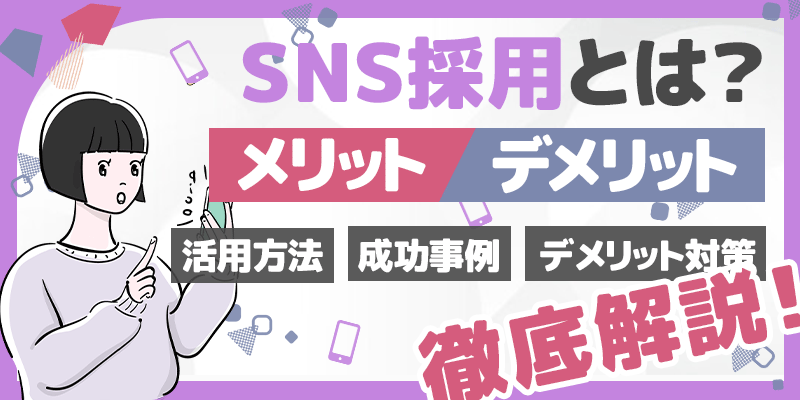採用支援
内定者懇親会の内容とは?オンライン開催のメリットや盛り上がるゲームまで紹介
更新日:2025.08.19
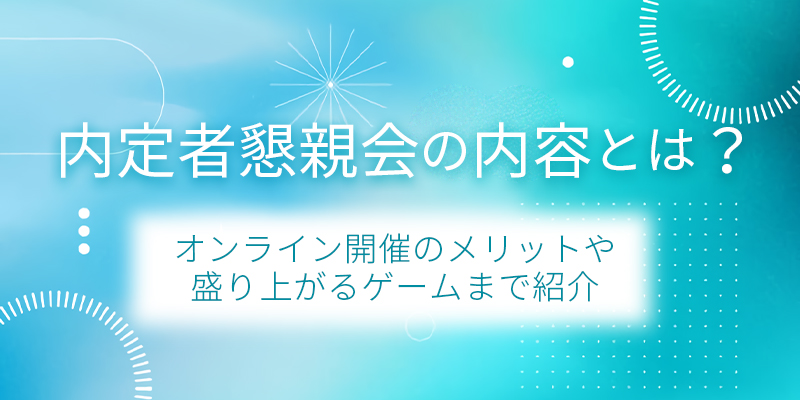
内定者懇親会は、内定者同士や内定者と社員が交流し、親睦を深めることを目的としたイベントです。
企業への理解促進や入社への不安解消、内定辞退の防止など、多くのメリットが期待できます。近年では、オンライン懇親会が普及し、場所を選ばずに参加できる利便性も高まっています。
本記事では、内定者懇親会の開催目的から具体的な進行、盛り上がるゲーム、そして成功のポイントまで、企画・運営担当者が知っておくべき内容を詳しくご紹介します。
内定者懇親会の開催目的
内定者懇親会は、企業が内定者に対して入社前の不安を解消し、入社への意欲を高めるための重要な施策です。内定者同士や社員との交流を通じて、企業文化への理解を深め、スムーズな入社をサポートすることを目的としています。
特に、近年は複数企業から内定を得る学生が多いため、内定辞退を防ぐ上で懇親会の役割は重要性を増しています。
まず、同期となる仲間と事前に顔を合わせ、自己紹介を通じて互いの人柄や背景を知ることで、入社前の不安が軽減されます。新しい環境に飛び込むことへの緊張は、見知った顔があるだけで大きく和らぐためです。
さらに、共通の話題を見つけたり、趣味や関心事を共有したりすることで、仲間意識が芽生え、入社後の人間関係がスムーズになります。内定者懇親会では、簡単なゲームやグループワークを取り入れることで、自然な形でコミュニケーションを促進し、内定者間の親睦を深めることが可能です。
また、内定者同士だけでなく、先輩社員との交流も図ることで、職場の雰囲気や実際の働き方を肌で感じることができ、入社後のギャップを減らすことにも寄与します。
結果として、内定辞退や入社後の早期離職の防止にも繋がり、内定者が安心して会社生活をスタートできる環境を整えることができます。
内定辞退の防止については、こちらの記事も参考になります。
特に、近年は複数企業から内定を得る学生が多いため、内定辞退を防ぐ上で懇親会の役割は重要性を増しています。
内定者懇親会を行うメリット
入社前に懇親会を通して内定者同士がコミュニケーションを図ることは、内定者にとっても、企業にとって多くのメリットをもたらします。まず、同期となる仲間と事前に顔を合わせ、自己紹介を通じて互いの人柄や背景を知ることで、入社前の不安が軽減されます。新しい環境に飛び込むことへの緊張は、見知った顔があるだけで大きく和らぐためです。
さらに、共通の話題を見つけたり、趣味や関心事を共有したりすることで、仲間意識が芽生え、入社後の人間関係がスムーズになります。内定者懇親会では、簡単なゲームやグループワークを取り入れることで、自然な形でコミュニケーションを促進し、内定者間の親睦を深めることが可能です。
また、内定者同士だけでなく、先輩社員との交流も図ることで、職場の雰囲気や実際の働き方を肌で感じることができ、入社後のギャップを減らすことにも寄与します。
結果として、内定辞退や入社後の早期離職の防止にも繋がり、内定者が安心して会社生活をスタートできる環境を整えることができます。
内定辞退の防止については、こちらの記事も参考になります。
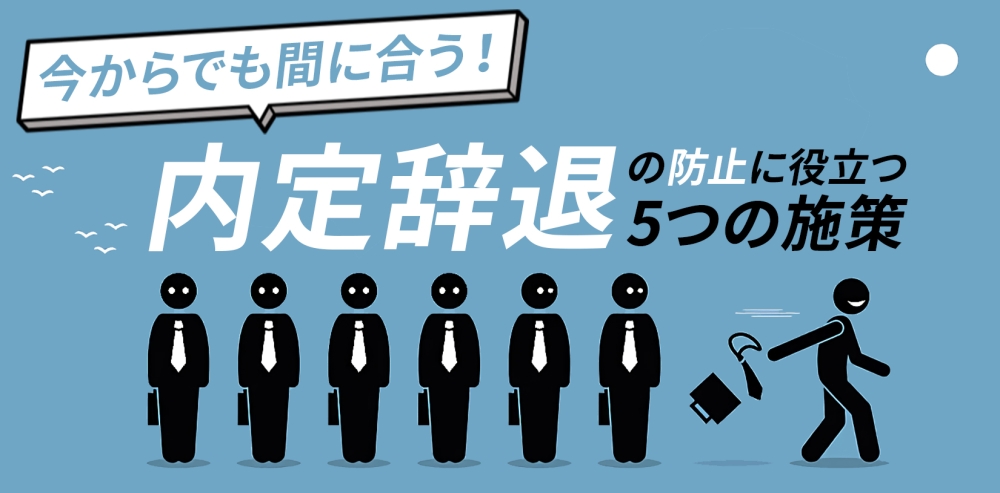
内定者懇親会の基本的な進行
内定者懇親会の基本的な進行は、内定者の緊張を和らげ、自然な交流を促すための構成が重要です。
一般的には、会社からの挨拶と説明から始まり、参加者の自己紹介、アイスブレイク、自由な交流時間、そして社員への質問機会の提供といった内容で進められます。これらの要素をバランス良く組み合わせることで、内定者が企業や他の内定者、社員との関係をスムーズに築けるようサポートします。
まずは、採用担当者や経営層からの歓迎の言葉で内定者を温かく迎え入れ、入社への期待を伝えることから始めましょう。この際、内定者に対して感謝の気持ちを示すとともに、今後の期待を具体的に伝えることで、彼らのモチベーション向上に繋がります。
次に、会社のビジョン、事業内容、企業文化、そして今後の展望について簡潔に説明します。一方的な情報提供にならないよう、内定者が興味を持ちやすい内容にしたり、動画やスライドを効果的に活用したりする工夫が求められます。特に、会社の雰囲気や社員の働き方など、入社後に直結する情報に触れることで、内定者の会社理解を深められます。
また、懇親会の目的や当日のプログラム、タイムスケジュールを明確に提示し、内定者が安心して参加できるよう配慮することも大切です。これにより、内定者は懇親会全体の内容を把握し、スムーズに各プログラムへ移行できます。
この最初の挨拶と説明は、内定者が企業に対して抱く第一印象を左右する重要な要素となるため、丁寧かつ魅力的に行うことが成功の鍵となります。
例えば、「最近あった良いこと(Good&New)」を共有したり、「自分を漢字一文字で表すと」といったテーマを設定したりすることで、一般的な自己紹介よりもユニークで記憶に残る内容にすることができます。これにより、内定者同士が共通の話題を見つけやすくなり、その後のフリートークへと繋がりやすくなります。
また、自己紹介の際には、オンラインであればブレイクアウトルーム機能を活用して少人数のグループに分け、より話しやすい雰囲気を作ることも有効です。社員も自己紹介に参加することで、内定者との距離を縮め、親近感を持ってもらえるように努めましょう。
自己紹介は、内定者が安心して交流できる場の基礎を築くための大切な時間であり、その後の懇親会全体の盛り上がりを左右する要素となります。
特に初対面の内定者同士や、社員との交流が初めての場合、硬い雰囲気になりがちですが、簡単なゲームやレクリエーションを取り入れることで、自然な笑顔と会話が生まれます。
アイスブレイクの企画としては、チーム対抗で楽しめる「共通点探しゲーム」や、絵を使って言葉を伝える「絵しりとり」などが挙げられます。これらのゲームは、参加者が協力したり、互いの意外な一面を発見したりするきっかけとなり、親近感を抱きやすくなります。
オンラインで開催する場合は、Zoomなどのツールのブレイクアウトルーム機能を活用し、少人数グループでのゲームを取り入れることで、より活発な交流を促すことができます。
また、お題に沿ってユニークな自己紹介をしてもらうことも、アイスブレイクとして効果的です。例えば、「もしも一つだけ願いが叶うなら」といった質問をすることで、参加者の個性や価値観が垣間見え、新たな話題に繋がります。
アイスブレイクは、懇親会全体の雰囲気を決定づける重要な要素であり、参加者が心から楽しめるような工夫を凝らすことが成功への鍵となります。
例えば、共通の趣味や学生時代の経験について語り合ったり、入社後の具体的な業務内容や職場の雰囲気に関する疑問を社員に直接質問したりする場として活用できます。オンライン開催の場合でも、ブレイクアウトルーム機能を活用して少人数のグループに分けることで、より密な会話を促すことが可能です。
グループ分けの際には、あらかじめ似たような興味を持つ内定者同士をまとめたり、既存社員を各グループに配置して会話のきっかけを作ったりするなどの工夫も有効です。
また、飲み物や軽食を用意することで、よりリラックスした雰囲気を作り出し、会話を弾ませることができます。
この自由な交流時間は、内定者が企業文化に触れ、自分がこの会社で働くイメージを具体化するための貴重な機会となるため、活発な会話が生まれるような環境を整えることが大切です。
例えば、事前に内定者から質問を募っておき、懇親会中にパネルディスカッション形式で社員が回答する形式や、少人数のグループに分かれて座談会形式で自由に質問できる場を設けるなどが考えられます。
オンライン開催の場合は、チャット機能を使ってリアルタイムで質問を受け付けたり、ブレイクアウトルームで少人数に分かれて先輩社員と交流する時間を設けたりすると、質問がしやすくなります。
社員側は、自身の経験談や入社後の具体的なエピソードを交えながら、率直かつ具体的に回答することで、内定者の共感を呼び、安心感を与えることができます。
また、質問を通して内定者の関心や不安の傾向を把握することは、今後の内定者フォローや入社後の育成計画にも役立てることができます。
質問の時間は、内定者が主体的に企業と関わる機会となるため、積極的に質問を促し、丁寧に対応することが、内定者の入社意欲向上に繋がります。
一般的には、会社からの挨拶と説明から始まり、参加者の自己紹介、アイスブレイク、自由な交流時間、そして社員への質問機会の提供といった内容で進められます。これらの要素をバランス良く組み合わせることで、内定者が企業や他の内定者、社員との関係をスムーズに築けるようサポートします。
会社の挨拶と説明
内定者懇親会の冒頭には、会社からの挨拶と説明を丁寧に行うことが重要です。まずは、採用担当者や経営層からの歓迎の言葉で内定者を温かく迎え入れ、入社への期待を伝えることから始めましょう。この際、内定者に対して感謝の気持ちを示すとともに、今後の期待を具体的に伝えることで、彼らのモチベーション向上に繋がります。
次に、会社のビジョン、事業内容、企業文化、そして今後の展望について簡潔に説明します。一方的な情報提供にならないよう、内定者が興味を持ちやすい内容にしたり、動画やスライドを効果的に活用したりする工夫が求められます。特に、会社の雰囲気や社員の働き方など、入社後に直結する情報に触れることで、内定者の会社理解を深められます。
また、懇親会の目的や当日のプログラム、タイムスケジュールを明確に提示し、内定者が安心して参加できるよう配慮することも大切です。これにより、内定者は懇親会全体の内容を把握し、スムーズに各プログラムへ移行できます。
この最初の挨拶と説明は、内定者が企業に対して抱く第一印象を左右する重要な要素となるため、丁寧かつ魅力的に行うことが成功の鍵となります。
参加者の自己紹介
内定者懇親会における参加者の自己紹介は、初対面同士の緊張を和らげ、相互理解を深めるための重要なステップです。単に名前や出身校を述べるだけでなく、内定者がお互いの人柄や個性について知ることができるような工夫を凝らすと良いでしょう。例えば、「最近あった良いこと(Good&New)」を共有したり、「自分を漢字一文字で表すと」といったテーマを設定したりすることで、一般的な自己紹介よりもユニークで記憶に残る内容にすることができます。これにより、内定者同士が共通の話題を見つけやすくなり、その後のフリートークへと繋がりやすくなります。
また、自己紹介の際には、オンラインであればブレイクアウトルーム機能を活用して少人数のグループに分け、より話しやすい雰囲気を作ることも有効です。社員も自己紹介に参加することで、内定者との距離を縮め、親近感を持ってもらえるように努めましょう。
自己紹介は、内定者が安心して交流できる場の基礎を築くための大切な時間であり、その後の懇親会全体の盛り上がりを左右する要素となります。
アイスブレイクの実施
内定者懇親会においてアイスブレイクの実施は、参加者の緊張を和らげ、円滑なコミュニケーションを促すために不可欠です特に初対面の内定者同士や、社員との交流が初めての場合、硬い雰囲気になりがちですが、簡単なゲームやレクリエーションを取り入れることで、自然な笑顔と会話が生まれます。
アイスブレイクの企画としては、チーム対抗で楽しめる「共通点探しゲーム」や、絵を使って言葉を伝える「絵しりとり」などが挙げられます。これらのゲームは、参加者が協力したり、互いの意外な一面を発見したりするきっかけとなり、親近感を抱きやすくなります。
オンラインで開催する場合は、Zoomなどのツールのブレイクアウトルーム機能を活用し、少人数グループでのゲームを取り入れることで、より活発な交流を促すことができます。
また、お題に沿ってユニークな自己紹介をしてもらうことも、アイスブレイクとして効果的です。例えば、「もしも一つだけ願いが叶うなら」といった質問をすることで、参加者の個性や価値観が垣間見え、新たな話題に繋がります。
アイスブレイクは、懇親会全体の雰囲気を決定づける重要な要素であり、参加者が心から楽しめるような工夫を凝らすことが成功への鍵となります。
自由な交流時間の設定
内定者懇親会において自由な交流時間を設定することは、内定者同士や社員との間で自発的なコミュニケーションを促す上で非常に重要です。この時間を通じて、内定者は自己紹介やアイスブレイクで生まれた関心事を深掘りしたり、個人的な話題を共有したりすることができます。例えば、共通の趣味や学生時代の経験について語り合ったり、入社後の具体的な業務内容や職場の雰囲気に関する疑問を社員に直接質問したりする場として活用できます。オンライン開催の場合でも、ブレイクアウトルーム機能を活用して少人数のグループに分けることで、より密な会話を促すことが可能です。
グループ分けの際には、あらかじめ似たような興味を持つ内定者同士をまとめたり、既存社員を各グループに配置して会話のきっかけを作ったりするなどの工夫も有効です。
また、飲み物や軽食を用意することで、よりリラックスした雰囲気を作り出し、会話を弾ませることができます。
この自由な交流時間は、内定者が企業文化に触れ、自分がこの会社で働くイメージを具体化するための貴重な機会となるため、活発な会話が生まれるような環境を整えることが大切です。
社員への質問機会の提供
内定者懇親会において社員への質問機会を設けることは、内定者が抱える疑問や不安を解消し、企業への理解を深める上で非常に有効です。会社説明会や面接では聞きづらかったことや、実際の働き方、社風、キャリアパスなど、内定者が本当に知りたい情報を提供できる貴重な時間となります。例えば、事前に内定者から質問を募っておき、懇親会中にパネルディスカッション形式で社員が回答する形式や、少人数のグループに分かれて座談会形式で自由に質問できる場を設けるなどが考えられます。
オンライン開催の場合は、チャット機能を使ってリアルタイムで質問を受け付けたり、ブレイクアウトルームで少人数に分かれて先輩社員と交流する時間を設けたりすると、質問がしやすくなります。
社員側は、自身の経験談や入社後の具体的なエピソードを交えながら、率直かつ具体的に回答することで、内定者の共感を呼び、安心感を与えることができます。
また、質問を通して内定者の関心や不安の傾向を把握することは、今後の内定者フォローや入社後の育成計画にも役立てることができます。
質問の時間は、内定者が主体的に企業と関わる機会となるため、積極的に質問を促し、丁寧に対応することが、内定者の入社意欲向上に繋がります。

オンライン懇親会ならではのメリット
オンライン懇親会は、近年普及が進む開催形式であり、多くの企業がその利便性から導入しています。
従来の対面形式とは異なる特性を持つものの、感染症のリスクを気にせず開催できるだけでなく、場所や時間の制約を大幅に軽減できるといったメリットがあります。特に遠方に住む内定者にとって、移動にかかる時間や費用、精神的な負担を軽減できる点は大きな魅力といえるでしょう。
これらの利点を活かすことで、より多くの内定者が懇親会に参加しやすくなり、結果として内定者フォローの機会を増やすことが可能になります。
まず、会場費や飲食費、交通費、宿泊費といった物理的なコストが不要となるため、開催規模に関わらず経費を抑えることが可能です。例えば、大人数の懇親会では会場の確保やケータリングの手配に費用がかかりますが、オンラインであればこれらの費用が一切発生しません。
また、遠方に住む内定者を招待する場合、交通費や宿泊費の補助は企業にとって大きな負担となりますが、オンライン開催であればこれらの費用を考慮する必要がなくなります。さらに、イベントの準備にかかる人件費や時間も削減できるため、全体的な運営コストの抑制に貢献します。
浮いた費用を、内定者への送付品(お菓子や軽食セットなど)や、懇親会を盛り上げる企画コンテンツの充実に充てることで、参加者の満足度向上にも繋げられます。
インターネット環境とデバイスがあれば、自宅や実家、海外からでも手軽に参加できるため、地理的な制約や移動にかかる負担がなくなります。
特に、遠方に住む内定者や、留学中などの理由で対面参加が難しい内定者にとっては、この点が大きなメリットとなります。従来の対面形式では、移動時間や交通費が参加の障壁となることがありましたが、オンラインであればこれらの心配が不要となるため、より多くの内定者が気軽に参加しやすくなります。
結果として、内定者全体の参加率向上が期待でき、企業と内定者、そして内定者同士の接点を増やす機会を創出できます。
また、参加者の都合に合わせて短時間で実施することも可能なため、多忙な内定者のスケジュールにも合わせやすいという利点もあります。
従来の対面形式とは異なる特性を持つものの、感染症のリスクを気にせず開催できるだけでなく、場所や時間の制約を大幅に軽減できるといったメリットがあります。特に遠方に住む内定者にとって、移動にかかる時間や費用、精神的な負担を軽減できる点は大きな魅力といえるでしょう。
これらの利点を活かすことで、より多くの内定者が懇親会に参加しやすくなり、結果として内定者フォローの機会を増やすことが可能になります。
メリット1:開催費用の削減
オンライン懇親会は、対面での開催と比較して、費用削減が期待できます。まず、会場費や飲食費、交通費、宿泊費といった物理的なコストが不要となるため、開催規模に関わらず経費を抑えることが可能です。例えば、大人数の懇親会では会場の確保やケータリングの手配に費用がかかりますが、オンラインであればこれらの費用が一切発生しません。
また、遠方に住む内定者を招待する場合、交通費や宿泊費の補助は企業にとって大きな負担となりますが、オンライン開催であればこれらの費用を考慮する必要がなくなります。さらに、イベントの準備にかかる人件費や時間も削減できるため、全体的な運営コストの抑制に貢献します。
浮いた費用を、内定者への送付品(お菓子や軽食セットなど)や、懇親会を盛り上げる企画コンテンツの充実に充てることで、参加者の満足度向上にも繋げられます。
メリット2:場所を選ばずに参加可能
オンライン懇親会の最大の利点は、場所を選ばずに参加できることです。インターネット環境とデバイスがあれば、自宅や実家、海外からでも手軽に参加できるため、地理的な制約や移動にかかる負担がなくなります。
特に、遠方に住む内定者や、留学中などの理由で対面参加が難しい内定者にとっては、この点が大きなメリットとなります。従来の対面形式では、移動時間や交通費が参加の障壁となることがありましたが、オンラインであればこれらの心配が不要となるため、より多くの内定者が気軽に参加しやすくなります。
結果として、内定者全体の参加率向上が期待でき、企業と内定者、そして内定者同士の接点を増やす機会を創出できます。
また、参加者の都合に合わせて短時間で実施することも可能なため、多忙な内定者のスケジュールにも合わせやすいという利点もあります。
懇親会を盛り上げる企画
内定者懇親会を成功させるためには、参加者が心から楽しめる企画を用意することが不可欠です。ただ集まるだけでなく、ゲームやレクリエーションを通じて自然なコミュニケーションを促し、内定者同士の絆を深めることが重要です。
対面とオンライン、それぞれの特性を活かした企画を組み合わせることで、より記憶に残る懇親会を演出できます。
ここでは、参加者の緊張をほぐし、交流を活性化させるための具体的な企画アイデアをご紹介します。
例えば、「絵しりとり」や「ジェスチャーゲーム」などが挙げられます。これらのゲームは、特別な道具や複雑なルールを必要としないため、準備も簡単で、初対面同士でもスムーズに交流を始められるというメリットがあります。
ゲームを通じて協力したり、笑い合ったりすることで、内定者間の心理的な距離が縮まり、入社後の円滑な人間関係構築に繋がるでしょう。
具体的な進行方法としては、まず司会者が最初のお題となる絵を描き、次の人がその絵の最後の部分から連想される絵を順番に描いていきます。例えば、最初の人が「りんご」の絵を描いたら、次の人は「ごりら」の絵を描くといった流れです。
オンラインで開催する場合は、ホワイトボード機能や共有画面に直接絵を描けるツールを使用するとスムーズです。
参加者は、描かれた絵を見て連想し、次に繋がる絵を考えるため、自然と集中力が高まり、他の参加者の絵にも注目するようになります。絵のクオリティは問わず、アイデアの面白さや連想のユニークさが評価されるため、絵に自信がない人でも気兼ねなく参加できます。
このゲームを通じて、参加者はお互いの意外な発想力や表現力に触れることができ、笑顔や会話が生まれやすくなります。絵を使ったしりとりは、内定者同士の共通の話題を作り、親睦を深めるための効果的なゲームといえるでしょう。
進行方法としては、まずお題(例:動物、職業、スポーツなど)を設定し、一人ずつそのお題をジェスチャーで表現します。他の参加者は、そのジェスチャーからお題を当てる形式です。オンラインで開催する際は、カメラに全身が映るように工夫したり、ジェスチャーをより大きく表現したりすることで、伝えやすくなります。
また、チーム対抗形式にすることで、より一層ゲームが盛り上がり、チームビルディングの効果も期待できます。例えば、チーム内で順番にジェスチャーをする人を決め、制限時間内にいくつの答えを導き出せるかを競い合います。言葉の壁がないため、文化的な背景が異なる内定者がいる場合でも、全員が平等に楽しむことができます。
ジェスチャーゲームを通じて、参加者は互いのユニークな表現方法に触れ、笑いや一体感が生まれるため、内定者間の緊張を和らげ、自然な形で親睦を深めることができるでしょう。
実際に同じ空間にいることで、非言語的なコミュニケーションがより豊かになり、深い人間関係の構築に繋がりやすくなります。少人数でのグループワークや、カジュアルな雰囲気での社員との交流会などは、対面だからこそ得られる一体感や臨場感を伴い、内定者の満足度を高めることができます。
数人から成る小さなグループに分かれることで、一人ひとりが発言しやすくなり、議論に積極的に参加する機会が増えます。
例えば、企業に関連する簡単なケーススタディや、特定のテーマ(例:入社後に挑戦したいこと、理想の働き方など)についてディスカッションを行うことで、内定者は互いの価値観や考え方を深く理解できます。ワークを通じて協力し、一つのアウトプットを出す過程で、自然とチームワークが生まれ、連帯感が醸成されます。
また、グループに先輩社員を配置することで、内定者はより実践的な視点やアドバイスを得ることができ、企業文化への理解を深めることができます。
社員は、内定者の個性や潜在能力を把握する良い機会にもなります。グループワークの成果を発表する時間を設けることで、他のグループの意見にも触れることができ、多様な視点から学びを得られます。
少人数でのグループワークは、内定者が安心して自分を表現できる場を提供し、入社後の業務におけるチーム連携の基礎を築くための大切なステップとなるでしょう。
堅苦しい場ではなく、リラックスした雰囲気の中で社員と内定者が自由に会話することで、内定者は企業文化や社員の人柄をより深く理解できます。
例えば、立食形式の食事会や、軽食を囲んでの歓談は、自然な話題の流れを作り出し、内定者が気軽に質問できる環境を整えます。社員は、自身の仕事内容やキャリアパス、入社後の生活などについて具体的な話を提供することで、内定者の不安を解消し、入社への期待感を高めることができます。
この際、内定者が特定の社員に話しかけやすいように、社員の部署や担当業務を明示したり、名札に趣味の話題を記載したりするなどの工夫も有効です。
また、話題が途切れないよう、事前にいくつか質問のテーマを用意しておくと良いでしょう。社員との交流は、内定者が企業への信頼感を深め、入社後のミスマッチを防ぐ上で不可欠な要素となります。
カジュアルな交流会を通じて、内定者は「この会社で働きたい」という気持ちをさらに強く抱くことができるでしょう。
ここでは、オンライン開催だからこそできる、内定者間の交流を深め、満足度を高めるための企画アイデアをご紹介します。
全体での質疑応答では質問しにくい内容も、少人数のグループであれば、内定者は気軽に質問を投げかけることができます。
オンライン会議ツールのブレイクアウトルーム機能を活用し、数名の内定者と一人の先輩社員でグループを作り、フランクな雰囲気で会話できる場を設けるのが効果的です。この際、事前に内定者から質問したい内容を募っておき、それを参考に各グループでの話題を振り分けることで、より有意義な時間となるでしょう。
先輩社員は、自身の業務内容、一日のスケジュール、入社後のキャリアパス、社内の雰囲気など、内定者が知りたいリアルな情報を提供することで、彼らの入社への不安を軽減し、期待感を高めることができます。また、内定者側も、同じような質問や悩みを持つ同期の存在を知り、共感を深めるきっかけにもなります。
この少人数懇談は、内定者が企業への理解を深め、入社後の具体的なイメージを掴むための重要な機会となり、入社意欲の向上に直結します。
参加者全員が気軽に楽しめる定番ゲームでありながら、オンラインツールを活用することで、場所を選ばずに一体感を醸成できます。通常の数字ビンゴだけでなく、内定者のプロフィールに関連する項目(例:「海外旅行に行ったことがある人」「〇〇大学出身者」「趣味が読書の人」など)をビンゴカードのマス目に記載することで、参加者同士が互いのパーソナルな情報を知り、交流を深めるきっかけとなります。
進行役は、オンラインでビンゴカードを配布し、抽選ツールを使って番号やプロフィール項目を発表します。ビンゴになった参加者には、企業に関連する景品や、オンラインで送れるギフトカードなどを贈呈すると、さらに盛り上がります。
オンライン懇親会では、会話が生まれにくいという課題がありますが、ビンゴ大会のようなゲーム性のある企画を取り入れることで、自然なコミュニケーションが促進されます。また、チーム対抗形式にして、チーム内で協力してビンゴを目指す形にすると、内定者同士の絆を深める効果も期待できるでしょう。
オンラインビンゴ大会は、手軽に実施でき、参加者全員が楽しめるため、オンライン懇親会の定番企画としておすすめです。
対面とオンライン、それぞれの特性を活かした企画を組み合わせることで、より記憶に残る懇親会を演出できます。
ここでは、参加者の緊張をほぐし、交流を活性化させるための具体的な企画アイデアをご紹介します。
対面・オンライン共通のゲーム
対面でもオンラインでも楽しめるゲームを取り入れることは、内定者懇親会を盛り上げ、参加者間の交流を促進する上で非常に効果的です。例えば、「絵しりとり」や「ジェスチャーゲーム」などが挙げられます。これらのゲームは、特別な道具や複雑なルールを必要としないため、準備も簡単で、初対面同士でもスムーズに交流を始められるというメリットがあります。
ゲームを通じて協力したり、笑い合ったりすることで、内定者間の心理的な距離が縮まり、入社後の円滑な人間関係構築に繋がるでしょう。
絵を使ったしりとり
絵を使ったしりとりは、内定者懇親会で緊張をほぐし、参加者間のコミュニケーションを促進するのに最適なゲームの一つです。このゲームの魅力は、言葉ではなく絵で表現することで、参加者の創造性を刺激し、ユーモアを交えながら楽しめる点にあります。具体的な進行方法としては、まず司会者が最初のお題となる絵を描き、次の人がその絵の最後の部分から連想される絵を順番に描いていきます。例えば、最初の人が「りんご」の絵を描いたら、次の人は「ごりら」の絵を描くといった流れです。
オンラインで開催する場合は、ホワイトボード機能や共有画面に直接絵を描けるツールを使用するとスムーズです。
参加者は、描かれた絵を見て連想し、次に繋がる絵を考えるため、自然と集中力が高まり、他の参加者の絵にも注目するようになります。絵のクオリティは問わず、アイデアの面白さや連想のユニークさが評価されるため、絵に自信がない人でも気兼ねなく参加できます。
このゲームを通じて、参加者はお互いの意外な発想力や表現力に触れることができ、笑顔や会話が生まれやすくなります。絵を使ったしりとりは、内定者同士の共通の話題を作り、親睦を深めるための効果的なゲームといえるでしょう。
ジェスチャーでの意思疎通ゲーム
ジェスチャーでの意思疎通ゲームは、内定者懇親会において言葉を使わずに身体表現だけで意思を伝えるユニークなゲームです。このゲームは、参加者の表現力や観察力を養い、チーム内での非言語コミュニケーション能力を高める効果が期待できます。進行方法としては、まずお題(例:動物、職業、スポーツなど)を設定し、一人ずつそのお題をジェスチャーで表現します。他の参加者は、そのジェスチャーからお題を当てる形式です。オンラインで開催する際は、カメラに全身が映るように工夫したり、ジェスチャーをより大きく表現したりすることで、伝えやすくなります。
また、チーム対抗形式にすることで、より一層ゲームが盛り上がり、チームビルディングの効果も期待できます。例えば、チーム内で順番にジェスチャーをする人を決め、制限時間内にいくつの答えを導き出せるかを競い合います。言葉の壁がないため、文化的な背景が異なる内定者がいる場合でも、全員が平等に楽しむことができます。
ジェスチャーゲームを通じて、参加者は互いのユニークな表現方法に触れ、笑いや一体感が生まれるため、内定者間の緊張を和らげ、自然な形で親睦を深めることができるでしょう。
対面開催に適した交流方法
対面開催の内定者懇親会では、オンラインでは難しい物理的な距離感を活かした交流方法が効果的です。実際に同じ空間にいることで、非言語的なコミュニケーションがより豊かになり、深い人間関係の構築に繋がりやすくなります。少人数でのグループワークや、カジュアルな雰囲気での社員との交流会などは、対面だからこそ得られる一体感や臨場感を伴い、内定者の満足度を高めることができます。
少人数でのグループワーク
対面開催の内定者懇親会において、少人数でのグループワークは、内定者同士の密な交流を促し、協調性や課題解決能力を養う上で非常に有効な方法です。数人から成る小さなグループに分かれることで、一人ひとりが発言しやすくなり、議論に積極的に参加する機会が増えます。
例えば、企業に関連する簡単なケーススタディや、特定のテーマ(例:入社後に挑戦したいこと、理想の働き方など)についてディスカッションを行うことで、内定者は互いの価値観や考え方を深く理解できます。ワークを通じて協力し、一つのアウトプットを出す過程で、自然とチームワークが生まれ、連帯感が醸成されます。
また、グループに先輩社員を配置することで、内定者はより実践的な視点やアドバイスを得ることができ、企業文化への理解を深めることができます。
社員は、内定者の個性や潜在能力を把握する良い機会にもなります。グループワークの成果を発表する時間を設けることで、他のグループの意見にも触れることができ、多様な視点から学びを得られます。
少人数でのグループワークは、内定者が安心して自分を表現できる場を提供し、入社後の業務におけるチーム連携の基礎を築くための大切なステップとなるでしょう。
社員とのカジュアルな交流会
対面開催の内定者懇親会において、社員とのカジュアルな交流会は、内定者が会社の雰囲気を肌で感じ、入社後の人間関係を円滑にする上で非常に効果的な方法です。堅苦しい場ではなく、リラックスした雰囲気の中で社員と内定者が自由に会話することで、内定者は企業文化や社員の人柄をより深く理解できます。
例えば、立食形式の食事会や、軽食を囲んでの歓談は、自然な話題の流れを作り出し、内定者が気軽に質問できる環境を整えます。社員は、自身の仕事内容やキャリアパス、入社後の生活などについて具体的な話を提供することで、内定者の不安を解消し、入社への期待感を高めることができます。
この際、内定者が特定の社員に話しかけやすいように、社員の部署や担当業務を明示したり、名札に趣味の話題を記載したりするなどの工夫も有効です。
また、話題が途切れないよう、事前にいくつか質問のテーマを用意しておくと良いでしょう。社員との交流は、内定者が企業への信頼感を深め、入社後のミスマッチを防ぐ上で不可欠な要素となります。
カジュアルな交流会を通じて、内定者は「この会社で働きたい」という気持ちをさらに強く抱くことができるでしょう。
オンライン開催に適した企画
オンライン懇親会では、物理的な制約があるため、その特性を最大限に活かした企画が求められます。参加者が自宅からでも楽しめる工夫や、オンラインツールならではの機能を活用した企画が成功の鍵となります。ここでは、オンライン開催だからこそできる、内定者間の交流を深め、満足度を高めるための企画アイデアをご紹介します。
先輩社員との少人数懇談
オンライン開催の内定者懇親会において、先輩社員との少人数懇談は、内定者が抱える疑問や不安を解消し、より実践的な情報を得る上で非常に有効な企画です。全体での質疑応答では質問しにくい内容も、少人数のグループであれば、内定者は気軽に質問を投げかけることができます。
オンライン会議ツールのブレイクアウトルーム機能を活用し、数名の内定者と一人の先輩社員でグループを作り、フランクな雰囲気で会話できる場を設けるのが効果的です。この際、事前に内定者から質問したい内容を募っておき、それを参考に各グループでの話題を振り分けることで、より有意義な時間となるでしょう。
先輩社員は、自身の業務内容、一日のスケジュール、入社後のキャリアパス、社内の雰囲気など、内定者が知りたいリアルな情報を提供することで、彼らの入社への不安を軽減し、期待感を高めることができます。また、内定者側も、同じような質問や悩みを持つ同期の存在を知り、共感を深めるきっかけにもなります。
この少人数懇談は、内定者が企業への理解を深め、入社後の具体的なイメージを掴むための重要な機会となり、入社意欲の向上に直結します。
オンラインでのビンゴ大会
オンライン内定者懇親会を盛り上げる企画として、オンラインでのビンゴ大会は非常に有効なゲームです。参加者全員が気軽に楽しめる定番ゲームでありながら、オンラインツールを活用することで、場所を選ばずに一体感を醸成できます。通常の数字ビンゴだけでなく、内定者のプロフィールに関連する項目(例:「海外旅行に行ったことがある人」「〇〇大学出身者」「趣味が読書の人」など)をビンゴカードのマス目に記載することで、参加者同士が互いのパーソナルな情報を知り、交流を深めるきっかけとなります。
進行役は、オンラインでビンゴカードを配布し、抽選ツールを使って番号やプロフィール項目を発表します。ビンゴになった参加者には、企業に関連する景品や、オンラインで送れるギフトカードなどを贈呈すると、さらに盛り上がります。
オンライン懇親会では、会話が生まれにくいという課題がありますが、ビンゴ大会のようなゲーム性のある企画を取り入れることで、自然なコミュニケーションが促進されます。また、チーム対抗形式にして、チーム内で協力してビンゴを目指す形にすると、内定者同士の絆を深める効果も期待できるでしょう。
オンラインビンゴ大会は、手軽に実施でき、参加者全員が楽しめるため、オンライン懇親会の定番企画としておすすめです。

懇親会を成功させるためのポイント
内定者懇親会を成功させるためには、入念な企画と準備、そして当日の円滑な運営が不可欠です。参加者の満足度を高め、内定辞退の防止や入社への意欲向上といった目的を達成するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
ここでは、懇親会を成功に導くための具体的な秘訣をご紹介します。
内定者にとって、初めて参加する会社のイベントは不安が伴うものです。そのため、開催日時、場所(オンラインの場合はURL)、プログラム内容、服装、持ち物など、懇親会に関する具体的な情報を事前に分かりやすく伝える必要があります。
特に、オンライン懇親会の場合、使用するツールの使い方や通信環境に関する注意点なども含めて案内することで、当日スムーズに進行できます。これらの情報は、メールでまとめて送付し、必要に応じてリマインドを行うと良いでしょう。
件名も「内定者懇親会のお知らせ」のように一目で内容が分かるように工夫し、内定者が見落とさないように配慮することが大切です。
また、事前に質問したい内容などをヒアリングしておくことで、当日の準備をより円滑に進められます。事前の丁寧な情報共有は、内定者の不安を軽減し、安心して懇親会に参加してもらうための第一歩であり、懇親会全体の満足度を大きく左右する重要なポイントとなります。
そこで、企画の段階から、内定者の緊張をほぐし、自然な笑顔と会話が生まれるようなレクリエーションやゲームを取り入れることを積極的に検討しましょう。
この記事でご紹介した、ユニークな自己紹介や絵しりとり、ジェスチャーゲームなどは、初対面同士でも楽しみながら交流できる人気の企画です。オンライン開催の場合、ブレイクアウトルーム機能を活用して少人数グループでの交流を促したり、オンラインビンゴ大会のような参加型のゲームを取り入れたりするのも効果的です。
また、参加者全員で楽しめるお菓子や軽食を用意したり、懇親会の途中で休憩を挟んだりするなど、リラックスできる環境づくりも大切です。
さらに、社員も積極的に交流に参加し、内定者からの質問に丁寧に答えることで、安心感を与え、親近感を持ってもらえます。
これらの工夫により、内定者は「この会社に入社して良かった」と感じ、入社への意欲がさらに高まるでしょう。
各プログラムにかける時間を明確にすることで、だらだらとした進行を防ぎ、参加者の集中力を維持できます。
例えば、会社の挨拶と説明、自己紹介、アイスブレイク、グループ交流、社員への質問時間、閉会の挨拶など、それぞれの項目に適切な時間を割り振りましょう。特に、内定者が主体的に交流する時間や質問する時間は、長めに設定することで、より深いコミュニケーションを促すことができます。
オンライン懇親会の場合、休憩時間を適切に設けることも重要です。画面越しの交流は対面よりも疲労感が大きいため、短い休憩を挟むことで、参加者の集中力を持続させることができます。
また、予期せぬトラブルや質問の延長などに対応できるよう、少し余裕を持ったタイムスケジュールを設定することも大切です。当日は、司会者がタイムキーパーとして進行を管理し、予定通りにプログラムが進んでいるかを確認しながら、必要に応じて柔軟に調整する役割を担います。
明確なタイムスケジュールは、内定者にとっても安心材料となり、懇親会全体への満足度向上に繋がるでしょう。
ここでは、懇親会を成功に導くための具体的な秘訣をご紹介します。
事前の情報共有の重要性
内定者懇親会を成功させるためには、事前の情報共有が非常に重要です。内定者にとって、初めて参加する会社のイベントは不安が伴うものです。そのため、開催日時、場所(オンラインの場合はURL)、プログラム内容、服装、持ち物など、懇親会に関する具体的な情報を事前に分かりやすく伝える必要があります。
特に、オンライン懇親会の場合、使用するツールの使い方や通信環境に関する注意点なども含めて案内することで、当日スムーズに進行できます。これらの情報は、メールでまとめて送付し、必要に応じてリマインドを行うと良いでしょう。
件名も「内定者懇親会のお知らせ」のように一目で内容が分かるように工夫し、内定者が見落とさないように配慮することが大切です。
また、事前に質問したい内容などをヒアリングしておくことで、当日の準備をより円滑に進められます。事前の丁寧な情報共有は、内定者の不安を軽減し、安心して懇親会に参加してもらうための第一歩であり、懇親会全体の満足度を大きく左右する重要なポイントとなります。
参加者が楽しめる工夫
内定者懇親会を成功させるためには、参加者が心から楽しめるような工夫を凝らすことが非常に重要です。堅苦しい雰囲気では、内定者も本音で話しにくく、交流が深まりません。そこで、企画の段階から、内定者の緊張をほぐし、自然な笑顔と会話が生まれるようなレクリエーションやゲームを取り入れることを積極的に検討しましょう。
この記事でご紹介した、ユニークな自己紹介や絵しりとり、ジェスチャーゲームなどは、初対面同士でも楽しみながら交流できる人気の企画です。オンライン開催の場合、ブレイクアウトルーム機能を活用して少人数グループでの交流を促したり、オンラインビンゴ大会のような参加型のゲームを取り入れたりするのも効果的です。
また、参加者全員で楽しめるお菓子や軽食を用意したり、懇親会の途中で休憩を挟んだりするなど、リラックスできる環境づくりも大切です。
さらに、社員も積極的に交流に参加し、内定者からの質問に丁寧に答えることで、安心感を与え、親近感を持ってもらえます。
これらの工夫により、内定者は「この会社に入社して良かった」と感じ、入社への意欲がさらに高まるでしょう。
タイムスケジュールの設定
内定者懇親会を円滑に進行させ、成功に導くためには、タイムスケジュールの綿密な設定が不可欠です。各プログラムにかける時間を明確にすることで、だらだらとした進行を防ぎ、参加者の集中力を維持できます。
例えば、会社の挨拶と説明、自己紹介、アイスブレイク、グループ交流、社員への質問時間、閉会の挨拶など、それぞれの項目に適切な時間を割り振りましょう。特に、内定者が主体的に交流する時間や質問する時間は、長めに設定することで、より深いコミュニケーションを促すことができます。
オンライン懇親会の場合、休憩時間を適切に設けることも重要です。画面越しの交流は対面よりも疲労感が大きいため、短い休憩を挟むことで、参加者の集中力を持続させることができます。
また、予期せぬトラブルや質問の延長などに対応できるよう、少し余裕を持ったタイムスケジュールを設定することも大切です。当日は、司会者がタイムキーパーとして進行を管理し、予定通りにプログラムが進んでいるかを確認しながら、必要に応じて柔軟に調整する役割を担います。
明確なタイムスケジュールは、内定者にとっても安心材料となり、懇親会全体への満足度向上に繋がるでしょう。
まとめ
内定者懇親会は、内定者と企業、そして内定者同士の絆を深めるための重要なイベントです。
オンライン開催では費用削減や場所の制約解消といったメリットがあり、対面とオンラインの特性を活かした企画が成功の鍵となります。社員との交流やゲームを通じて、入社前の不安を解消し、入社への意欲を高めることができるでしょう。
本記事でご紹介したポイントを参考に、内定者が安心して入社できるような懇親会を企画し、企業への理解促進と内定辞退の防止に繋げてください。
オンライン開催では費用削減や場所の制約解消といったメリットがあり、対面とオンラインの特性を活かした企画が成功の鍵となります。社員との交流やゲームを通じて、入社前の不安を解消し、入社への意欲を高めることができるでしょう。
本記事でご紹介したポイントを参考に、内定者が安心して入社できるような懇親会を企画し、企業への理解促進と内定辞退の防止に繋げてください。
ご不明点はお気軽にお問い合わせください
この度はリソースクリエイションにご興味を持ってくださいまして、誠にありがとうございます。
ご不明点・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。
殿堂入り記事
オススメ記事
オススメ記事
殿堂入り記事