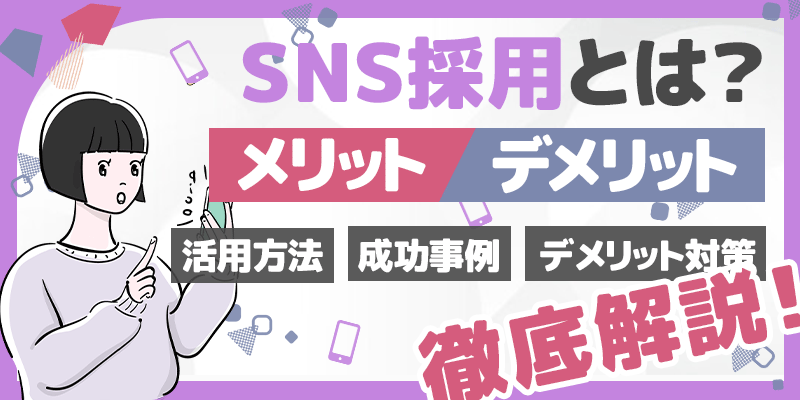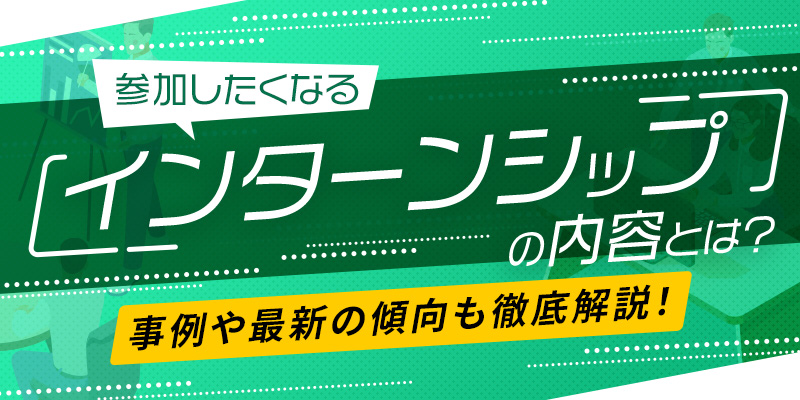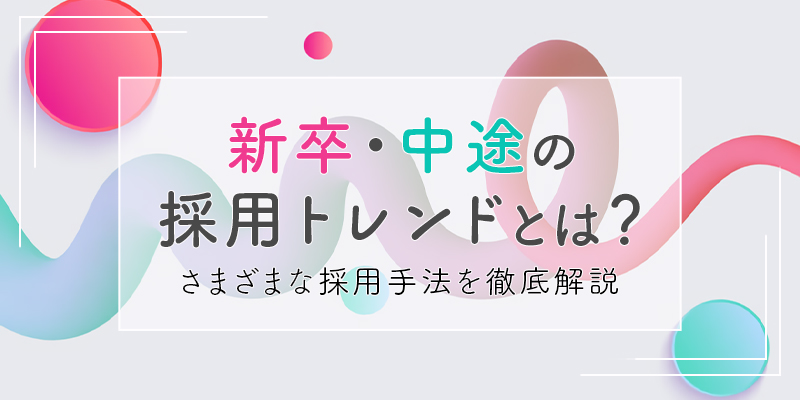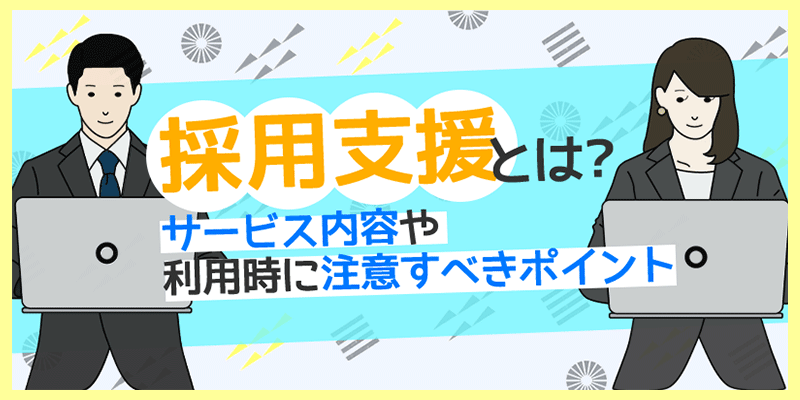採用支援
内定通知はいつ送る?内定出しのタイミングとその後のフォロー方法
更新日:2025.09.11
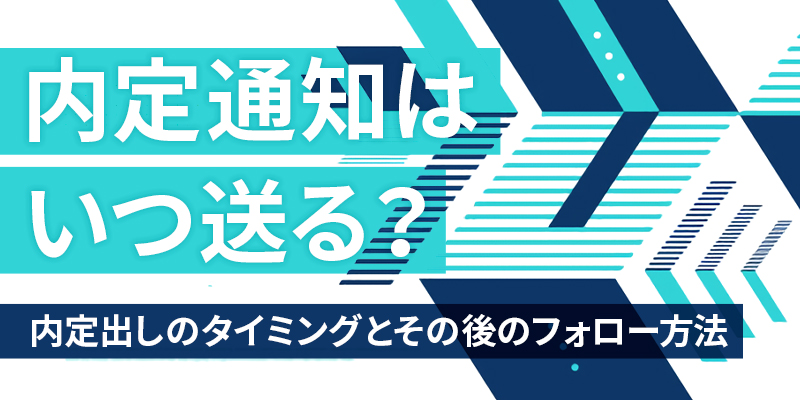
内定通知は、企業の採用活動における重要な手続きの一つです。
最終面接を終えた候補者に対し、どのタイミングで、どのような内容を伝えれば良いのか、特に経験の浅い人事担当者は迷うことが多いかもしれません。
このプロセスを適切に進めることは、優秀な人材を確保し、入社までのエンゲージメントを高める上で極めて重要です。
本記事では、内定通知を送る適切な時期から、採用通知書との違い、法的な注意点、内定辞退を防ぐためのフォロー策まで、人事担当者が知っておくべき実務知識を網羅的に解説します。
そもそも「内定」とは?人事担当者が知るべき基礎知識
採用活動において「内定」という言葉は頻繁に使われますが、その法的な意味や関連用語との違いを正確に理解しておくことは、人事担当者にとって不可欠です。
例えば、「内々定」との違いや、「採用通知書」と「内定通知書」の役割を混同してしまうと、候補者との間で認識の齟齬が生じ、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
ここでは、採用業務を円滑に進めるために、土台となる内定に関する基礎知識を整理し、それぞれの言葉が持つ意味合いと法的な位置づけを明確にします。
これは法的な拘束力を持つ労働契約の一種です。
一方「内々定」は主に新卒採用において政府が要請する正式な内定解禁日より前に企業が学生に対して「内定を出す予定である」という意向を口頭などで伝える非公式な約束です。
内々定の段階では労働契約は成立しておらず法的な拘束力は内定に比べて弱いとされています。
企業は法的な位置づけの違いを正しく認識し候補者に対して誤解を与えないよう慎重にコミュニケーションを取る必要があります。
採用通知書は、選考の結果、採用が決定したことを速報的に伝えるための書類です。
これに対して内定通知書は、採用の決定を伝えるとともに、労働契約の申し込みを行う正式な文書としての意味合いが強くなります。
ただし、実務上はこれらの役割を一つにまとめ、「内定通知書」として送付する企業がほとんどです。
この場合、内定通知書が採用決定の通知と労働契約の申し込みを兼ねることになります。
重要なのは、その書類が労働契約の成立を意味する正式なものであることを、企業と候補者の双方が認識することです。
例えば、「内々定」との違いや、「採用通知書」と「内定通知書」の役割を混同してしまうと、候補者との間で認識の齟齬が生じ、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
ここでは、採用業務を円滑に進めるために、土台となる内定に関する基礎知識を整理し、それぞれの言葉が持つ意味合いと法的な位置づけを明確にします。
「内定」と「内々定」の法的な位置づけの違い
「内定」とは企業が候補者に対して採用の意思を正式に通知し候補者がこれを承諾した時点で成立する「始期付解約権留保付労働契約」を指します。これは法的な拘束力を持つ労働契約の一種です。
一方「内々定」は主に新卒採用において政府が要請する正式な内定解禁日より前に企業が学生に対して「内定を出す予定である」という意向を口頭などで伝える非公式な約束です。
内々定の段階では労働契約は成立しておらず法的な拘束力は内定に比べて弱いとされています。
企業は法的な位置づけの違いを正しく認識し候補者に対して誤解を与えないよう慎重にコミュニケーションを取る必要があります。
採用通知書と内定通知書の役割の違い
採用通知書と内定通知書は、厳密には役割が異なります。採用通知書は、選考の結果、採用が決定したことを速報的に伝えるための書類です。
これに対して内定通知書は、採用の決定を伝えるとともに、労働契約の申し込みを行う正式な文書としての意味合いが強くなります。
ただし、実務上はこれらの役割を一つにまとめ、「内定通知書」として送付する企業がほとんどです。
この場合、内定通知書が採用決定の通知と労働契約の申し込みを兼ねることになります。
重要なのは、その書類が労働契約の成立を意味する正式なものであることを、企業と候補者の双方が認識することです。
内定通知は最終面接後いつまでに出すのがベスト?
最終面接後の内定通知のタイミングは、候補者の入社意欲に大きく影響します。
通知が遅いと、候補者は「不合格だったのではないか」と不安になったり、先に内定を出してくれた他社への入社を決めてしまったりする可能性が高まります。
優秀な人材ほど複数の企業から内定を得ているケースが多いため、選考プロセスにおけるスピード感は、採用競争力を左右する重要な要素です。
ここでは、候補者の心理や他社の動向を踏まえ、内定通知を出す最適な時期と、万が一遅れる場合の対応について解説します。
多くの候補者は複数の企業の選考を同時に進めており、長期間待たされると企業への志望度が低下したり、他社からの内定を承諾してしまったりするリスクが高まります。
特に新卒採用の場合、例えば大学4年生の5月頃から選考が活発化し、6月以降は他社からも続々と内定が出始めるため、迅速な通知が他社との差別化につながります。
社内での承認プロセスなどに時間がかかる場合でも、候補者を不安にさせないよう、スピーディーな連絡を心がけるべきです。
結果を早く伝えることは、候補者への配慮を示す誠実な姿勢ともいえます。
まずは電話などで「選考に時間がかかっており申し訳ありません」と正直に伝え、いつ頃までに結果を連絡できるか具体的な目途を示します。
この一本の連絡があるだけで、候補者は「忘れられているわけではない」と安心し、誠実な企業であるという印象を持ちます。
連絡を怠ると、候補者は不信感を抱き、たとえ後から内定を出しても辞退される可能性が高まります。
通知が遅れる時こそ、丁寧なコミュニケーションで候補者との関係性を維持し、次の選考への期待感を繋ぎとめる対応が求められます。
通知が遅いと、候補者は「不合格だったのではないか」と不安になったり、先に内定を出してくれた他社への入社を決めてしまったりする可能性が高まります。
優秀な人材ほど複数の企業から内定を得ているケースが多いため、選考プロセスにおけるスピード感は、採用競争力を左右する重要な要素です。
ここでは、候補者の心理や他社の動向を踏まえ、内定通知を出す最適な時期と、万が一遅れる場合の対応について解説します。
候補者の不安を解消する「1週間以内」の通知が理想
最終面接後の内定通知は、可能な限り早く、遅くとも1週間以内に行うのが理想的です。多くの候補者は複数の企業の選考を同時に進めており、長期間待たされると企業への志望度が低下したり、他社からの内定を承諾してしまったりするリスクが高まります。
特に新卒採用の場合、例えば大学4年生の5月頃から選考が活発化し、6月以降は他社からも続々と内定が出始めるため、迅速な通知が他社との差別化につながります。
社内での承認プロセスなどに時間がかかる場合でも、候補者を不安にさせないよう、スピーディーな連絡を心がけるべきです。
結果を早く伝えることは、候補者への配慮を示す誠実な姿勢ともいえます。
通知が遅れる場合に人事が取るべき対応
社内調整や決裁者の不在といった事情で、どうしても内定通知が1週間を超えてしまう場合は、候補者に対して中間連絡を入れることが不可欠です。まずは電話などで「選考に時間がかかっており申し訳ありません」と正直に伝え、いつ頃までに結果を連絡できるか具体的な目途を示します。
この一本の連絡があるだけで、候補者は「忘れられているわけではない」と安心し、誠実な企業であるという印象を持ちます。
連絡を怠ると、候補者は不信感を抱き、たとえ後から内定を出しても辞退される可能性が高まります。
通知が遅れる時こそ、丁寧なコミュニケーションで候補者との関係性を維持し、次の選考への期待感を繋ぎとめる対応が求められます。
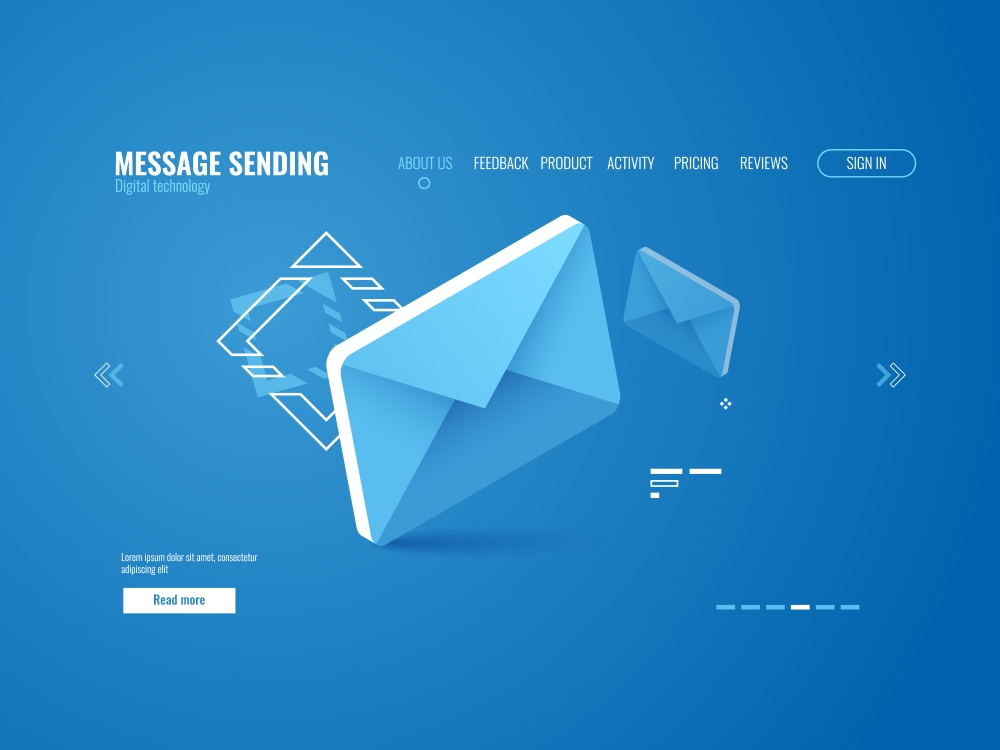
内定通知から承諾まで!人事が進めるべき3ステップ
採用を決定してから、候補者が正式に入社を承諾するまでのプロセスは、迅速かつ丁寧に進める必要があります。
この段階での対応が、候補者の入社意欲を左右し、内定辞退のリスクを低減させる鍵となります。
手続きをスムーズに進めることで、候補者に安心感を与え、企業への信頼を深めてもらうことが可能です。
ここでは、内定通知から承諾書の回収までを、具体的な3つのステップに分けて解説し、人事担当者が確実に行うべき実務の流れを整理します。
書類の送付よりも早く結果を伝えられるため、候補者の喜びや安心につながります。
連絡の際には、まず合格したことを知らせ、選考に参加してくれたことへの感謝を伝えます。その上で、改めて入社意思の有無を口頭で確認します。
電話連絡の場合、このときに候補者の反応を直接感じ取れることも大きなメリットです。
声のトーンや質問内容から、入社への期待度や懸念点を把握できるかもしれません。
最後に、内定通知書などの関連書類を近日中に送付する旨を伝え、今後の流れを簡潔に説明しましょう。
一般的に送付する書類は、内定通知書、内定承諾書、労働条件通知書、そして返信用封筒などです。
郵送の場合は、送付状(添え状)を同封するのがビジネスマナーとして適切です。
近年では、PDF形式の書類をメールで送付する企業も増えています。
どちらの方法を選択するにせよ、候補者が必要な情報を正確に受け取れるよう、書類に不備がないか、宛先が正しいかを十分に確認してから送付することが求められます。
内定承諾書は、候補者が企業の提示した条件に同意し、入社することを約束する意思表示の書類です。
この書類を企業が受領した時点で、正式に労働契約が成立したとみなされます。
内定通知書で指定した返送期限までに承諾書が届かない場合は、電話やメールで状況を確認しましょう。
承諾書を受け取った後は、「書類を確かに受領いたしました」という旨を候補者に一報入れると、より丁寧な印象を与え、候補者の安心につながります。
これで内定から承諾までの一連の手続きが完了となります。
この段階での対応が、候補者の入社意欲を左右し、内定辞退のリスクを低減させる鍵となります。
手続きをスムーズに進めることで、候補者に安心感を与え、企業への信頼を深めてもらうことが可能です。
ここでは、内定通知から承諾書の回収までを、具体的な3つのステップに分けて解説し、人事担当者が確実に行うべき実務の流れを整理します。
ステップ1:合格の連絡をして入社の意思を確認
最終面接の合格が決まったら、まずは電話やメールで候補者に連絡するのが最初のステップです。書類の送付よりも早く結果を伝えられるため、候補者の喜びや安心につながります。
連絡の際には、まず合格したことを知らせ、選考に参加してくれたことへの感謝を伝えます。その上で、改めて入社意思の有無を口頭で確認します。
電話連絡の場合、このときに候補者の反応を直接感じ取れることも大きなメリットです。
声のトーンや質問内容から、入社への期待度や懸念点を把握できるかもしれません。
最後に、内定通知書などの関連書類を近日中に送付する旨を伝え、今後の流れを簡潔に説明しましょう。
ステップ2:内定通知書や入社関連書類を郵送またはメールで送付
電話またはメールでの速報後、速やかに内定通知書をはじめとする入社関連書類を送付します。このステップは、口頭での連絡を正式な形で記録に残す重要な手続きです。一般的に送付する書類は、内定通知書、内定承諾書、労働条件通知書、そして返信用封筒などです。
郵送の場合は、送付状(添え状)を同封するのがビジネスマナーとして適切です。
近年では、PDF形式の書類をメールで送付する企業も増えています。
どちらの方法を選択するにせよ、候補者が必要な情報を正確に受け取れるよう、書類に不備がないか、宛先が正しいかを十分に確認してから送付することが求められます。
ステップ3:内定承諾書を返送してもらい正式に手続き完了
最終ステップは、候補者から内定承諾書を返送してもらうことです。内定承諾書は、候補者が企業の提示した条件に同意し、入社することを約束する意思表示の書類です。
この書類を企業が受領した時点で、正式に労働契約が成立したとみなされます。
内定通知書で指定した返送期限までに承諾書が届かない場合は、電話やメールで状況を確認しましょう。
承諾書を受け取った後は、「書類を確かに受領いたしました」という旨を候補者に一報入れると、より丁寧な印象を与え、候補者の安心につながります。
これで内定から承諾までの一連の手続きが完了となります。
内定通知書に必ず記載すべき項目リスト
内定通知書は、採用決定を伝えるだけでなく、労働契約の申し込みという法的な意味合いを持つ非常に重要な書類です。そのため、記載内容に漏れや曖昧な点があると、後々のトラブルの原因になりかねません。
候補者が安心して内定を承諾し、スムーズに入社手続きを進められるようにするためには、必要事項を正確かつ明確に記載することが不可欠です。
ここでは、人事担当者が内定通知書を作成する際に、必ず盛り込むべき基本的な項目をリストアップして解説します。
「拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、先日の選考の結果、慎重に審議を重ねました結果、貴殿の採用を決定いたしましたので、ここにご通知申し上げます。」
といったように、お祝いの言葉とともに、採用が確定した旨をはっきりと伝えましょう。
曖昧な表現は候補者に混乱や不安を与える可能性があるため避けるべきです。
また、これまでの選考に参加してくれたことへの感謝の意を添えることで、より丁寧でポジティブな印象を与えることができます。
返送期限は、一般的に通知日から1週間〜1ヶ月程度で設定されることが多いですが、候補者の事情も考慮して、あまりに短期間に設定することは避けるべきです。
具体的に「◯年◯月◯日必着」と日付を明確に記載します。
あわせて、提出方法についても「同封の返信用封筒にてご返送ください」や「PDFに署名の上、メールにてご返信ください」など、具体的な手順を案内します。
これにより、候補者は何をすべきかが明確になり、手続きがスムーズに進みます。
新卒採用であれば「入社予定日:◯年4月1日」のように、中途採用であれば双方で合意した日付を記載しましょう。
また、入社日までの間に、内定者懇親会、健康診断、事前研修などが予定されている場合は、その概要や日程もあわせて案内します。
今後のスケジュールを事前に知らせることで、候補者は予定を調整しやすくなり、入社までの期間を安心して過ごすことができます。
これは、入社意欲の維持や内定辞退の防止にも効果的です。
その際に、気軽に問い合わせができる窓口を明記しておくことは非常に重要です。
人事部の部署名、担当者の氏名、直通の電話番号、メールアドレスを正確に記載しましょう。担当者が明確であれば、候補者は誰に連絡すれば良いか迷うことがなく、安心して相談できます。
このような細やかな配慮が、企業への信頼感を高めることにつながり、内定者との良好な関係構築の第一歩となります。
問い合わせに対して迅速かつ丁寧に対応する体制を整えておくことも大切です。
候補者が安心して内定を承諾し、スムーズに入社手続きを進められるようにするためには、必要事項を正確かつ明確に記載することが不可欠です。
ここでは、人事担当者が内定通知書を作成する際に、必ず盛り込むべき基本的な項目をリストアップして解説します。
採用が決定したことを明確に伝える一文
内定通知書の冒頭には、選考の結果、採用が決定したことを誰が読んでもわかるように、明確な言葉で記載する必要があります。「拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、先日の選考の結果、慎重に審議を重ねました結果、貴殿の採用を決定いたしましたので、ここにご通知申し上げます。」
といったように、お祝いの言葉とともに、採用が確定した旨をはっきりと伝えましょう。
曖昧な表現は候補者に混乱や不安を与える可能性があるため避けるべきです。
また、これまでの選考に参加してくれたことへの感謝の意を添えることで、より丁寧でポジティブな印象を与えることができます。
入社承諾書の返送期限と提出方法
候補者が内定を承諾するかどうかを回答するための期限を明記することは、採用計画を円滑に進める上で不可欠です。返送期限は、一般的に通知日から1週間〜1ヶ月程度で設定されることが多いですが、候補者の事情も考慮して、あまりに短期間に設定することは避けるべきです。
具体的に「◯年◯月◯日必着」と日付を明確に記載します。
あわせて、提出方法についても「同封の返信用封筒にてご返送ください」や「PDFに署名の上、メールにてご返信ください」など、具体的な手順を案内します。
これにより、候補者は何をすべきかが明確になり、手続きがスムーズに進みます。
入社日や今後のスケジュールに関する案内
候補者が入社後の生活やキャリアプランを具体的にイメージできるよう、入社予定日を明確に記載します。新卒採用であれば「入社予定日:◯年4月1日」のように、中途採用であれば双方で合意した日付を記載しましょう。
また、入社日までの間に、内定者懇親会、健康診断、事前研修などが予定されている場合は、その概要や日程もあわせて案内します。
今後のスケジュールを事前に知らせることで、候補者は予定を調整しやすくなり、入社までの期間を安心して過ごすことができます。
これは、入社意欲の維持や内定辞退の防止にも効果的です。
問い合わせ先となる部署名と担当者連絡先
内定通知書を受け取った候補者は、書類の内容や今後の手続きについて疑問や不安な点が出てくる可能性があります。その際に、気軽に問い合わせができる窓口を明記しておくことは非常に重要です。
人事部の部署名、担当者の氏名、直通の電話番号、メールアドレスを正確に記載しましょう。担当者が明確であれば、候補者は誰に連絡すれば良いか迷うことがなく、安心して相談できます。
このような細やかな配慮が、企業への信頼感を高めることにつながり、内定者との良好な関係構築の第一歩となります。
問い合わせに対して迅速かつ丁寧に対応する体制を整えておくことも大切です。
内定通知書とあわせて送付するべき2つの重要書類
内定通知書を送付する際には、それ単体で送るのではなく、関連する重要な書類を同封することが一般的です。
これらの書類は、候補者に入社の意思を確認したり、労働条件を正式に提示したりする役割を担っており、後のトラブルを避けるためにも不可欠です。
特に「内定承諾書」と「労働条件通知書」は、法的な観点からも非常に重要な意味を持ちます。
ここでは、内定通知書とセットで送付すべきこれら2つの書類について、その役割と重要性を詳しく解説します。
内定誓約書と呼ばれることもあります。
この書類に候補者が署名・捺印し、企業に返送することで、双方の合意が形成され、労働契約が正式に成立します。
内定通知書で提示された条件に同意する旨の一文と、本人による署名・捺印欄、提出日を記載する欄を設けるのが一般的です。
企業はこの書類を回収・保管することで、候補者が入社を承諾したという明確な証拠を残すことができます。
契約期間、就業場所、業務内容、始業・終業時刻、休日、賃金の決定・計算方法、退職に関する事項など、法律で定められた項目を網羅的に記載する必要があります。
この書類は、候補者がどのような条件で働くことになるのかを正確に理解し、納得した上で内定を承諾するための重要な判断材料となります。
内定通知の段階で労働条件を明確に提示しておくことは、入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチや労務トラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。
これらの書類は、候補者に入社の意思を確認したり、労働条件を正式に提示したりする役割を担っており、後のトラブルを避けるためにも不可欠です。
特に「内定承諾書」と「労働条件通知書」は、法的な観点からも非常に重要な意味を持ちます。
ここでは、内定通知書とセットで送付すべきこれら2つの書類について、その役割と重要性を詳しく解説します。
入社の意思を確認するための「内定承諾書」
内定承諾書は、企業からの内定(労働契約の申し込み)に対して、候補者が承諾し、入社する意思があることを書面で示すための書類です。内定誓約書と呼ばれることもあります。
この書類に候補者が署名・捺印し、企業に返送することで、双方の合意が形成され、労働契約が正式に成立します。
内定通知書で提示された条件に同意する旨の一文と、本人による署名・捺印欄、提出日を記載する欄を設けるのが一般的です。
企業はこの書類を回収・保管することで、候補者が入社を承諾したという明確な証拠を残すことができます。
雇用条件を明記した「労働条件通知書」
労働条件通知書は、労働基準法第15条に基づき、企業が労働者に対して明示することが義務付けられている労働条件を記載した書類です。契約期間、就業場所、業務内容、始業・終業時刻、休日、賃金の決定・計算方法、退職に関する事項など、法律で定められた項目を網羅的に記載する必要があります。
この書類は、候補者がどのような条件で働くことになるのかを正確に理解し、納得した上で内定を承諾するための重要な判断材料となります。
内定通知の段階で労働条件を明確に提示しておくことは、入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチや労務トラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。
人事担当者が押さえておきたい内定の法的効力と注意点
内定通知は、単に「合格おめでとう」と伝える行為ではありません。法的には、企業と候補者との間で労働契約が成立したことを意味する、非常に重要な手続きです。
この法的効力を正しく理解していないと、安易な内定取り消しが「不当解雇」とみなされ、深刻な労務トラブルに発展するリスクがあります。
人事担当者としては、候補者の権利を守り、企業のコンプライアンスを遵守する観点から、内定にまつわる法的な知識と注意点を正確に把握しておく必要があります。
これは、「入社予定日を勤務開始日とし、それまでの期間に内定時に定めた取り消し事由が発生した場合には、企業は労働契約を解約できる権利を持つ」という特殊な労働契約です。
つまり、内定を出した時点で、単なる口約束ではなく、法的な拘束力を持つ契約関係が始まっていると認識しなくてはなりません。
この理解が、後のトラブルを未然に防ぐための第一歩となります。
したがって、内定取り消しが有効と認められるのは、非常に限定的なケースです。
具体的には、内定当時に知ることができなかった重大な経歴詐称が発覚した場合や、卒業を条件としていた学生が単位不足で卒業できなかった場合など、「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と是認できる」場合に限られます。
単なる業績の悪化や、他のより優秀な人材が見つかったといった理由での内定取り消しは、不当解雇として無効になる可能性が極めて高いことを理解しておくべきです。
候補者には憲法で保障された「職業選択の自由」があり、複数の内定先を比較検討し、熟慮する時間が必要です。
特に新卒採用の場合、他社の選考がまだ続いていることも少なくありません。
1週間以内など、極端に短い期限を設定して決断を迫る行為は、候補者に不誠実な印象を与え、場合によってはトラブルの原因にもなり得ます。
候補者から期限の延長を相談された際には、可能な範囲で柔軟に対応するなど、相手の立場に配慮した姿勢が企業の信頼性を高めます。
この法的効力を正しく理解していないと、安易な内定取り消しが「不当解雇」とみなされ、深刻な労務トラブルに発展するリスクがあります。
人事担当者としては、候補者の権利を守り、企業のコンプライアンスを遵守する観点から、内定にまつわる法的な知識と注意点を正確に把握しておく必要があります。
内定通知の時点で労働契約が成立することを理解する
過去の判例において、企業による採用内定通知と、それに対する候補者からの入社承諾書の提出によって、「始期付解約権留保付労働契約」が成立すると解釈されています。これは、「入社予定日を勤務開始日とし、それまでの期間に内定時に定めた取り消し事由が発生した場合には、企業は労働契約を解約できる権利を持つ」という特殊な労働契約です。
つまり、内定を出した時点で、単なる口約束ではなく、法的な拘束力を持つ契約関係が始まっていると認識しなくてはなりません。
この理解が、後のトラブルを未然に防ぐための第一歩となります。
客観的に合理的な理由がない内定取り消しは無効となる
内定によって労働契約が成立しているため、企業が一方的に内定を取り消すことは、法律上「解雇」と同じ扱いを受けます。したがって、内定取り消しが有効と認められるのは、非常に限定的なケースです。
具体的には、内定当時に知ることができなかった重大な経歴詐称が発覚した場合や、卒業を条件としていた学生が単位不足で卒業できなかった場合など、「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と是認できる」場合に限られます。
単なる業績の悪化や、他のより優秀な人材が見つかったといった理由での内定取り消しは、不当解雇として無効になる可能性が極めて高いことを理解しておくべきです。
内定承諾の期限は候補者に配慮して設定する
内定通知書に記載する内定承諾書の返送期限は、企業側の都合だけで一方的に短く設定すべきではありません。候補者には憲法で保障された「職業選択の自由」があり、複数の内定先を比較検討し、熟慮する時間が必要です。
特に新卒採用の場合、他社の選考がまだ続いていることも少なくありません。
1週間以内など、極端に短い期限を設定して決断を迫る行為は、候補者に不誠実な印象を与え、場合によってはトラブルの原因にもなり得ます。
候補者から期限の延長を相談された際には、可能な範囲で柔軟に対応するなど、相手の立場に配慮した姿勢が企業の信頼性を高めます。
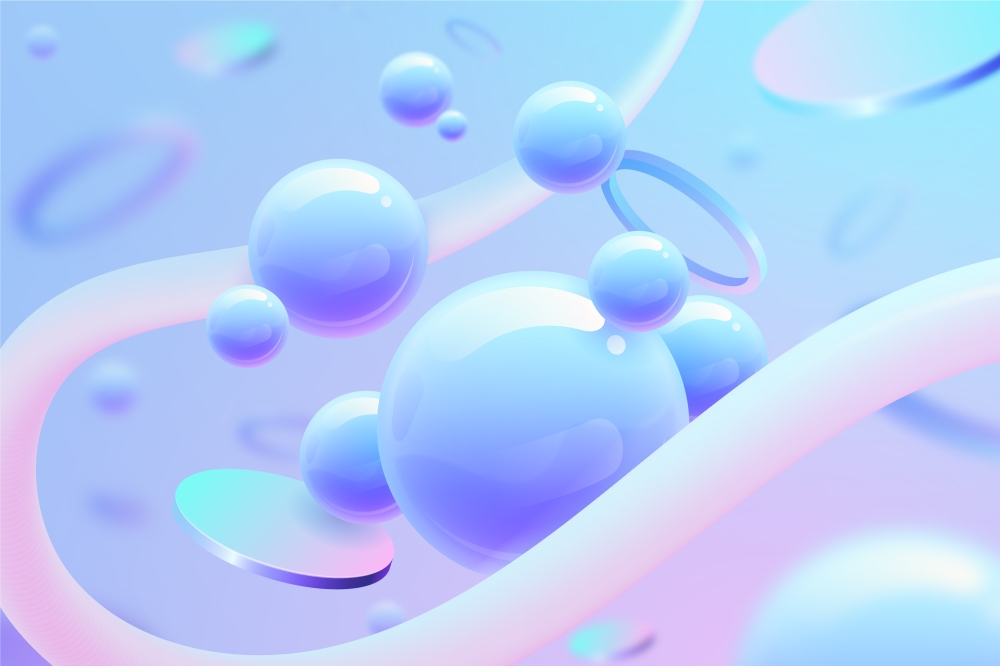
内定辞退を防止するために人事が取り組むべきフォロー策
内定通知を出し、承諾を得た後も、採用活動は終わりではありません。
特に新卒採用など入社までの期間が長い場合、候補者は他社の選考結果を待ったり、友人や家族からの情報を得たりする中で、入社の意思が揺らぐことがあります。
いわゆる「内定ブルー」に陥るケースも少なくありません。
優秀な人材を確実に迎え入れるためには、内定承諾後から入社日までの間、継続的に候補者をフォローし、エンゲージメントを高めていく施策が不可欠です。
ここでは、内定辞退を防ぐための具体的なフォローアップ策を紹介します。
これを防ぐためには、人事担当者が定期的にコミュニケーションを取ることが効果的です。
例えば、月に一度のメールマガジンで会社の近況を伝えたり、電話やオンライン面談で個別に状況をヒアリングしたりします。
入社準備に関する質問に答えたり、些細な悩みを聞いたりするだけでも、内定者は会社とのつながりを感じ、安心感を得られます。
過度な連絡は負担になるため、適切な頻度と内容を心がけることが求められます。
特に年齢の近い若手社員との座談会や食事会を企画することで、内定者は仕事のやりがいや大変なこと、職場の雰囲気、プライベートとの両立など、リアルな情報を気兼ねなく質問できます。
人事担当者からでは伝えきれない、現場の生の声を聞くことで、会社への理解が深まり、親近感が湧きます。
こうした交流を通じて、内定者同士の横のつながりが生まれることも、入社へのモチベーション向上につながります。
内定者を対象とした職場見学を実施し、実際に業務を行うデスク周りや会議室、休憩スペースなどを案内します。
可能であれば、配属予定の部署で働く社員の仕事風景を短時間見学させてもらうのも良いでしょう。
自分が働く環境を具体的に目にすることで、入社後のイメージがより鮮明になり、「この場所で働きたい」という気持ちが高まります。
オンラインでのオフィスツアーなども、遠方の内定者には有効な手段です。
内定者のフォロー方法についてはこちらの記事も参考になります。
特に新卒採用など入社までの期間が長い場合、候補者は他社の選考結果を待ったり、友人や家族からの情報を得たりする中で、入社の意思が揺らぐことがあります。
いわゆる「内定ブルー」に陥るケースも少なくありません。
優秀な人材を確実に迎え入れるためには、内定承諾後から入社日までの間、継続的に候補者をフォローし、エンゲージメントを高めていく施策が不可欠です。
ここでは、内定辞退を防ぐための具体的なフォローアップ策を紹介します。
内定者と定期的に連絡を取り不安を解消する
内定から入社までの期間、企業からの連絡が途絶えると、内定者は「本当にこの会社で良いのだろうか」という不安や孤独感を抱きやすくなります。これを防ぐためには、人事担当者が定期的にコミュニケーションを取ることが効果的です。
例えば、月に一度のメールマガジンで会社の近況を伝えたり、電話やオンライン面談で個別に状況をヒアリングしたりします。
入社準備に関する質問に答えたり、些細な悩みを聞いたりするだけでも、内定者は会社とのつながりを感じ、安心感を得られます。
過度な連絡は負担になるため、適切な頻度と内容を心がけることが求められます。
先輩社員と交流できる座談会や食事会を開催する
内定者が入社後の働き方を具体的にイメージし、不安を払拭するためには、実際に働く先輩社員との交流機会を設けることが非常に有効です。特に年齢の近い若手社員との座談会や食事会を企画することで、内定者は仕事のやりがいや大変なこと、職場の雰囲気、プライベートとの両立など、リアルな情報を気兼ねなく質問できます。
人事担当者からでは伝えきれない、現場の生の声を聞くことで、会社への理解が深まり、親近感が湧きます。
こうした交流を通じて、内定者同士の横のつながりが生まれることも、入社へのモチベーション向上につながります。
実際の仕事風景がわかる職場見学を実施する
企業のウェブサイトやパンフレットだけでは伝わりにくい、オフィスの雰囲気や社員が働く様子を実際に見てもらうことも、内定辞退防止に効果があります。内定者を対象とした職場見学を実施し、実際に業務を行うデスク周りや会議室、休憩スペースなどを案内します。
可能であれば、配属予定の部署で働く社員の仕事風景を短時間見学させてもらうのも良いでしょう。
自分が働く環境を具体的に目にすることで、入社後のイメージがより鮮明になり、「この場所で働きたい」という気持ちが高まります。
オンラインでのオフィスツアーなども、遠方の内定者には有効な手段です。
内定者のフォロー方法についてはこちらの記事も参考になります。
まとめ
内定通知は、最終面接後1週間以内を目安に速やかに行うことが、候補者の入社意欲を維持する上で重要です。
この通知は法的に「始期付解約権留保付労働契約」の成立を意味するため、安易な取り消しは認められません。
通知の際には、内定承諾書や労働条件通知書を同封し、記載事項に漏れがないよう注意を払う必要があります。
また、内定承諾後から入社までの期間、定期的な連絡や社員との交流会などを通じて内定者をフォローし続けることが、内定辞退を防ぎ、優秀な人材を確実に確保することにつながります。
これらの手続きと注意点を正しく理解し、誠実な対応を実践することが、採用活動の成功に不可欠です。
内定辞退の防止についてはこちらの記事も参考になります。
この通知は法的に「始期付解約権留保付労働契約」の成立を意味するため、安易な取り消しは認められません。
通知の際には、内定承諾書や労働条件通知書を同封し、記載事項に漏れがないよう注意を払う必要があります。
また、内定承諾後から入社までの期間、定期的な連絡や社員との交流会などを通じて内定者をフォローし続けることが、内定辞退を防ぎ、優秀な人材を確実に確保することにつながります。
これらの手続きと注意点を正しく理解し、誠実な対応を実践することが、採用活動の成功に不可欠です。
内定辞退の防止についてはこちらの記事も参考になります。
ご不明点はお気軽にお問い合わせください
この度はリソースクリエイションにご興味を持ってくださいまして、誠にありがとうございます。
ご不明点・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。
殿堂入り記事
オススメ記事
オススメ記事
殿堂入り記事