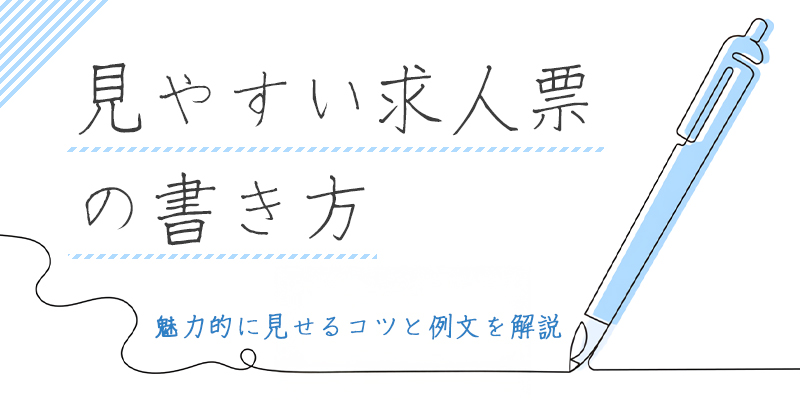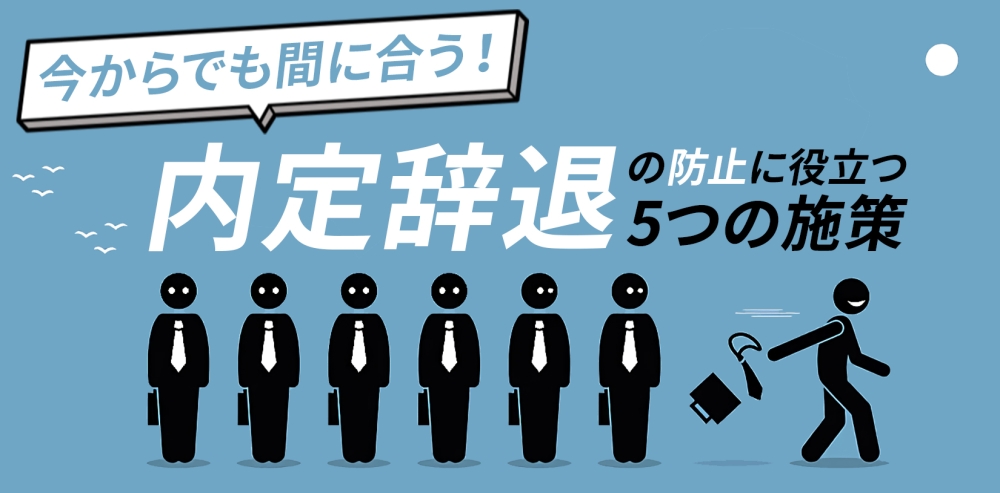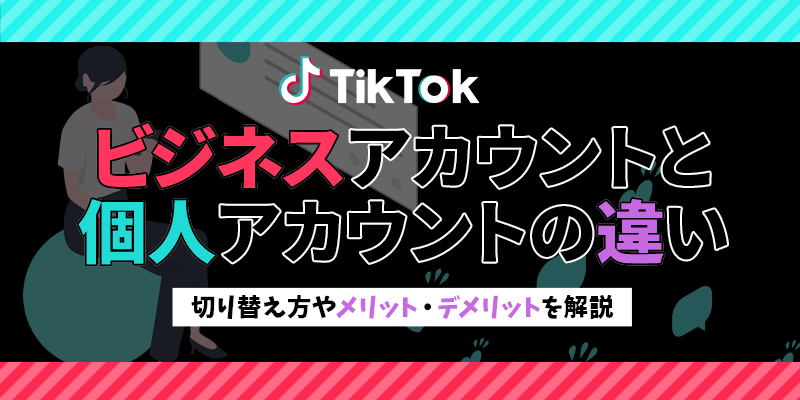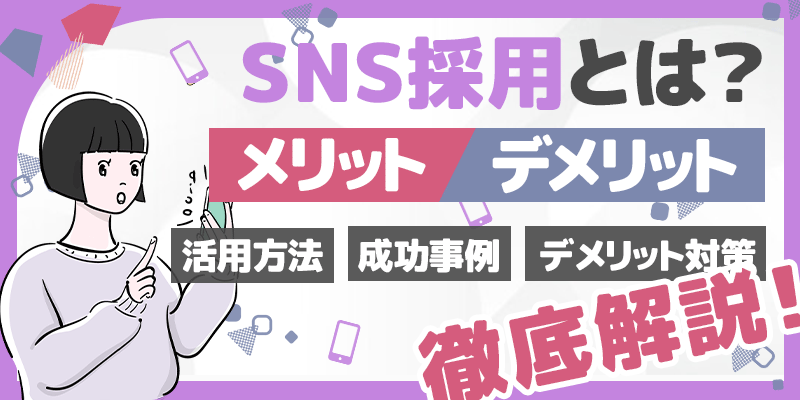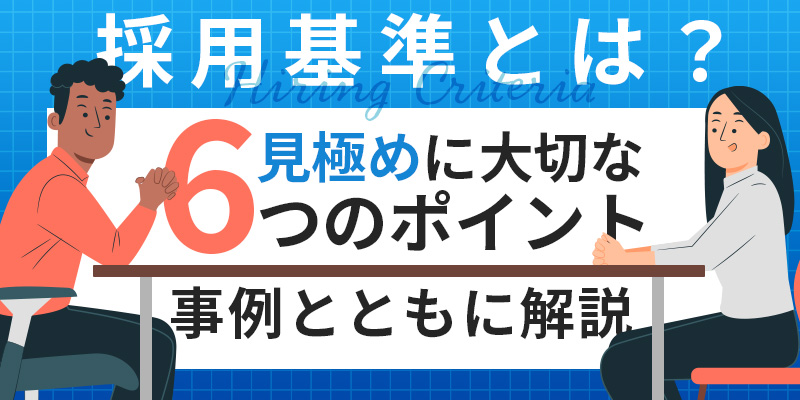SNS戦略
【採用広報とは?】企業が今行うべき戦略設計を成功事例付きで解説
更新日:2025.08.25
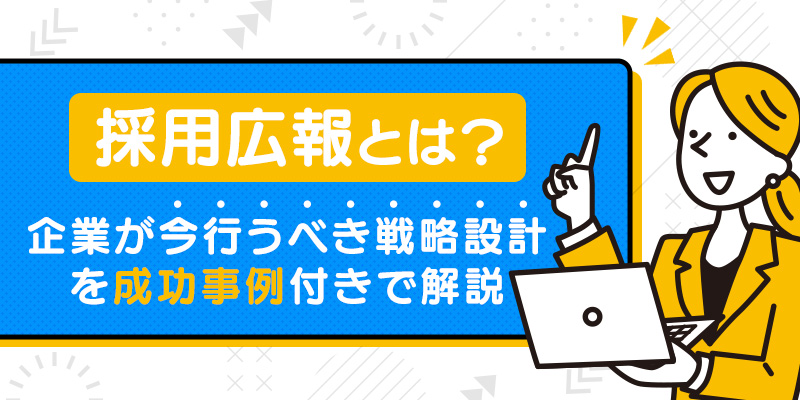
採用活動において、多くの企業が応募者数の減少やミスマッチといった課題に直面しています。こうした状況を打開するために注目されているのが「採用広報」です。 採用広報とは、企業自らが積極的に情報発信を行い、自社の魅力や価値観を求職者に伝え、共感を促す戦略的なコミュニケーション活動を指します。 本記事では、採用広報の基本から具体的な進め方、そして成功事例までを網羅的に解説し、採用活動に課題を感じている企業の経営者、人事担当者、採用担当者の方々が自社の採用力を向上させるためのヒントを提供します。
そもそも採用広報とは?目的や担当部門を解説
採用広報とは、企業が自社で働くイメージを持ってもらうために情報発信を行う活動です。 求人情報だけでなく、具体的な仕事内容や働き方、職場の雰囲気、企業理念や現場の声といったコンテンツを通じて、自社の魅力を伝えます。 その目的は、優秀な人材の確保と定着であり、人事部門だけでなく全社で取り組む広報活動として位置づけられます。 採用広報は、企業の認知度向上や入社後のミスマッチ防止にもつながる重要な仕事内容を含んでいます。
⇩求人情報だけでなく、仕事内容や働き方、企業理念などを通じて自社の魅力を伝えます。
なお、求人広告をどう活用するかについては、こちらの記事も参考になります!
採用広報の目的は優秀な人材の確保と定着
採用広報の主な目的は、自社が求める優秀な人材を確保し、長期的な定着へとつなげることです。 具体的には、転職を考えているキャリア層や新卒、中途採用の候補者に対して、企業のビジョンやカルチャー、仕事内容、働く環境などを多角的に発信します。 これにより、求職者は入社前に企業への理解を深め、自身のキャリアプランや価値観と企業との合致度を判断できるようになります。 結果として、入社後のミスマッチを防ぎ、高い定着率を実現することが期待されます。採用広報は人事だけでなく全社で取り組む活動
採用広報は、人事担当者や採用担当者だけの仕事ではなく、企業全体で取り組む広報活動です。 社員インタビューやオフィスの様子など、現場のリアルな情報を発信する際には、各部門の協力が不可欠となります。 発信内容が現場の実態と乖離していると、求職者が入社後にギャップを感じてしまう可能性があるため、採用部門だけでなく他部門からの理解と協力を得ることが重要です。 採用広報の目的や意義を全社で共有し、協力体制を構築することが成功の鍵となります。⇩求人情報だけでなく、仕事内容や働き方、企業理念などを通じて自社の魅力を伝えます。
なお、求人広告をどう活用するかについては、こちらの記事も参考になります!
採用広報が多くの企業で重要視される3つの理由
採用広報が多くの企業で重要視される背景には、採用市場の変化と求職者の意識変革があります。 従来の「待ち」の採用活動では優秀な人材の獲得が難しくなっており、企業は「攻め」の戦略として採用広報を取り入れる必要に迫られています。 具体的には、「転職潜在層へのアプローチ」「SNSやWebメディアの普及による情報収集の変化」「求職者が企業のリアルな情報を求めるようになった」の3つのトレンドが挙げられます。
⇩採用広報が多くの企業で重要視される背景には、採用市場の変化と求職者の意識変革があります。特に「人材不足」は大きな要因の一つです。この点については、こちらの記事で詳しく解説しています!
転職潜在層へのアプローチが必要になったため
現在の採用市場は売り手市場であり、転職を具体的に考えていない転職潜在層へのアプローチが不可欠となっています。 採用広報は、求人広告だけではリーチしにくいこれらの層に対し、企業の魅力や働く意義を継続的に発信することで、将来的な転職先候補として自社を意識してもらうためのマーケティング活動として機能します。SNSやWebメディアの普及で情報収集の方法が変化したため
SNSやWebメディアの普及は、求職者の情報収集の方法を大きく変化させました。 Twitter、YouTube、note、オウンドメディアなど、多様なチャネルを通じて企業に関する情報を手軽に入手できるようになり、求職者は多角的な視点から企業を評価するようになっています。 この変化に対応し、企業も積極的にSNSやWebメディアを活用した広報活動を展開することが、採用競争を勝ち抜く上で重要です。求職者が企業のリアルな情報を求めるようになったため
現代の求職者は、給与や福利厚生といった条件だけでなく、企業のビジョンや文化、実際に働く社員の仕事内容や人柄、職場の雰囲気など、よりリアルな情報を求めています。 採用広報では、社員インタビュー記事や動画コンテンツなどを通じて、企業のありのままの姿を伝えることで、求職者の企業理解を深め、共感を醸成することが可能です。⇩採用広報が多くの企業で重要視される背景には、採用市場の変化と求職者の意識変革があります。特に「人材不足」は大きな要因の一つです。この点については、こちらの記事で詳しく解説しています!
企業が採用広報に取り組む3つのメリット
企業が採用広報に取り組むことで、採用活動に多くのメリットがもたらされます。 企業の認知度向上、候補者の企業理解の深化による志望度アップ、そして入社後のミスマッチ防止による定着率改善などが挙げられます。 これらのメリットは、結果的に採用コストの削減や、企業の採用ブランディング強化にもつながります。
企業の認知度が向上し応募者数の増加につながる
採用広報によって企業が積極的に情報発信を行うことで、自社の認知度を向上させることが可能です。 転職を検討している顕在層だけでなく、転職潜在層へもリーチできるようになり、将来的に転職を考えた際に自社が選択肢の一つとして認識される可能性が高まります。 これにより、結果として応募者数の増加が期待できます。候補者の企業理解が深まり志望度が上がる
採用広報は、候補者の企業に対する理解を深め、志望度を高める効果があります。 企業のビジョンや文化、働く環境、社員のリアルな声などを伝えることで、候補者は「この企業で働きたい」という具体的なイメージを持ちやすくなります。 企業理解が深まることで、選考プロセスにおける意欲の向上や、内定承諾率の改善にもつながります。入社後のミスマッチを防ぎ定着率が改善する
採用広報は、入社後のミスマッチを防ぎ、社員の定着率を改善する上で非常に有効です。 企業のリアルな情報や課題までオープンに発信することで、求職者は入社前に職務内容や企業文化への理解を深め、「思っていたのと違った」という認識のズレを最小限に抑えることができます。 これにより、早期離職の防止や、入社後の活躍にもつながるメリットがあります。採用広報の戦略的な進め方5ステップ
採用広報を成功させるには、効果的な戦略設計が不可欠です。闇雲に情報発信するのではなく、計画的に進めることで、求める人材の獲得へとつながります。 具体的なやり方としては、 「採用課題を明確にし目的を設定する」 「ターゲットとなる理想の人物像(ペルソナ)を決める」 「ターゲットに響く自社の魅力を洗い出す」 「伝える内容に合った発信メディアを選定する」 「効果を測定するためのKPIを設定する」 の5つのステップがあります。
STEP1. 採用課題を明確にし目的を設定する
採用広報を始める上で、まず「何のために情報発信をするのか」という目的を明確に設定することが重要です。 たとえば、「認知度が低く応募数が少ない」という課題があるなら、まずは企業のミッションや事業内容を知ってもらうことを目的に、広範囲への情報発信が必要です。 一方、「応募数は多いがミスマッチによる早期離職が多い」という課題がある場合は、社員インタビューや福利厚生など、働き方に関する情報発信が効果的となるでしょう。 解決したい採用課題を明確にし、それに合わせた具体的な目標を設定することが、採用広報の目的達成への第一歩となります。STEP2. ターゲットとなる理想の人物像(ペルソナ)を決める
採用広報の戦略を効果的に進めるためには、「誰に、何を伝えたいか」を明確にする必要があります。 そのために、ターゲットとなる理想の人物像、すなわち「採用ペルソナ」を設定することが重要です。年齢、性別、スキル、経験といった基本的な情報だけでなく、希望年収、キャリア形成の志向、仕事への価値観、ワークライフバランスの重視度など、細かな点まで具体的に設定することで、よりターゲットに響くメッセージを発信できるようになります。 このマーケティング的なアプローチが、採用広報の精度を高めます。STEP3. ターゲットに響く自社の魅力を洗い出す
ターゲットとなるペルソナが明確になったら、そのターゲットに響く自社の魅力を具体的に洗い出しましょう。 企業が持つ魅力は多岐にわたりますが、ただ羅列するだけでなく、ターゲットの価値観やニーズに合致する視点から言語化することが重要です。 事業内容、社員の働き方、企業文化、制度、キャリアパス、会社の将来性など、多様なコンテンツを検討し、採用ブランディングに繋がる情報を整理します。STEP4. 伝える内容に合った発信メディアを選定する
ターゲットに響く自社の魅力が洗い出せたら、次に伝える内容に合った発信メディアを選定します。 若年層がターゲットであればSNS(Twitter、YouTubeなど)、企業の深い想いや文化を伝えたい場合はnoteやオウンドメディアが適しています。 各メディアやチャネルにはそれぞれの特性があるため、コンテンツの内容やターゲット層との相性を考慮して、最適な媒体やツールを選択しましょう。 Wantedlyのような採用特化型SNSも有効な手段の一つです。STEP5. 効果を測定するためのKPIを設定する
採用広報の効果を最大化するためには、具体的な目標達成度を測るためのKPI(重要業績評価指標)を設定することが不可欠です。 たとえば、Webサイトやコンテンツへの流入数(PV数)、応募数、選考参加数、内定承諾率、入社後の定着率などがKPIとして設定されます。 KPIを設定することで、採用広報活動の進捗状況や成果を客観的に把握し、どの施策が効果的であったか、どの企画に課題があるのかを明確にできます。 定期的に効果を測定し、PDCAサイクルを回すことで、継続的な改善と目標達成に繋げられるでしょう。【目的別】採用広報で活用したいおすすめの手法5選
採用広報には様々な手法がありますが、目的やターゲットに合わせて効果的な施策を選択することが重要です。 手軽に始められるSNSから、企業の想いを深く伝えられるブログ・note、自由度の高いオウンドメディア、リアルな雰囲気を伝えられる動画コンテンツ、そして候補者と直接交流できるイベントまで、多様なツールやチャネルがあります。 これらの手法を適切に組み合わせることで、採用活動をより有利に進められます。
手軽に始められる「SNS(Twitter, Instagramなど)」
SNSは、手軽に始められる採用広報の手法として多くの企業が活用しています。 TwitterやInstagramなどのSNSは拡散性が高く、企業の知名度が低い場合でも多くの求職者にリーチできる可能性があります。 日常の業務風景や社員の紹介、社内イベントの様子などを動画や画像と共に発信することで、企業のリアルな雰囲気を伝え、親近感を醸成することが可能です。 また、採用関連のハッシュタグを活用したり、フォロワーとのコミュニケーションを積極的に行うことで、エンゲージメントを高め、応募へとつなげる効果が期待できます。企業の想いやストーリーを伝える「ブログ・note」
ブログやnoteは、企業の想いやストーリー、文化などを深く伝えることができるテキストコンテンツとして有効です。 社内での出来事や社員の様子を記事として発信することで、求職者は企業風土や職場の雰囲気を詳細に理解し、働くイメージを具体的に持つことができます。 特に、社員のインタビュー記事や経験談は、求職者にとって信頼性が高く、共感を呼びやすい情報源となります。 これにより、入社後のミスマッチ防止にもつながるでしょう。自由度の高い情報発信ができる「オウンドメディア」
オウンドメディアは、自社で運営する採用に特化したメディアであり、求人媒体と比較して自由度の高い情報発信が可能です。 企業のビジョン、文化、事業内容、社員インタビュー記事など、多岐にわたるコンテンツを掲載することで、求職者は企業の魅力を多角的に理解できます。 特に、まだ転職願望がない潜在層へのアプローチに有効で、長期的な採用ブランディングに貢献します。 オウンドメディアを通じて企業理解を深めた候補者は、入社後のカルチャーフィットも高く、定着率の改善にもつながります。リアルな雰囲気を伝えられる「動画コンテンツ(YouTubeなど)」
動画コンテンツは、企業のリアルな雰囲気を効果的に伝えられる手法です。 YouTubeなどを活用して、オフィスツアー動画、社員の1日の様子、社内イベントの風景などを発信することで、求職者は視覚的に企業の文化や働き方を理解しやすくなります。 文章だけでは伝わりにくい情報を、動画ならではの臨場感で届けることで、応募者に強い印象を与え、入社後のミスマッチ低減にも繋がると期待されます。候補者と直接交流できる「オンライン/オフラインイベント」
オンライン/オフラインのイベントは、候補者と直接交流し、企業の魅力を伝える貴重な機会となります。 会社説明会やミートアップ、インターンシップなどを開催することで、一方的な情報発信に留まらず、求職者の疑問や不安を解消し、相互理解を深めることが可能です。 イベントでのインタビューや座談会を通じて、社員の生の声を聞いてもらうことで、求職者はより具体的に働くイメージを描き、企業への志望度を高めることができます。採用広報を成功させるために押さえておきたい3つのポイント
採用広報を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。 単に情報を発信するだけでなく、企業のビジョンを一貫して伝え、現場社員のリアルな声を活用し、ターゲットと目的に合わせたコンテンツを継続的に提供することが、効果的な採用広報につながります。 これらの点を意識することで、採用活動の成果を最大化し、長期的な採用力の向上を目指せます。
企業のビジョンやパーパスを一貫して発信する
採用広報を成功させるには、企業のビジョンやパーパスを、発信する全てのコンテンツにおいて一貫して伝えることが重要です。 求職者は、給与や福利厚生だけでなく、企業の目指す方向性や社会貢献性、働く意味に共感できるかを重視しています。 企業の核となるメッセージを明確にし、それを軸として情報発信を行うことで、自社の採用ブランディングを強化し、価値観に共感する人材を惹きつけることができます。現場で働く社員に協力してもらいリアルな声を届ける
採用広報において、現場で働く社員の協力は不可欠です。 社員インタビュー記事や、実際の仕事風景、職場の雰囲気を伝えるコンテンツは、求職者にとって非常に信頼性が高く、企業のリアルな姿を伝える上で大きな効果を発揮します。 社員が自社の魅力を語ることで、求職者は働くイメージを具体的に持つことができ、入社後のミスマッチを防ぐことにもつながります。ターゲットと目的に合わせたコンテンツを継続的に提供する
採用広報を成功させるためには、ターゲットとする求職者層と設定した目的に合わせて、適切なコンテンツを継続的に提供し続けることが重要です。 短期的な成果だけでなく、長期的な視点を持って企画を立て、質の高いコンテンツを定期的に発信することで、企業の認知度を高め、求職者との関係性を深めていくことができます。 効果測定を行いながら、コンテンツ内容や施策を改善していくPDCAサイクルを回すことも大切です。取り組みから学ぶ!採用広報の成功事例
採用広報を効果的に進める上で、他社の成功事例から学ぶことは非常に有益です。 メルカリのSNS活用、Wantedlyのブログを通じたカルチャー発信、レバレジーズの経営層によるビジョン共有など、様々な企業が独自の戦略で採用広報を成功させています。 これらの事例は、スタートアップ企業から中小企業まで、規模を問わず多くの企業にとって参考になるでしょう。
SNSで社員の日常を発信し親近感を醸成した事例
株式会社メルカリは、採用オウンドメディア「メルカン」の運営に加え、SNSを活用して社員のインタビューや日常を伝えるコンテンツを毎日更新し、親近感を醸成しています。 特にInstagramでは、「内定者の就活秘話」や「選考対策や就活アドバイス」など、学生の興味を引く情報を発信することで、応募者数が約2割増加した事例もあります。 SNSは、スタートアップ企業など知名度が低い企業でも、拡散性を利用して効果的に認知度を高め、採用に繋げられる手法です。独自のカルチャーをブログで伝え共感を呼んだ事例
Wantedlyを利用している企業の中には、自社のブログを通じて独自のカルチャーや社員の経験談を発信し、共感を呼んでいる事例が多くあります。 例えば、某SaaSベンダー企業では、採用ターゲットに近い社員へのインタビューを実施し、自社の魅力や課題をオープンに発信することで、応募数増加に成功しました。 また、株式会社freeeも新卒・中途採用それぞれのブログで社員インタビューを掲載し、企業カルチャーを深く伝えることで、カルチャーマッチ採用に大きな効果を上げています。このような記事コンテンツは、候補者が企業の解像度を深める上で非常に有効です。経営層が自社のビジョンを語りファンを獲得した事例
経営層が自社のビジョンやパーパスを積極的に語る採用広報は、企業のファンを獲得し、優秀な人材を引き寄せる上で非常に効果的です。 例えば、リクルートやレバレジーズといった企業では、経営層のインタビュー記事やメッセージを通じて、企業の目指す方向性や大切にしている価値観を強く発信しています。 これにより、求職者は企業の将来性や社会貢献性について深く理解し、共感を覚えることで、高い志望度を持って応募するようになります。 企業のトップが自らの言葉で語ることは、求職者にとって大きな安心感と信頼感を与え、採用ブランディングにも繋がります。まとめ
採用広報とは、企業が自社の魅力を積極的に発信し、求める人材を惹きつけるための戦略的な広報活動です。応募者数の増加、企業理解の深化、入社後のミスマッチ防止など、多くのメリットがあります。 採用広報を成功させるには、まず採用課題を明確にし、ターゲットとなるペルソナを設定した上で、ターゲットに響く自社の魅力をコンテンツとして洗い出すことが重要です。その上で、SNS、ブログ、オウンドメディア、動画コンテンツ、イベントなど、多様な手法の中から最適なチャネルを選び、継続的に情報提供を行う必要があります。 効果測定のためのKPI設定も忘れずに行い、PDCAサイクルを回しながら採用広報の精度を高めていきましょう。本記事で紹介した成功事例も参考に、自社に合った戦略を設計し、採用活動を有利に進めてください。
ご不明点はお気軽にお問い合わせください
この度はリソースクリエイションにご興味を持ってくださいまして、誠にありがとうございます。
ご不明点・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。
殿堂入り記事
オススメ記事
殿堂入り記事